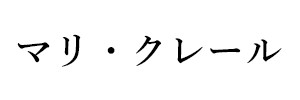書評
『ニューロン人間』(みすず書房)
この本の標題になっている『ニューロン人間』というのは、中身にそいながらいえば、人間は、身体を動かす行動も、感覚やこころの動きも、大脳皮質のなかのニューロン(神経細胞)の特定の集まりのはたらきによって惹き起されるものですよ、という意味になる。そんなことはわかっているという常識や先入見もあれば、身体の行動ならともかく、感覚やこころの動きが、大脳皮質のなかのニューロンのある固有の集まりのはたらきと一義的(アインドイッテッヒ)に結びつけられるはずがないという常識や先入見もある。そしてどちらも距離の概念と関係という概念とを、どう解釈するかによって、それぞれ正当さをもっている。わたしたちは心身が関わりあう領域で、たくさんの高度な論議を、宗教と哲学と科学のあいだでつみ重ねてきたし、それが人間の精神の歴史の核に、いつも横たわっているといってもいい。偉大な宗教家も哲学者も科学者も、この問題についてだけは、ぴたりと合った答えをだしたことはないし、いまもない。なぜかというと、このばあい答えが合うことと、答えが合うというのはどういうことかを解明することが、おなじ課題にふくまれてしまうから、答えが合ったことを立証したことと、答えが合ったと主観的におもい込むこととは、きりはなすことができない。これは量子論の不確定性原理と似たところがあるといっていい。でも何も神秘的なところはないから、やがて解明されるにきまっているのだが、現在のような水準の論議では、宗教も哲学も科学もこれを解くことができないから、ねばり強く論議のレベルがパラー位置に移るまで、肉迫をつづけるよりほかない。
この本は、そのパラー位置に論議のレベルを肉迫させていて、久しぶりに興奮しながら読みおえた。古代から現在までの心身の関わりあう領域についての哲学と科学の論議を集約し、それをまた人間の大脳のはたらきについての哲学と科学の論議に集約し、最後に大脳皮質のニューロンのはたらきに関係づけて集約し、ほんとうの神経生理学の専門家を除けば、あっと驚くようなニューロンについての知見に結びつけている。しかもほんとうの神経生理学の専門家には、この本だけの問題を人間についての科学や哲学の考察の広場へもちだすことはできないとおもわれる。
この本の著者の啓蒙線にそっていうと、人間の大脳皮質の左右のふたつの半球は、表面が二千二百平方センチあり、そこに三百億くらいのニューロンを含んでいる。そして常識に反してニューロンはそれぞれ離れて孤立してならんでいて、細胞体からでている軸索という突起にそってシナプス(神経連結)を介してだけつながった状態になっている。そして神経の信号は、細胞体からでている軸索にそった振動方向をもち、音の速さよりおそい速度で伝播してゆく。この伝播は電流のように流れるのではなく、陰性の波のように、毎秒〇・一メートルから百メートルくらいの速さで、毎秒一ミリから数ミリしか持続しないインパルス(刺戟波)として伝播する。
もうすこしさきまで著者の啓蒙にそって知識を頂戴してみる。ニューロンはそれぞれ膜につつまれている。そしてこの膜の内部ではナトリウムイオン(Na+)の濃度が、膜の外にくらべて十分の一であり、逆にカリウムイオン(K+)の濃度は、膜の外にくらべて十倍の濃度をもっている。そしてニューロンの膜の内は電位が高く、膜の外は電位が低くなっている。この膜は透過膜(イオンを通す膜)で、静止しているときはカリウムイオンだけを通し、ナトリウムイオンは通さない。この膜の内外のイオンの濃度の差で電位の差ができ、これが神経インパルスのもとになる。そのことはよくわかった。ではこの膜の内外のイオン濃度の差は、どうしてできるのか。ある種のタンパク質が酵素のポンプとしてはたらき、イオンをとらえては他方の側に送りこんでいる。ではこの酵素ポンプを作動させるエネルギーはどこから供給されるのか。それは細胞呼吸によって生みだされるATPの分子がこわされるときのエネルギーだ。
さて、あらゆる生物の行動は「精神細胞の一定の集まりを動員している」から、動員された部分の神経細胞や数や形や動員のされ方と、生物のこころと身体の行動とのあいだに、ある対応関係がみつけられれば、わたしたちは心身の関わりあう領域について、現在までどんな宗教も哲学も科学もたどりつけなかったところへ、一歩ふみこめたことになる。そしてこの本がほんとうに圧巻だなとおもえるところもまた、それを記述している個所にあるといえよう。
例えば「渇き」という言葉で、わたしたちはのどが渇くというように、身体的にもつかうし、こころの渇きというように渇望、願望をもとめるこころの欠如の意味にもつかう。いいかえれば「渇き」は身体の欲求からはじまってこころにまで影響をあたえることのひとつだ。著者によればこの「渇き」に関わっている大脳のニューロンは、視床の下部に局在している。そしてこのばあいニューロンのはたらきを活性化しているのは、ペプチドのうちの一種で、八個のアミノ酸がつながってできているアンギオテンシンIIという化合物である。この化合物を血液内に注入するか、あるいは大脳の視床下部のしかるべき領域にじかに投与するとインパルスの仕掛けが動きはじめ、この化合物の濃さがある値をこえると、生物は水分を飲みはじめる。生物の身体にそくしていえば、アンギオテンシンIIが神経系に水分が不足してくると危険だという信号をおくる。腎臓が血液のなかへこの物質をみちびき入れるように反応し、その濃度が高まってくると大脳の「渇き」をつかさどる特定領域のニューロンを活性化させて、水分をとることを促しはじめることになる。ここでは何が新しい知見かといえば、アンギオテンシンIIという化合物が「渇き」のニューロンにはたらきかけることなしには、のどの渇きもそれから波紋をひろげるこころの渇きやそれを充たそうとする願望が起されることはないことを確定したことだ。するとわたしたちは、ニューロンがいっぱいつまった大脳の暗箱を介して行われるこころと身体の関わりについて、不明確であいまいだった領域を一歩せばめていったことになる。
わたしはたまたま痛みに悩まされたばかりで、いまもその続きを体験しているところなのでそのことをとりあげれば、痛みはたいていの身体の器官、たとえば内臓とか、皮膚表面に分布した神経の末端の刺戟から起される。暑さ、寒さ、圧力、打撲などはそれだし、内臓の病変でも起される。どうして痛みが起るかといえば、刺戟とか病変とかによって身体のなかに、プロスタグランジンE2という化合物がつくられ、これが脊髄の神経節の細胞体にインパルスを伝え、その痛みのニューロンが仲介するニューロンとシナプスをつくりだして大脳まで伝播してゆくからだ。この化合物はアスピリンによって合成が阻止される。アスピリンを投与したら痛みが和らいだとか止ったとかいうのはこのことを指している。痛みの化合物は、もちろんたくさんの種類が見つかっている。痛みは渇きにくらべればこころの領域がすこし多いということができよう。この本の著者は、こんなふうに次第にこころの動きのおおい方へ、読者をつれていってくれる。その間の記述、たとえば快感や性のオルガスムについても、どんな斬新なことがいわれているか計りしれない。ゆとりがあればまたたち返るとして、わたしがいちばん感銘をうけた問題にすぐに入ってゆくとする。
人間の感覚の器官を介して入ってくる情報は、以前から視床を中継として経たうえで、大脳の皮質のあるはっきりと区別できる領野に投射されることが知られている。視覚にたいしては後頭部のあたりの皮質の領野に、触覚は頭のてっぺんの部分に位置している。つまりそれぞれの皮質の表面に感覚器官が感受する物理的なデータが表現されていることになる。もっとこまかくいうと皮質にはそれぞれの感覚器官が受け入れた物の縮尺の地図が描かれる。例えば触覚を例にとる。サルの親指を局所で刺戟し、これをその感覚に固有な領野(頭頂葉の一、二、二野)のレベルで起る電気的な反応を記録してみる。電極をゆきあたりばったりにおいても、反応は観察できない。そこで皮質の領野のひとつの地点から他の地点へ、電極を決った仕方で移動させる。すると電位がきゅうにあがり、数ミリメートル這わせるとこの変化は消える。これで親指の反応は終って、つぎに人差指の反応に移る。そしてだんだん手が描かれてゆく。これをつぎつぎやってゆくと、ひとつの手が反応で描かれることになる。このやり方をなおつづけると、身体の半側全体があらわれてくる。こうやって大脳皮質の表面にトレースされてゆく小像は、サルに似はじめてくる。脳から頭のてっぺんまでのあいだ、舌、頭、前肢と手、後肢と足、尾ができてくる。これらは三次元のものが二次元に投影しているから歪みが起っている。この皮質に描かれた小像は、じっさいのサルの像とはちがうようにみえても、その人間がどんな感覚器官にふだん重要度を与えているかによって強調されたり、ひかえめに描かれたりしていて、外界との接触点の像を作っている。
わたしたちは大脳のはたらきを感覚器官とむすびつける経路が神経とインパルスによって成り立っていることは知っていた。しかしそれが皮質の表面にそのものの感受の仕方にしたがった縮図像を描くことまでは、まったく想像もしていなかった。べつな言葉でいえば、わたしたちが心身の相関する領域に与えていた錯綜したイメージにくらべて、はるかに単純で像的にはっきりした受容の仕方が成り立っているのだという印象をうけ、少なからず感銘をうけたといっていい。
さらにもう少しつっこんで感覚から神経のはたらきの領域に入ってゆくと、もっと驚きを感じさせられる。大脳皮質の機能の細分化のありさまをつきつめてゆくと、結局は個々の神経細胞そのものにゆきつくと、著者はいっている。ある細胞はただ一方の眼に反応し、べつの細胞は両方の眼に反応する。さらにべつの細胞は特別の方向をもった光線や特定の向きにうごく点に反応するということが起っている。わたしたちが「チェア」というとき、ルイ十三世風の椅子もあればルイ十六世風の椅子もあり、その他の様式のものもある。このさまざまな椅子のつくられた感覚像から、いま「チェア」の概念をつくろうとすれば、「細部の除外、図式化、さらには抽象化」が行われる。この概念-原型が大脳の皮質の細胞に記憶として留められて、「チェア」の知覚やイメージのような感覚像とつながりながら、しかもちがった純粋のこころの動きとしての概念が形成されてゆく。この本の著者の考え方は、知覚やイメージと概念とをおなじカテゴリーに包括させていることだ。それによって概念に対応する言語は、知覚やイメージと関連づけられることになる。これはわたしなどが近年とっているハイ・イメージ論の考え方と似ていて親近感をおぼえる。
ところで概念という純粋なこころのはたらきまできたとき、大脳がニューロン機械だという生物学との関連を捨てなければならないのだろうか。著者はネズミに光とそのあとの痛みを連動させた実験を例に、ネズミが反射以前に身動きしなくなるのは、概念の原型を記憶して恐怖するからで、けっして条件反射の行動ではないと注意している。いいかえれば、皮質の局部的な複数の領野を貫いて流れる鎖のようなつながりが、あらかじめ概念のわくをつくっているので、このばあいでも生物学的な接近が可能なことを示唆している。この本によってこころのはたらきから、不可知の膜が一枚はがされた気がする。
【この書評が収録されている書籍】
この本は、そのパラー位置に論議のレベルを肉迫させていて、久しぶりに興奮しながら読みおえた。古代から現在までの心身の関わりあう領域についての哲学と科学の論議を集約し、それをまた人間の大脳のはたらきについての哲学と科学の論議に集約し、最後に大脳皮質のニューロンのはたらきに関係づけて集約し、ほんとうの神経生理学の専門家を除けば、あっと驚くようなニューロンについての知見に結びつけている。しかもほんとうの神経生理学の専門家には、この本だけの問題を人間についての科学や哲学の考察の広場へもちだすことはできないとおもわれる。
この本の著者の啓蒙線にそっていうと、人間の大脳皮質の左右のふたつの半球は、表面が二千二百平方センチあり、そこに三百億くらいのニューロンを含んでいる。そして常識に反してニューロンはそれぞれ離れて孤立してならんでいて、細胞体からでている軸索という突起にそってシナプス(神経連結)を介してだけつながった状態になっている。そして神経の信号は、細胞体からでている軸索にそった振動方向をもち、音の速さよりおそい速度で伝播してゆく。この伝播は電流のように流れるのではなく、陰性の波のように、毎秒〇・一メートルから百メートルくらいの速さで、毎秒一ミリから数ミリしか持続しないインパルス(刺戟波)として伝播する。
もうすこしさきまで著者の啓蒙にそって知識を頂戴してみる。ニューロンはそれぞれ膜につつまれている。そしてこの膜の内部ではナトリウムイオン(Na+)の濃度が、膜の外にくらべて十分の一であり、逆にカリウムイオン(K+)の濃度は、膜の外にくらべて十倍の濃度をもっている。そしてニューロンの膜の内は電位が高く、膜の外は電位が低くなっている。この膜は透過膜(イオンを通す膜)で、静止しているときはカリウムイオンだけを通し、ナトリウムイオンは通さない。この膜の内外のイオンの濃度の差で電位の差ができ、これが神経インパルスのもとになる。そのことはよくわかった。ではこの膜の内外のイオン濃度の差は、どうしてできるのか。ある種のタンパク質が酵素のポンプとしてはたらき、イオンをとらえては他方の側に送りこんでいる。ではこの酵素ポンプを作動させるエネルギーはどこから供給されるのか。それは細胞呼吸によって生みだされるATPの分子がこわされるときのエネルギーだ。
さて、あらゆる生物の行動は「精神細胞の一定の集まりを動員している」から、動員された部分の神経細胞や数や形や動員のされ方と、生物のこころと身体の行動とのあいだに、ある対応関係がみつけられれば、わたしたちは心身の関わりあう領域について、現在までどんな宗教も哲学も科学もたどりつけなかったところへ、一歩ふみこめたことになる。そしてこの本がほんとうに圧巻だなとおもえるところもまた、それを記述している個所にあるといえよう。
例えば「渇き」という言葉で、わたしたちはのどが渇くというように、身体的にもつかうし、こころの渇きというように渇望、願望をもとめるこころの欠如の意味にもつかう。いいかえれば「渇き」は身体の欲求からはじまってこころにまで影響をあたえることのひとつだ。著者によればこの「渇き」に関わっている大脳のニューロンは、視床の下部に局在している。そしてこのばあいニューロンのはたらきを活性化しているのは、ペプチドのうちの一種で、八個のアミノ酸がつながってできているアンギオテンシンIIという化合物である。この化合物を血液内に注入するか、あるいは大脳の視床下部のしかるべき領域にじかに投与するとインパルスの仕掛けが動きはじめ、この化合物の濃さがある値をこえると、生物は水分を飲みはじめる。生物の身体にそくしていえば、アンギオテンシンIIが神経系に水分が不足してくると危険だという信号をおくる。腎臓が血液のなかへこの物質をみちびき入れるように反応し、その濃度が高まってくると大脳の「渇き」をつかさどる特定領域のニューロンを活性化させて、水分をとることを促しはじめることになる。ここでは何が新しい知見かといえば、アンギオテンシンIIという化合物が「渇き」のニューロンにはたらきかけることなしには、のどの渇きもそれから波紋をひろげるこころの渇きやそれを充たそうとする願望が起されることはないことを確定したことだ。するとわたしたちは、ニューロンがいっぱいつまった大脳の暗箱を介して行われるこころと身体の関わりについて、不明確であいまいだった領域を一歩せばめていったことになる。
わたしはたまたま痛みに悩まされたばかりで、いまもその続きを体験しているところなのでそのことをとりあげれば、痛みはたいていの身体の器官、たとえば内臓とか、皮膚表面に分布した神経の末端の刺戟から起される。暑さ、寒さ、圧力、打撲などはそれだし、内臓の病変でも起される。どうして痛みが起るかといえば、刺戟とか病変とかによって身体のなかに、プロスタグランジンE2という化合物がつくられ、これが脊髄の神経節の細胞体にインパルスを伝え、その痛みのニューロンが仲介するニューロンとシナプスをつくりだして大脳まで伝播してゆくからだ。この化合物はアスピリンによって合成が阻止される。アスピリンを投与したら痛みが和らいだとか止ったとかいうのはこのことを指している。痛みの化合物は、もちろんたくさんの種類が見つかっている。痛みは渇きにくらべればこころの領域がすこし多いということができよう。この本の著者は、こんなふうに次第にこころの動きのおおい方へ、読者をつれていってくれる。その間の記述、たとえば快感や性のオルガスムについても、どんな斬新なことがいわれているか計りしれない。ゆとりがあればまたたち返るとして、わたしがいちばん感銘をうけた問題にすぐに入ってゆくとする。
人間の感覚の器官を介して入ってくる情報は、以前から視床を中継として経たうえで、大脳の皮質のあるはっきりと区別できる領野に投射されることが知られている。視覚にたいしては後頭部のあたりの皮質の領野に、触覚は頭のてっぺんの部分に位置している。つまりそれぞれの皮質の表面に感覚器官が感受する物理的なデータが表現されていることになる。もっとこまかくいうと皮質にはそれぞれの感覚器官が受け入れた物の縮尺の地図が描かれる。例えば触覚を例にとる。サルの親指を局所で刺戟し、これをその感覚に固有な領野(頭頂葉の一、二、二野)のレベルで起る電気的な反応を記録してみる。電極をゆきあたりばったりにおいても、反応は観察できない。そこで皮質の領野のひとつの地点から他の地点へ、電極を決った仕方で移動させる。すると電位がきゅうにあがり、数ミリメートル這わせるとこの変化は消える。これで親指の反応は終って、つぎに人差指の反応に移る。そしてだんだん手が描かれてゆく。これをつぎつぎやってゆくと、ひとつの手が反応で描かれることになる。このやり方をなおつづけると、身体の半側全体があらわれてくる。こうやって大脳皮質の表面にトレースされてゆく小像は、サルに似はじめてくる。脳から頭のてっぺんまでのあいだ、舌、頭、前肢と手、後肢と足、尾ができてくる。これらは三次元のものが二次元に投影しているから歪みが起っている。この皮質に描かれた小像は、じっさいのサルの像とはちがうようにみえても、その人間がどんな感覚器官にふだん重要度を与えているかによって強調されたり、ひかえめに描かれたりしていて、外界との接触点の像を作っている。
わたしたちは大脳のはたらきを感覚器官とむすびつける経路が神経とインパルスによって成り立っていることは知っていた。しかしそれが皮質の表面にそのものの感受の仕方にしたがった縮図像を描くことまでは、まったく想像もしていなかった。べつな言葉でいえば、わたしたちが心身の相関する領域に与えていた錯綜したイメージにくらべて、はるかに単純で像的にはっきりした受容の仕方が成り立っているのだという印象をうけ、少なからず感銘をうけたといっていい。
さらにもう少しつっこんで感覚から神経のはたらきの領域に入ってゆくと、もっと驚きを感じさせられる。大脳皮質の機能の細分化のありさまをつきつめてゆくと、結局は個々の神経細胞そのものにゆきつくと、著者はいっている。ある細胞はただ一方の眼に反応し、べつの細胞は両方の眼に反応する。さらにべつの細胞は特別の方向をもった光線や特定の向きにうごく点に反応するということが起っている。わたしたちが「チェア」というとき、ルイ十三世風の椅子もあればルイ十六世風の椅子もあり、その他の様式のものもある。このさまざまな椅子のつくられた感覚像から、いま「チェア」の概念をつくろうとすれば、「細部の除外、図式化、さらには抽象化」が行われる。この概念-原型が大脳の皮質の細胞に記憶として留められて、「チェア」の知覚やイメージのような感覚像とつながりながら、しかもちがった純粋のこころの動きとしての概念が形成されてゆく。この本の著者の考え方は、知覚やイメージと概念とをおなじカテゴリーに包括させていることだ。それによって概念に対応する言語は、知覚やイメージと関連づけられることになる。これはわたしなどが近年とっているハイ・イメージ論の考え方と似ていて親近感をおぼえる。
ところで概念という純粋なこころのはたらきまできたとき、大脳がニューロン機械だという生物学との関連を捨てなければならないのだろうか。著者はネズミに光とそのあとの痛みを連動させた実験を例に、ネズミが反射以前に身動きしなくなるのは、概念の原型を記憶して恐怖するからで、けっして条件反射の行動ではないと注意している。いいかえれば、皮質の局部的な複数の領野を貫いて流れる鎖のようなつながりが、あらかじめ概念のわくをつくっているので、このばあいでも生物学的な接近が可能なことを示唆している。この本によってこころのはたらきから、不可知の膜が一枚はがされた気がする。
【この書評が収録されている書籍】