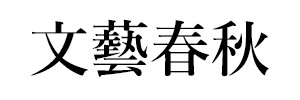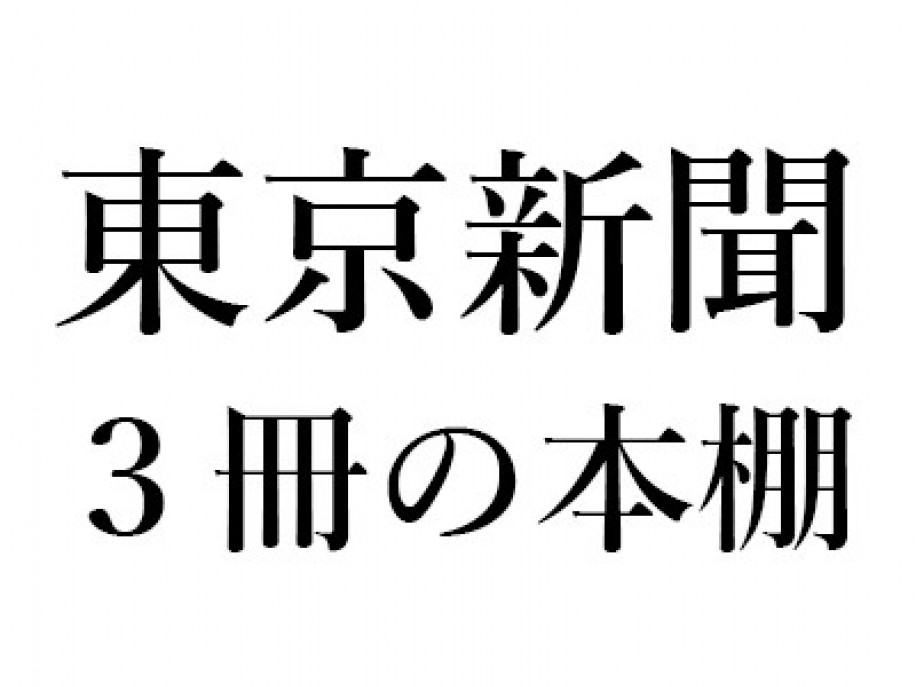対談・鼎談
『倫敦巴里』和田誠|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
【新版】 丸谷 これはパロディの本です。パロディとしては、絵のパロディもあります。たとえば「漫画オールスターパレード」なんていうのがあって、さっきの話の続きでいうと「天才バカボンのおやじ」を田中角栄で描いたというのなんかがそうですね。「CM三角大福」という、テレビのコマーシャルで例の四人の大物と佐藤栄作をからかったものなんか、じつによく出来ている(33頁)。それからもちろん文章のパロディがある。その実例として、山口瞳が『雪国』を書けばどうなるか。
それから庄司薫。
どっちも、いかにも山口瞳らしいし、いかにも庄司薫らしいし、うまいと思うな。腹かかえて笑うしかないくらいおもしろい。
つまり、これは言葉遊びによる批評なんですね。もちろん山口瞳さんは批評されてる、庄司薫さんは批評されてる。しかし、ノーベル賞作家も批評されているんだなあ。さらにノーベル賞作家の読者たちも批評されてる。庄司薫の読者も批評されてるし、山口瞳の読者も批評されてるし、むやみやたらに批評のほこ先が多岐にわたっちゃって、意味賦与(ふよ)が非常にたくさんできる。これはパロディという特異な批評形式のありがたみですね。
でもパロディというものは、近代日本文学では非常に軽んじられていて、斎藤緑雨のもの以後は、ほとんど問題にされていなかった。斎藤緑雨だけは、何か抜群の才があるということになっていて、あとはまあどうってことはないということにされていた。
これは要するにパロディが軽蔑されていただけじゃなくて、言葉遊びってものが軽視されていたんだと思うんです。なぜ言葉遊びが軽視されていたかというと、第一に近代日本文学というのは真面目なもので、深刻趣味があって、遊戯性が軽んじられていて、ユーモアとか笑いとかいうようなことは、つまらないこととされていた。そういう明治日本で始まった深刻趣味、真面目趣味、要するに一種のヴィクトリアニズム――いや、ヴィクトリアニズムよりも、もっと真面目だったんですね。ヴィクトリアニズムってものは、たとえばルイス・キャロル(英国の童話作家)とか、ああいう人をつくったわけですからね。
第二に、言葉遊びというものは、言葉を大事にするということなんだけど、言葉ってものは伝統的なものであって、その伝統的なものをもじるから遊びが成立する。ところが、伝統というものが、近代日本では非常に価値の低いものとされていた。
山崎 人の大事にしてるものをおもちゃにすれば、これは刺激がありますが、だれも大事にしてないものをおもちゃにしたって、だれもびっくりしない。いいかえれば、世の中が言葉を大事にしてないから、言葉で遊んで見せても何の冒涜にもならないし、冒涜のもつ反逆性も出てこないということでしょう。
丸谷 だから近代日本で多少とも意味があったのは、小学生がやった教育勅語のパロディ。そういう言葉遊びへの軽蔑、反撥、蔑視、いろんなものがあって、言葉遊びってものはずっと軽んじられてきた。ひるがえって考えてみると、文学ってのは、要するに言葉遊びなわけですよね。和歌だって、発句だって、要するに言葉の遊びで、王朝和歌でいちばん大事な掛詞とか、縁語とかは言葉遊びの最たるものですが、そういうものがえらく軽んじられることになった。そうしてできあがったものが、レトリックを非常に無視した近代日本文学だったわけですね。
ところが、最近、近代日本文学の言葉遊びをきらう風潮に対する反動が、ずいずん露骨になってきたと思う。そのいちばん典型的なものは、池田満寿夫さんの『エーゲ海に捧ぐ』ですね。日本から電話かけてきた奥さんが、主人公である画家に向かって、あなたはどういう男であるかって悪口言うところがある。
まるでぼくのことをいっているんじゃないかという気がするんだけど……(笑)。『エーゲ海に捧ぐ』って小説でいちばんいいところは、ここだと思うんだよ(笑)。
山崎 かなり無責任な発言だな(笑)。
(次ページに続く)
トンネルを抜けると雪国だった。
この書き方は正確ではない。トンネルを抜けなくたって、雪国なのである。しかし、トンネルを抜けたら雪国だったというのは、私におけるひとつの観点である。当っているかもしれないし、当っていないかもしれない。
全く久しぶりで汽車に乗った。(中略)
汽車が止まると、私の前の席の若い女が立上がっていきなり窓を開けた。雪の冷気が流れ込んで寒い。寒がりの私にはどうにも迷惑であるが、それに気がつく様子はない。こういう人がふえてきたように思われる
それから庄司薫。
国境のトンネルはなにしろ長くて、ぼくはちょうど持っていたソニーのトランジスタラジオから流れてくる「真実一路のマーチ」なんかをボヤッと聞いているうちに、汽車がその相当長いトンネルを抜けでると(どうも唐突だけれど)、そこは雪国だった。(中略)
汽車が信号所に止まると、ぼくの前の席の女の子が(どうしようもないおかしな魅力のある人なんだ)、窓を開けて叫んだ。「駅長さあん、駅長さあん」(後略)
どっちも、いかにも山口瞳らしいし、いかにも庄司薫らしいし、うまいと思うな。腹かかえて笑うしかないくらいおもしろい。
つまり、これは言葉遊びによる批評なんですね。もちろん山口瞳さんは批評されてる、庄司薫さんは批評されてる。しかし、ノーベル賞作家も批評されているんだなあ。さらにノーベル賞作家の読者たちも批評されてる。庄司薫の読者も批評されてるし、山口瞳の読者も批評されてるし、むやみやたらに批評のほこ先が多岐にわたっちゃって、意味賦与(ふよ)が非常にたくさんできる。これはパロディという特異な批評形式のありがたみですね。
でもパロディというものは、近代日本文学では非常に軽んじられていて、斎藤緑雨のもの以後は、ほとんど問題にされていなかった。斎藤緑雨だけは、何か抜群の才があるということになっていて、あとはまあどうってことはないということにされていた。
これは要するにパロディが軽蔑されていただけじゃなくて、言葉遊びってものが軽視されていたんだと思うんです。なぜ言葉遊びが軽視されていたかというと、第一に近代日本文学というのは真面目なもので、深刻趣味があって、遊戯性が軽んじられていて、ユーモアとか笑いとかいうようなことは、つまらないこととされていた。そういう明治日本で始まった深刻趣味、真面目趣味、要するに一種のヴィクトリアニズム――いや、ヴィクトリアニズムよりも、もっと真面目だったんですね。ヴィクトリアニズムってものは、たとえばルイス・キャロル(英国の童話作家)とか、ああいう人をつくったわけですからね。
第二に、言葉遊びというものは、言葉を大事にするということなんだけど、言葉ってものは伝統的なものであって、その伝統的なものをもじるから遊びが成立する。ところが、伝統というものが、近代日本では非常に価値の低いものとされていた。
山崎 人の大事にしてるものをおもちゃにすれば、これは刺激がありますが、だれも大事にしてないものをおもちゃにしたって、だれもびっくりしない。いいかえれば、世の中が言葉を大事にしてないから、言葉で遊んで見せても何の冒涜にもならないし、冒涜のもつ反逆性も出てこないということでしょう。
丸谷 だから近代日本で多少とも意味があったのは、小学生がやった教育勅語のパロディ。そういう言葉遊びへの軽蔑、反撥、蔑視、いろんなものがあって、言葉遊びってものはずっと軽んじられてきた。ひるがえって考えてみると、文学ってのは、要するに言葉遊びなわけですよね。和歌だって、発句だって、要するに言葉の遊びで、王朝和歌でいちばん大事な掛詞とか、縁語とかは言葉遊びの最たるものですが、そういうものがえらく軽んじられることになった。そうしてできあがったものが、レトリックを非常に無視した近代日本文学だったわけですね。
ところが、最近、近代日本文学の言葉遊びをきらう風潮に対する反動が、ずいずん露骨になってきたと思う。そのいちばん典型的なものは、池田満寿夫さんの『エーゲ海に捧ぐ』ですね。日本から電話かけてきた奥さんが、主人公である画家に向かって、あなたはどういう男であるかって悪口言うところがある。
無知で無能で無感覚で、無関心で、無作で無為で無援で無学で無軌道で、無芸で無策で無残で、無自覚で無趣味で、無造作で無恥で無ちゃくちゃで無定見で無益で無責任で、そのくせに自分では無類のお人好しだと思い込み、無欲だと思い込み、無償の芸術にいそしみ、無邪気で無心で、無視されることをおそれているくせに、無我の境地にいると信じ、無やみにオンナを欲しがり、無罪を主張し、無精卵のオンナが好きで、無断でオンナと寝、自分には無批判で、無力だからって哀願し、無欲だからって人の同情をあてにし、無限に生きていくつもりで……
まるでぼくのことをいっているんじゃないかという気がするんだけど……(笑)。『エーゲ海に捧ぐ』って小説でいちばんいいところは、ここだと思うんだよ(笑)。
山崎 かなり無責任な発言だな(笑)。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする