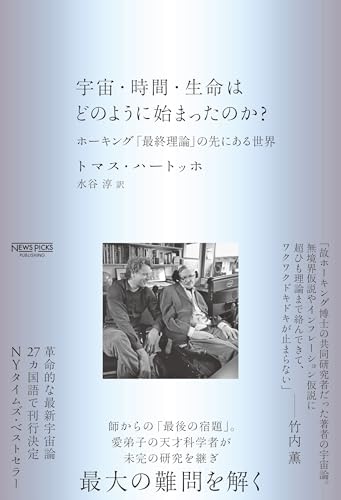書評
『ほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法』(講談社)
今日も各地で行われているであろう結論ありきの上意下達的会議は、不毛なばかりでなく悪を生む。
近年多発する企業の不正の裏には、このような会議があると著者は言う。米国のギャンブル症者が偶然始めた話し合いは、言いっ放し、聞きっ放しで討論なし、批判なし、結論なし。仮名で何でも話し合うミーティングの継続がギャンブル症者特有の「今だけ」、「自分だけ」、「金だけ」を消滅させると知って驚いた。
今やこの自助グループの目標は、思いやり、寛容、正直、謙虚だという。見事だ。これは、フィンランドで精神障害者に関わる問題解決法として始まったオープン・ダイアローグと重なる。
核心は多声性。評価抜きで多様な意見を述べ合っているうちに、思いがけない世界が見えてくるのだ。ここで培われるのはネガティブ・ケイパビリティ(答えの出ない事態に耐える力)であり、これが人間を成長させるのだ。
著者の留学体験を踏まえての、ラカン、カミュなどフランスの知性を輩出したパリのアパルトマンでの「終わりなき対話」の紹介も興味深い。「答えは質問の不幸である」という言葉を嚙みしめ、明日からほんとうの会議をしよう。
近年多発する企業の不正の裏には、このような会議があると著者は言う。米国のギャンブル症者が偶然始めた話し合いは、言いっ放し、聞きっ放しで討論なし、批判なし、結論なし。仮名で何でも話し合うミーティングの継続がギャンブル症者特有の「今だけ」、「自分だけ」、「金だけ」を消滅させると知って驚いた。
今やこの自助グループの目標は、思いやり、寛容、正直、謙虚だという。見事だ。これは、フィンランドで精神障害者に関わる問題解決法として始まったオープン・ダイアローグと重なる。
核心は多声性。評価抜きで多様な意見を述べ合っているうちに、思いがけない世界が見えてくるのだ。ここで培われるのはネガティブ・ケイパビリティ(答えの出ない事態に耐える力)であり、これが人間を成長させるのだ。
著者の留学体験を踏まえての、ラカン、カミュなどフランスの知性を輩出したパリのアパルトマンでの「終わりなき対話」の紹介も興味深い。「答えは質問の不幸である」という言葉を嚙みしめ、明日からほんとうの会議をしよう。
ALL REVIEWSをフォローする