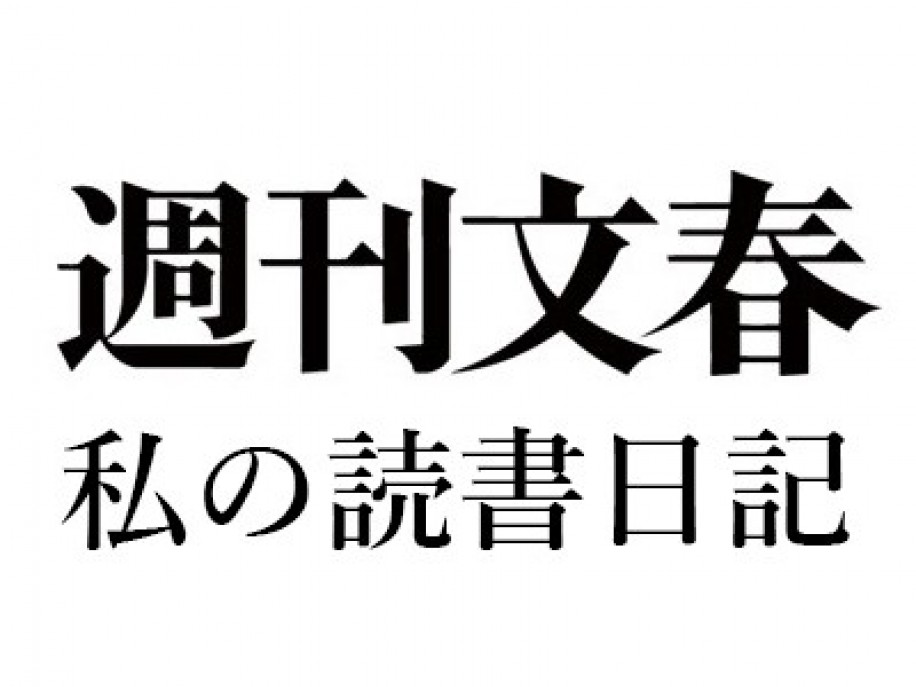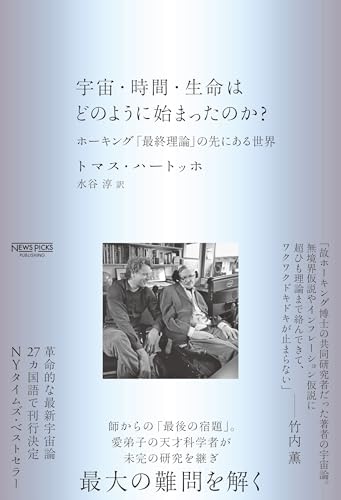書評
『日本列島四万年のディープヒストリー 先史考古学からみた現代』(朝日新聞出版)
現代文明社会の問題点である自然の中での人間のありようを考え直す手段として、日本列島に暮らし始めた4万年前からの歴史を辿る。
世界史では新石器時代のものとされる磨製石器が旧石器時代の3・7万年前、土器も1・5万年ほど前に見られ、日本列島での文化の始まりは早い。これを著者は森林環境が生み出したとし、大陸文化の影響だけを重視せず、自然との関わりに注目した。列島内でも各地に特徴があり、北では大型獣の捕獲をめざす精巧な細石刃、南では貝など簡素なものが生まれた。これを優劣でなく環境との関わりと見ることが重要である。
1・1万年前から気候が安定な完新世になり、定住、農耕へ移行した時の生活・文化を特徴づけたのが四季の存在である。海・川・山野の資源が四季を意識させ、一年の暮らし方を予測しながら日常を組み立てることになったのだ。このような生活の基本は現代にまで続く。共同体での個人と集団の関係、平等と格差などの課題にも眼を向けながら、自然の一部としての生き方を探る試みである。
世界史では新石器時代のものとされる磨製石器が旧石器時代の3・7万年前、土器も1・5万年ほど前に見られ、日本列島での文化の始まりは早い。これを著者は森林環境が生み出したとし、大陸文化の影響だけを重視せず、自然との関わりに注目した。列島内でも各地に特徴があり、北では大型獣の捕獲をめざす精巧な細石刃、南では貝など簡素なものが生まれた。これを優劣でなく環境との関わりと見ることが重要である。
1・1万年前から気候が安定な完新世になり、定住、農耕へ移行した時の生活・文化を特徴づけたのが四季の存在である。海・川・山野の資源が四季を意識させ、一年の暮らし方を予測しながら日常を組み立てることになったのだ。このような生活の基本は現代にまで続く。共同体での個人と集団の関係、平等と格差などの課題にも眼を向けながら、自然の一部としての生き方を探る試みである。
ALL REVIEWSをフォローする