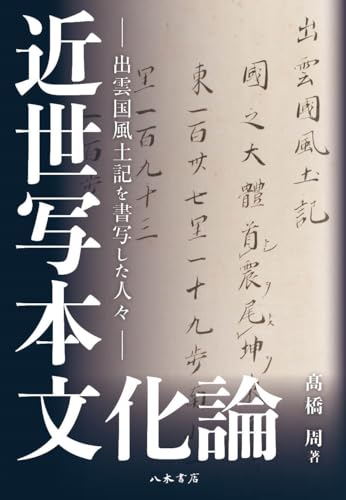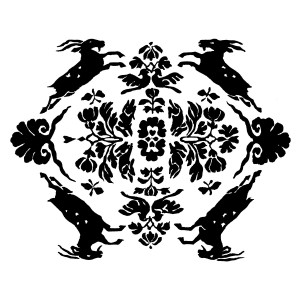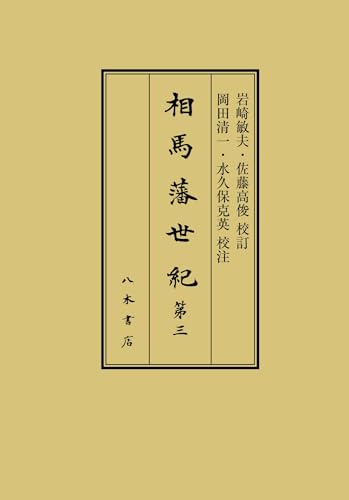自著解説
『近世写本文化論: 出雲国風土記を書写した人々』(八木書店)
200を超える出雲国風土記の写本調査は、全文比較によって写本間の系譜と歴史的背景を明らかにする営みである。人との縁が調査を支え、写本が語る物語が浮かび上がる。
出雲国風土記は出雲国(現在の島根県東部)の地理、産物、地名の由来などを記した地誌で、総じて200冊を超える写本が現存する。原本は天平5年(733)にまとめられたものであり、写本全文の内容は基本的に同じである。そのため、写本間の相違を確認するためには、部分的な比較では不正確な関係を導く可能性があり、全文として見る必要がある。写本番号(1)細川家本の場合、全文で1002行、一行あたり18字前後であるから、一冊18000字程度を目に通す膨大な作業である。実のところ、本書『近世写本文化論-出雲国風土記を書写した人々』の核心は本文ではなく、ウェブサイト掲載の「校異表」であり、本文の執筆よりも全文の対校に多くの時間を要している。その結果として写本間の系譜を見出すことができ、写本によっては歴史的背景のつながりも見えてくるのである。
写本間の関係ついては、奥書に親本や書写の経緯が記されることがあるが、写本間の校異を通しても共通の異同などから奥書の信憑性を確認できる。例えば、(105)古田氏本と(106)狩谷氏本は奥書などから、屋代弘賢(1758-1841)書写・旧蔵で賀茂真淵(1697-1769)旧蔵本を親本にしたと分かるが、写本の異同にも共通する点が多いのである。
さらに、異同を共通させる写本をまとめていくと、弘賢と親交を持った会津藩・一柳直陽(1753-1834)旧蔵の(107)慶応義塾図書館本や、真淵に近い遠江・斎藤信幸との関係が窺える(109)三階屋本が系譜的に近いことが分かる。このことは異同の検討を通した写本の系譜関係と歴史的背景がつながる好例と言えるだろう。
そして、古田氏本と狩谷氏本に先行する写本として、近衛家の(110)陽明文庫本と神宮祭主・藤波家の(111)藤波家本を位置付けることができる。この系譜関係は古田氏本と狩谷氏本の親本・賀茂真淵旧蔵本が京都の堂上公家の写本に由来することを示すものであり、真淵が在京中に出雲国風土記を書写あるいは落手したことが窺えるのである。こうした写本の関係性と真淵の動向を考究していくと、新知見につながる可能性もあるだろう。
このように、本書『近世写本文化論-出雲国風土記を書写した人々』では、写本そのものの系譜関係とともに、写本の背後にある歴史の一端を解き明かしていく。

本書の「おわりに」でも触れているが、出雲国風土記の写本調査の契機となったのが、郷原家本である。その所蔵者の郷原さんの質問に答えるために始めたのであるが、初め写本の対校に際しては島根県古代文化センターで所蔵される影印を参考とした。しかし、対校を重ねるうちにさらに多くの写本を確認する必要性を感じ、当時は現在のようにインターネット公開される写本は多くない中で、写本の所蔵先へ出かけて撮影したり、図書館で複写依頼をしたりして、調査を進めることとなった。
所蔵先の多くは図書館や博物館などの公共機関であったが、個人宅あるいは会社へ伺う場合もあった。いずれの所蔵先でも職員、所蔵者の方には親切に対応して頂いて、本書はそうした方々の協力なしでは成立し得なかったと言える。
図書館を通した複写依頼も然りである。写本の状態や当該館の方針によって複写料は異なり、高額になることもあるが、現住地から離れた場所にある写本を確認するには有効な方法である。もちろん、写本調査の基礎は実見であり、これを通して得られる知見もあるが、悉皆調査において全てを実見するのは現実的な方法ではない。また、図書館については、写本調査をするのに紹介状が必要な場合があるが、最寄りの公共図書館で対応して頂けることが多く、私のような大学などの研究機関に所属しない者でも調査を続けることができたのである。出雲国風土記に限らず、写本や古文書の調査を行う場合には、図書館を積極的に活用すべきであろう。
なお、写本の所在については国文学研究資料館ホームページ「国書データベース」でかなり網羅されているが、それが全てではない。個人蔵の写本には未確認のものが多く、各種「蔵書目録」「古書目録」のほか、研究者からも所在情報を得ることもあった。インターネットのオークションサイトを含めて、常に情報を広く捉えられるよう心がけている。
このように、これまでの写本調査を振り返ると、多くの人との縁が基礎にあったと考える。インターネットで広く公開される時代となっても、写本を伝えるのは人であり、それを調べ研究するのも人なのである。
[書き手]
髙橋 周(たかはし しゅう)
1975年 東京都あきる野市に生まれる
1998年 奈良大学文学部史学科卒業
2003年 学習院大学人文科学研究科史学専攻 博士後期課程単位取得退学
現在 出雲市文化財課・出雲弥生の森博物館専門研究員
学習院大学博士(史学)
[主な著作]
『近世写本文化論—出雲国風土記を書写した人々—』(八木書店、2025年)
「小栗広伴旧蔵『出雲国風土記』について―その奥書と写本系統をめぐって―」(『古文書研究』日本古文書学会、2018年)
「『出雲国風土記』の写本と写本系統」(島根県古代文化センター編『出雲国風土記―校訂・註釈編―』八木書店、2023年)
写本調査から見えること:全文比較が導く写本間の系譜と歴史的背景
出雲国風土記は出雲国(現在の島根県東部)の地理、産物、地名の由来などを記した地誌で、総じて200冊を超える写本が現存する。原本は天平5年(733)にまとめられたものであり、写本全文の内容は基本的に同じである。そのため、写本間の相違を確認するためには、部分的な比較では不正確な関係を導く可能性があり、全文として見る必要がある。写本番号(1)細川家本の場合、全文で1002行、一行あたり18字前後であるから、一冊18000字程度を目に通す膨大な作業である。実のところ、本書『近世写本文化論-出雲国風土記を書写した人々』の核心は本文ではなく、ウェブサイト掲載の「校異表」であり、本文の執筆よりも全文の対校に多くの時間を要している。その結果として写本間の系譜を見出すことができ、写本によっては歴史的背景のつながりも見えてくるのである。写本間の関係ついては、奥書に親本や書写の経緯が記されることがあるが、写本間の校異を通しても共通の異同などから奥書の信憑性を確認できる。例えば、(105)古田氏本と(106)狩谷氏本は奥書などから、屋代弘賢(1758-1841)書写・旧蔵で賀茂真淵(1697-1769)旧蔵本を親本にしたと分かるが、写本の異同にも共通する点が多いのである。
さらに、異同を共通させる写本をまとめていくと、弘賢と親交を持った会津藩・一柳直陽(1753-1834)旧蔵の(107)慶応義塾図書館本や、真淵に近い遠江・斎藤信幸との関係が窺える(109)三階屋本が系譜的に近いことが分かる。このことは異同の検討を通した写本の系譜関係と歴史的背景がつながる好例と言えるだろう。
そして、古田氏本と狩谷氏本に先行する写本として、近衛家の(110)陽明文庫本と神宮祭主・藤波家の(111)藤波家本を位置付けることができる。この系譜関係は古田氏本と狩谷氏本の親本・賀茂真淵旧蔵本が京都の堂上公家の写本に由来することを示すものであり、真淵が在京中に出雲国風土記を書写あるいは落手したことが窺えるのである。こうした写本の関係性と真淵の動向を考究していくと、新知見につながる可能性もあるだろう。
このように、本書『近世写本文化論-出雲国風土記を書写した人々』では、写本そのものの系譜関係とともに、写本の背後にある歴史の一端を解き明かしていく。

写本調査は人の縁
本書の「おわりに」でも触れているが、出雲国風土記の写本調査の契機となったのが、郷原家本である。その所蔵者の郷原さんの質問に答えるために始めたのであるが、初め写本の対校に際しては島根県古代文化センターで所蔵される影印を参考とした。しかし、対校を重ねるうちにさらに多くの写本を確認する必要性を感じ、当時は現在のようにインターネット公開される写本は多くない中で、写本の所蔵先へ出かけて撮影したり、図書館で複写依頼をしたりして、調査を進めることとなった。所蔵先の多くは図書館や博物館などの公共機関であったが、個人宅あるいは会社へ伺う場合もあった。いずれの所蔵先でも職員、所蔵者の方には親切に対応して頂いて、本書はそうした方々の協力なしでは成立し得なかったと言える。
図書館を通した複写依頼も然りである。写本の状態や当該館の方針によって複写料は異なり、高額になることもあるが、現住地から離れた場所にある写本を確認するには有効な方法である。もちろん、写本調査の基礎は実見であり、これを通して得られる知見もあるが、悉皆調査において全てを実見するのは現実的な方法ではない。また、図書館については、写本調査をするのに紹介状が必要な場合があるが、最寄りの公共図書館で対応して頂けることが多く、私のような大学などの研究機関に所属しない者でも調査を続けることができたのである。出雲国風土記に限らず、写本や古文書の調査を行う場合には、図書館を積極的に活用すべきであろう。
なお、写本の所在については国文学研究資料館ホームページ「国書データベース」でかなり網羅されているが、それが全てではない。個人蔵の写本には未確認のものが多く、各種「蔵書目録」「古書目録」のほか、研究者からも所在情報を得ることもあった。インターネットのオークションサイトを含めて、常に情報を広く捉えられるよう心がけている。
このように、これまでの写本調査を振り返ると、多くの人との縁が基礎にあったと考える。インターネットで広く公開される時代となっても、写本を伝えるのは人であり、それを調べ研究するのも人なのである。
[書き手]
髙橋 周(たかはし しゅう)
1975年 東京都あきる野市に生まれる
1998年 奈良大学文学部史学科卒業
2003年 学習院大学人文科学研究科史学専攻 博士後期課程単位取得退学
現在 出雲市文化財課・出雲弥生の森博物館専門研究員
学習院大学博士(史学)
[主な著作]
『近世写本文化論—出雲国風土記を書写した人々—』(八木書店、2025年)
「小栗広伴旧蔵『出雲国風土記』について―その奥書と写本系統をめぐって―」(『古文書研究』日本古文書学会、2018年)
「『出雲国風土記』の写本と写本系統」(島根県古代文化センター編『出雲国風土記―校訂・註釈編―』八木書店、2023年)
ALL REVIEWSをフォローする