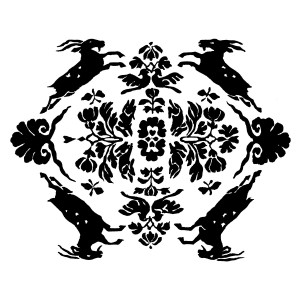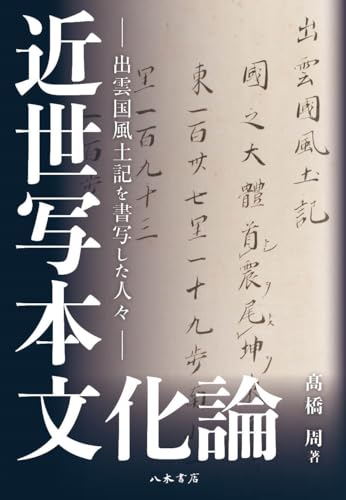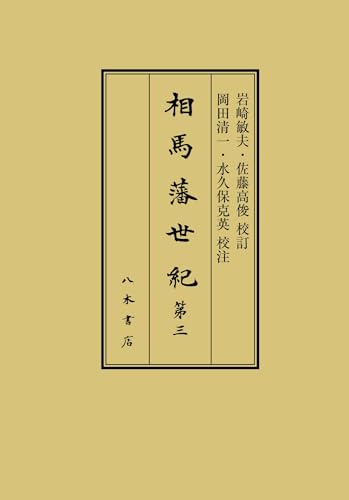自著解説
『鍋島直郷参府記』(八木書店)
江戸時代中期、激動の政治と文化の中心で、肥前鹿島藩第6代藩主・鍋島直郷が参勤交代の期間に綴った随筆『席珍』。8代将軍吉宗から9代家重への交代、桜町天皇を中心とする禁裡における文事の様子、荷田在満・田安宗武・賀茂真淵による歌学大論争など、政治と文学の転換点を目撃した直郷の視点から、当時の生の情報が克明に記録されています。
政治は、吉宗から9代家重への家督相続が行われる時節であった。『席珍』には、延享元年に「本卦帰り」を迎えた吉宗の歌「呉竹のふしの間こそにかさねおき六十の坂を安くこへけり」が記載されたあとに、延享二年秋に朝廷に差し出された吉宗の退位伺いの文章「表」の案文が記録されている。
「表」の題名は「延享乙丑秋何月何日臣等表之」で、後半には本多忠良・御三家以下、「老中四人/諸侯十八人/国主五人/帝鑑間/柳之間/雁之間/菊之間/別当若年寄」各々の署名欄が指示されており、臨場感が伝わってくる。
次に10月19日の日付で「隠退祝の佩刀配り」のリスト、また11月2日付で、「将軍宣下御祝義」として、吉宗・家重より、「禁裡」「一条関白」「両伝奏」「一条殿・二条殿」その他へ、また「伊勢内・外宮」「日光御宮」「山王」「氷川社」へ贈る祝品のリストが写されている。この間に、老中松平乗邑を罷免する申渡書が、延享二年十月九日付で載せられており、その理由三点、「権高ク」、「慎(つつしみ)」なく、「我意を立(たつ)る」が、直截に書かれていることが注目される。
一方の文事であるが、直郷は禁裡に対しても注意深い視線を注いでいた。桜町天皇は、七社奉幣の復興を三条西大納言公福に命じ、延享元年5月19日に「七社奉幣日時定」を行い、同年9月には宇佐への奉幣使発遣を定める。同10月17日作製の「御奉幣納物」のリストには、「一、宣命 黄紙 一、御幣〈金銀三串〉 唐(辛ト書テアリ)櫃一合ニ入 一、御幣物一包 唐櫃一合ニ入」、続いて「御剣」「御鏡」「御衣」「御撫物」についての記録があって、最後に「一、御製〈五十首御短尺〉 唐櫃六合ニ入」とある。最後の「御製五十首」が注意されるが、『席珍』には、ほかに御製十首が集められている。
なお御会については、延享三年正月二十四日公宴御会始抜書九首、同年正月晦日当座御会三十首、延享四年三月二十一日清涼殿花宴御会十五首、が記録されている。また、桜町天皇が烏丸光栄より古今伝授を受けられた日時と内容が、「延享元年二月二十三日 三部抄御伝授 詠歌大概・百人一首・未来記・雨中吟 同三月二十二日 伊勢物語御伝授 同五月七日 古今集御伝授」と記され、別条に「細川幽斎以来古今伝来次第」として、「幽斎―実條/光広―後水尾院―霊元院―通茂―実蔭/通躬―光栄(ナガ)/公福―当今」の系図を書き、「当時古今伝の人ハ当今・光栄・公福の三人也」と注記し、また、貞徳門弟次第を「長孝―長雅―長伯―長泉」の系図で示し「地下歌故不信仰也」と記している。
なお現在の伝授者の一人烏丸光栄と、当代の随一の歌人冷泉為村の二人が、延享3年4月に揃って家重の将軍就任祝いの使者として下向するが、江戸の堂上派の人々は、ここぞとばかり歌会を催しており、それらの歌稿も丹念に写されている。
ところで、寛保2年(1742)8月に荷田在満の『国歌八論』が田安宗武に献進された。宗武は反論書を書き、宗武に意見を徴された賀茂真淵も反論書を書き奉答する。この論争の最後は延享3年(1746)3月だったといわれている。この論争において、三者はともに堂上旧歌学を否定し、歌学の基礎を万葉集に置くことで一致するが、和歌については異なり、在満は古義学による翫歌説、宗武は朱子学により治道・教誡説、真淵は古文辞学により和歌を道の一つと認める。
この論争と『席珍』の執筆期間は重なっており、直郷は固唾を呑んで論争の行方を見つめていたに違いない。『席珍』の中に、この論争を匂わせる記事がある。その一は、延享2年(または3年)の在満の詠歌3首と真淵の6首とが並べて書かれている資料である。内容が田安家の和学御用係を辞退する者と新任者の登場を思わせるものがあるからである。
その二は、真淵を紹介した文章である。『日本書紀』を用い万葉集を読み解く和学者で、契沖を尊び、「貫之・定家をはじめてみな批判」し、「義理を論ずる」者だと評している。
その三は、徳川光圀が契沖を深く信頼した理由を説明した逸話である。光圀は、安藤為章より、紫式部は淫犯の女ではなく、歌に秀で、広く学問を身につけた人間味豊かな女性であることを教えられ、また、この人物評が契沖から出ていることを知り、契沖を「歎慕」したというものであった。
この近世和歌史上の大論争のただ中にあった4年間、直郷は苦闘を続け、その果てに堂上旧歌学(=古今伝授)の否定を受入れ、歌学は古代を学ぶことに決し、詠歌については古文辞学の新文学論(人情論)を許容することにしたと考えられる。ただし、真淵の万葉調を取り入れることはなかった。晩年は垂加神道の正伝相承者として、古代史の学びに専念し、自己の存在を大名ではなく、天皇の臣下(まくら)であると臆することなく公言した。
『席珍』は、こうした直郷の視線を通して記録された随筆だったのである。
[書き手]
井上 敏幸(いのうえ としゆき)
佐賀大学名誉教授。佐賀大学地域学歴史文化研究センター特命教授。日本近世文学。
[主な著作]
『史料纂集古記録編 第224回配本 鍋島直郷参府記』(共著、八木書店、2025年)
『肥前鹿島円福山普明禅寺誌』(共編著、佐賀大学地域学歴史文化研究センター、2016年)
『鹿島鍋島藩の政治と文化』(研究代表者、国文学研究資料館、2008年)
『鍋島直郷 西園和歌集 翻刻と解説』(共編著、風間書房、2004年)
文人大名・鍋島直郷の視座
本書『鍋島直郷参府記』の原題は『席珍』である。著者は、肥前鹿島藩第6代藩主鍋島直郷(1718~1770)。『席珍』は、『礼記』儒行篇の「席上之珍」(聖人の善道の教えを並べた)の意であるが、直郷は杜甫の「上韋左相二十韻(韋左相に上(たてまつ)る二十韻)」中の語句「席上ノ珍」(席上の美玉)を踏まえて、「眼前に展開される政治と文事の情報」を提供するという意味で用いたと思われる。執筆期間は、延享元年(1744)5月から寛延元年(1748)6月までの4年間である。この期間は8代将軍吉宗による改革政治の末期に当り、政治・文化ともに大きな変革の時期にさしかかっていた。
『席珍』に記録された将軍家の動き
政治は、吉宗から9代家重への家督相続が行われる時節であった。『席珍』には、延享元年に「本卦帰り」を迎えた吉宗の歌「呉竹のふしの間こそにかさねおき六十の坂を安くこへけり」が記載されたあとに、延享二年秋に朝廷に差し出された吉宗の退位伺いの文章「表」の案文が記録されている。「表」の題名は「延享乙丑秋何月何日臣等表之」で、後半には本多忠良・御三家以下、「老中四人/諸侯十八人/国主五人/帝鑑間/柳之間/雁之間/菊之間/別当若年寄」各々の署名欄が指示されており、臨場感が伝わってくる。
次に10月19日の日付で「隠退祝の佩刀配り」のリスト、また11月2日付で、「将軍宣下御祝義」として、吉宗・家重より、「禁裡」「一条関白」「両伝奏」「一条殿・二条殿」その他へ、また「伊勢内・外宮」「日光御宮」「山王」「氷川社」へ贈る祝品のリストが写されている。この間に、老中松平乗邑を罷免する申渡書が、延享二年十月九日付で載せられており、その理由三点、「権高ク」、「慎(つつしみ)」なく、「我意を立(たつ)る」が、直截に書かれていることが注目される。
禁裡と歌壇の動向
一方の文事であるが、直郷は禁裡に対しても注意深い視線を注いでいた。桜町天皇は、七社奉幣の復興を三条西大納言公福に命じ、延享元年5月19日に「七社奉幣日時定」を行い、同年9月には宇佐への奉幣使発遣を定める。同10月17日作製の「御奉幣納物」のリストには、「一、宣命 黄紙 一、御幣〈金銀三串〉 唐(辛ト書テアリ)櫃一合ニ入 一、御幣物一包 唐櫃一合ニ入」、続いて「御剣」「御鏡」「御衣」「御撫物」についての記録があって、最後に「一、御製〈五十首御短尺〉 唐櫃六合ニ入」とある。最後の「御製五十首」が注意されるが、『席珍』には、ほかに御製十首が集められている。なお御会については、延享三年正月二十四日公宴御会始抜書九首、同年正月晦日当座御会三十首、延享四年三月二十一日清涼殿花宴御会十五首、が記録されている。また、桜町天皇が烏丸光栄より古今伝授を受けられた日時と内容が、「延享元年二月二十三日 三部抄御伝授 詠歌大概・百人一首・未来記・雨中吟 同三月二十二日 伊勢物語御伝授 同五月七日 古今集御伝授」と記され、別条に「細川幽斎以来古今伝来次第」として、「幽斎―実條/光広―後水尾院―霊元院―通茂―実蔭/通躬―光栄(ナガ)/公福―当今」の系図を書き、「当時古今伝の人ハ当今・光栄・公福の三人也」と注記し、また、貞徳門弟次第を「長孝―長雅―長伯―長泉」の系図で示し「地下歌故不信仰也」と記している。
なお現在の伝授者の一人烏丸光栄と、当代の随一の歌人冷泉為村の二人が、延享3年4月に揃って家重の将軍就任祝いの使者として下向するが、江戸の堂上派の人々は、ここぞとばかり歌会を催しており、それらの歌稿も丹念に写されている。
和歌史を揺るがした大論争
ところで、寛保2年(1742)8月に荷田在満の『国歌八論』が田安宗武に献進された。宗武は反論書を書き、宗武に意見を徴された賀茂真淵も反論書を書き奉答する。この論争の最後は延享3年(1746)3月だったといわれている。この論争において、三者はともに堂上旧歌学を否定し、歌学の基礎を万葉集に置くことで一致するが、和歌については異なり、在満は古義学による翫歌説、宗武は朱子学により治道・教誡説、真淵は古文辞学により和歌を道の一つと認める。この論争と『席珍』の執筆期間は重なっており、直郷は固唾を呑んで論争の行方を見つめていたに違いない。『席珍』の中に、この論争を匂わせる記事がある。その一は、延享2年(または3年)の在満の詠歌3首と真淵の6首とが並べて書かれている資料である。内容が田安家の和学御用係を辞退する者と新任者の登場を思わせるものがあるからである。
その二は、真淵を紹介した文章である。『日本書紀』を用い万葉集を読み解く和学者で、契沖を尊び、「貫之・定家をはじめてみな批判」し、「義理を論ずる」者だと評している。
その三は、徳川光圀が契沖を深く信頼した理由を説明した逸話である。光圀は、安藤為章より、紫式部は淫犯の女ではなく、歌に秀で、広く学問を身につけた人間味豊かな女性であることを教えられ、また、この人物評が契沖から出ていることを知り、契沖を「歎慕」したというものであった。
この近世和歌史上の大論争のただ中にあった4年間、直郷は苦闘を続け、その果てに堂上旧歌学(=古今伝授)の否定を受入れ、歌学は古代を学ぶことに決し、詠歌については古文辞学の新文学論(人情論)を許容することにしたと考えられる。ただし、真淵の万葉調を取り入れることはなかった。晩年は垂加神道の正伝相承者として、古代史の学びに専念し、自己の存在を大名ではなく、天皇の臣下(まくら)であると臆することなく公言した。
『席珍』は、こうした直郷の視線を通して記録された随筆だったのである。
[書き手]
井上 敏幸(いのうえ としゆき)
佐賀大学名誉教授。佐賀大学地域学歴史文化研究センター特命教授。日本近世文学。
[主な著作]
『史料纂集古記録編 第224回配本 鍋島直郷参府記』(共著、八木書店、2025年)
『肥前鹿島円福山普明禅寺誌』(共編著、佐賀大学地域学歴史文化研究センター、2016年)
『鹿島鍋島藩の政治と文化』(研究代表者、国文学研究資料館、2008年)
『鍋島直郷 西園和歌集 翻刻と解説』(共編著、風間書房、2004年)
ALL REVIEWSをフォローする