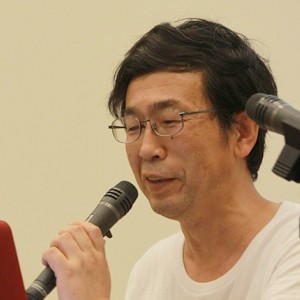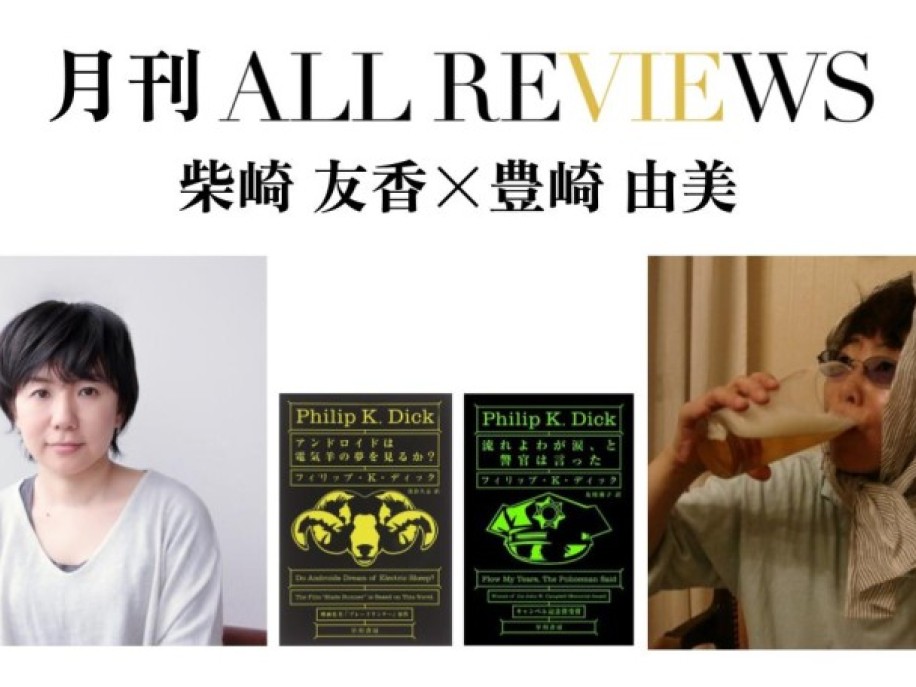書評
『帰れない探偵』(講談社)
「忘れることはなくなること」への対抗
「今から十年くらいあとの話」
柴崎友香の新作『帰れない探偵』は、七つのセクションでできている。そのセクションにはそれぞれ題名が付いていて、独立した短篇を集めた連作短篇集のような形式になっているが、ひと続きの長篇小説としても読める。最初に引用したのは、冒頭に置かれた「帰れない探偵」と題するセクションの書き出しで、その文章を読んだ瞬間に、わたしはもうこの本を読み終わるまで、『帰れない探偵』という小説世界から帰れなくなった。
「今から十年くらいあとの話」
この書き出しには、「今」の現在と、「十年くらいあと」の未来という、二つの時間がある。それにしても、未来の話をどうして現在の時点から語れるのか、あるいは語ろうとするのか。まず読者はその不思議な設定に惹(ひ)かれる。
「帰れない探偵」とは、探偵稼業をしている主人公が、住んでいた事務所が見つからなくなって、帰る場所を失ってしまい、依頼者のところに仮住まいをさせてもらうという話であると同時に、「世界探偵委員会連盟」なる組織から別の国へと派遣されているあいだに、母国の政治体制が変わってしまい、パスポートの使用が制限されて戻れなくなるという話でもある。その母国も、派遣先の国や街も、固有名がいっさい出てこない。主人公の探偵は、名前は伏せられているが、女性であるらしいことが話し方などからぼんやりと想像できる。それと同じように、本書でも言及される、カフカを想(おも)わせるような抽象度の高い小説世界でありながら、母国がどうやら日本であるらしいことも推察できる。つまり、この作品は近未来小説の形を取りながら、そこに薄(う)っすらと(しかしはっきりと)、わたしたちの現在が浮かび上がる仕掛けになっている。
『帰れない探偵』は、殺人事件の真相を究明するといった、ジャンルとしての探偵小説ではない。探偵である主人公が探すのは、過去に生きていた人がどんな景色を見ていたのか、どんなふうに生きたのかという日常的な事柄であり、この小説の時間には現在と未来だけでなく、過去もある。
主人公が帰るべき家や国を見失ってしまうように、時間の経過によって街や国も姿を変えてしまうのは、わたしたち読者にも実感できることだ。本書には、「見えないことは忘れること/忘れることはなくなること」という落書きが出てくるが、その落書きですら消されてしまう。そうした忘却の力に対抗するのは、書くことであり、歌うことだ。「昔覚えた歌はいつまでも忘れないのは不思議だと思いながら、宇宙の暗闇で地球が回っているのを思い浮かべながら、わたしは歌っている」
ほぼすべてのセクションは、最初に引用した文章で始まるが、「歌い続けよう」と題された最後のセクションだけは、書き出しが「これは、今から十年くらいあとの話」と少しだけ違う。長篇小説として読むとき、このセクションは結末であり、新たな始まりでもある。永遠に帰れないのではなく、いったん帰ってきた主人公は、「これから飛び立とうとしている」。もちろん、「帰れない探偵」とは、これまでに書いたことのない領域に踏み込んで、自ら退路を断ち、新たな小説の旅を敢行した、作者の柴崎友香なのだ。
ALL REVIEWSをフォローする