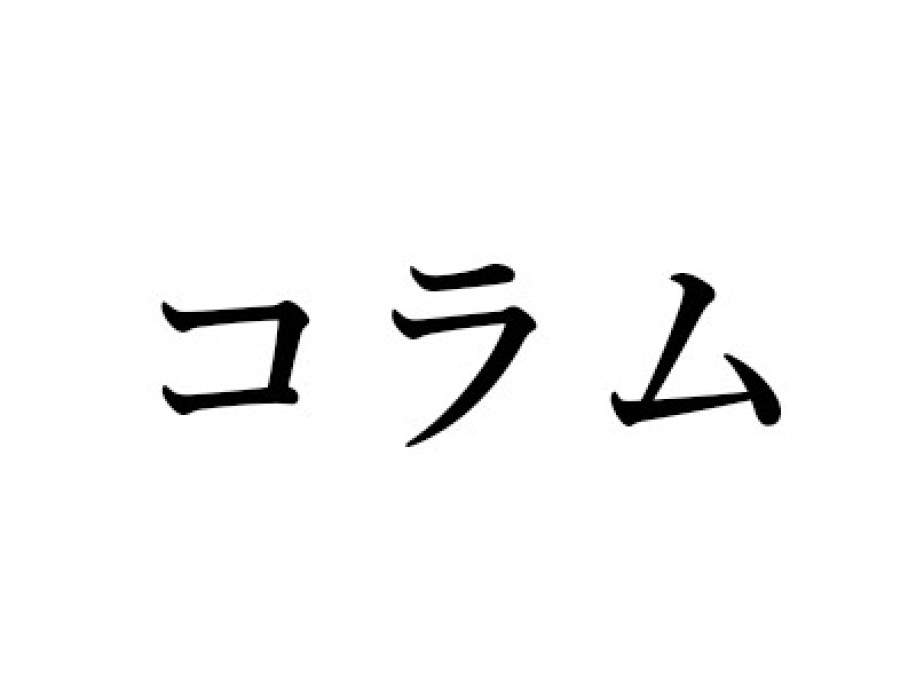前書き
『苦痛の心理学: なぜ人は自ら苦しみを求めるのか』(草思社)
ホラー小説やゲーム、激辛料理、過酷なスポーツなど、人間というのは自ら苦痛を求める生き物であるように見えます。いったいなぜ、私たちは本来遠ざけるべき苦痛に自分から近づいてゆくのでしょうか。実はそこには、科学的に説明できる深い理由があるのです。苦痛から人間の幸福について考察した『苦痛の心理学』から、「はじめに」を抜粋してご紹介します。
人間は苦痛を嫌い、苦痛から逃れるためならば必死になるものだ、と単純に考える人も多いかもしれない。人間とは常に快楽、快適さを追い求めるものだという考え方である。一生、一切何の苦痛もなければそれが一番良いというわけだ。苦痛、苦しみからは逃げたいと思うのが当然ということになる。片付けの達人、近藤麻理恵は、「ときめき」を感じない物はすべて捨てようと皆に呼びかけたことで有名になり、富を築いた。多くの人が、彼女の言葉を良き人生につながる良き助言と考えたからである。
しかし、人間とは苦痛を避け、快楽を追い求めるもの、という考えは間違いではないが、正確でもない。状況や程度にもよるが、実は人間は、身体的、精神的な苦痛、困難や失敗、喪失などを求めることもあるのだ。
あなたがあえて求めるとしたらそれはどのような苦痛かを考えてみよう。映画を見るのが好きな人は多いだろうが、悲しくて涙を流す映画、怖くて叫ぶ映画、見ると嫌な気分になる映画をあえて好んで見に行く人もいるのではないだろうか。悲しい歌をあえて聴くこともあるだろう。あえて痛みを感じるようなマッサージを受けることもあれば、とても辛い物を食べることも、痛いほど熱い風呂に浸かることもあるだろう。山に登る人、マラソンを走る人、ジムや道場にわざわざ殴られに行く人もいる。夢には快い夢より嫌な夢の方が多いというのは心理学者の間では古くから知られているが、実は白昼夢――これは目覚めている時の夢なのでその内容は自分で決められるはずだ――でも、その内容はネガティブなものになりやすい。
この本では、そうした本来良くないはずの体験から人が喜びを得る場合があるのはなぜか、ということを書いている。適切な苦痛は、後の喜びの土台になることがある。つまり、苦痛は、将来の大きな報酬のために支払うコストだということだ。苦痛のおかげで不安から逃れられることもある。苦痛によって自分を乗り越えられることもある。あえて苦痛を味わうことが他人へのメッセージになる場合もある。自分が強いことを知らせるメッセージになることもあれば、反対に助けを求めるメッセージになることもある。恐怖や悲しみといった不快な感情は、演劇や小説などのフィクションにおいて重要な役割を果たすことがある。そうした感情によって作品に対する満足度が上がる場合があるのだ。困難に打ち克つための努力、闘いは確かに苦しいが、困難の程度が適切であれば、達成の喜びが感じられ、「フロー」という心地よい状態に達することもある。
それこそが本書のテーマだ。苦しみと喜びの結びつきについて、あまり適切な表現でないかもしれないが「苦しみの喜び」を書いた本だと言ってもいいだろう。ただ、友人や同僚たちと話し、心理学者や哲学者などの研究者たちの著作を読んでいると、苦しみが喜びを生むことなど本当にあるのかと疑う気持ちも湧く。確かに熱い風呂に浸かること、悲しい歌を聴くこと、ジムや道場で殴られることが喜びにつながることはあるが、それは苦しみ全般に言えることではないのではないか。実際、私たちが求める悪い体験、苦しい体験の中には、単純には幸福などの良い感情につながらないものも多い――それでも私たちはあえて追い求めるのだ。苦しみを肯定し、喜びを否定することがある。
苦しみの中には、自ら望んで受けるものもある。人は、特に若い男性たちは、自ら望んで戦争に行くことがある。何も怪我をしたい、死にたいと望んでいるわけではないのだが、それでもあえて戦争に行きたがることがあるのだ。あえて困難や恐怖に立ち向かい、苦闘したいと望む――使い古された表現だが、「火の洗礼」を受けたいと望むわけだ。それがどれほど大変なことか知っていても、子供を持ちたいと望む人は多い。幼い子供のいる何年かは、人生の他の時期に比べてストレスが増える、という調査結果も得られている。それを知っている人も少なくないだろう(そんな調査を知らない人でも、子供が生まれればすぐに大変さを理解することになる)。それでも、子供を持つという自分の選択を後悔する人は稀である。しろ苦しみと犠牲を伴うその出来事を自分の人生の中心に位置づける人が多い。仮に子育てが容易で楽だったらそうなっただろうか。
苦しみが人生において重要というのは古くから言われていることだ。宗教の教えにもある。たとえば、聖書の創世記にも、人間には原罪がありその罰として生涯苦しむ運命にあると書かれている。仏教にも「四諦」という考え方がある。苦しみが大切という考えは、マックス・ウェーバーの労働倫理の中核にもなっている。
他のあらゆることで意見が合わない研究者でも、苦しみに価値があるということに関しては意見が一致する場合が多い。私が本書の大半を執筆したトロントでは最近、カナダの心理学者で著名なポストモダニズム批評家であるジョーダン・ピーターソンと、有名な極左哲学者であるスラヴォイ・シジェクが討論をした。討論の主題は「幸福」だった。「ザ・クロニクル・オブ・ハイアー・エデュケーション(The Chronicle of Higher Education)」紙に掲載されたこの討論についての記事では、二人の人物像とそれぞれの意見を紹介した上で、両者の類似点も指摘していた。二人がいずれも「苦しみ」を重要視していることは明らかだった。
ピーターソンは「人生の目的は、自分がどのくらいの重荷を背負えるかを見極め、実際にそれを背負うことである」と記している。一方のシジェクは「人生に深い満足が得られるのは、絶え間ない苦しみの人生を送った場合のみである」としている。この言葉はさすがに極端ではないかと私は思う――苦しみは絶え間なく続かなくてもいいのではないだろうか――が、ともかく、苦しみを重要と見ている点は二人とも同じである。
私がこの本で書いていることは複数の種類に分けられる。多くの部分では私が興味深いと思い、読者も同じように思うであろういくつかの「問い」に注目している。たとえば、「なぜホラー映画を好む人がいるのか」、「なぜ自らの身を傷つけたがる人がいるのか」、「なぜBDSM(緊縛、調教、サド、マゾ)に惹かれる人がいるのか」、「望まない苦しみ―たとえば我が子の死―は本当に人を強くするのか」、「苦しみが人を優しくすることは本当にあるのか」、「給料が二倍になれば幸福も二倍になるのか」、「子供を持つと人生に意味を感じるようになるというのは本当か」といった問いである。
本書で私は人間というものをできる限り多面的に理解しようと努力している。人間は苦しみを求めるもの、と考える人がいる一方で、人間は生来の快楽主義者だと考える人も多い。本当のことを言えば常に快楽を得ることにしか興味がないというわけだ。しかし、どうやらその見方は誤っているようである。詳しく調べれば、人間の痛みや苦しみへの欲求が本物であることがわかるからだ。人間とは、ただ快楽を求めるだけの浅薄な存在ではないということだ。多くの人がより深い何かを求め、ある種の超越を目指している。
[書き手]ポール・ブルーム(Paul Bloom)
トロント大学心理学教授。イェール大学心理学名誉教授(ブルックスおよびスザンヌ・レーゲン冠教授職)。道徳、アイデンティティ、快楽の心理学を探求している。学術誌『ネイチャー』や『サイエンス』のほか、『ニューヨーク・タイムズ』『ニューヨーカー』『アトランティック・マンスリー』にも寄稿している。著書に『ジャスト・ベイビー―赤ちゃんが教えてくれる善悪の起源』(NTT出版)、『喜びはどれほど深い?―心の根源にあるもの』(インターシフト)、『反共感論』(白揚社)などがある。
良い人生とは幸福な「だけ」のものか?
人生がうまくいっている時、私たちはつい自分たちの弱さを忘れがちになる。しかし、それを思い出させるものはいたるところにある。痛みは突然、いつ襲って来るかわからない――急に腰が痛み始めることもあれば、どこかに脛をぶつけることもある。頭が少し痛いなと思ったらそれが徐々に強くなることもある。精神的な苦痛に襲われることもある。メールを出す時にうっかり「全員に返信」ボタンを押してしまったために、個人的な秘密が大勢に広まってしまう、そんなこともあるだろう。ここにあげたのはほんのわずかな例にすぎない。私たちの苦痛の種になり得ることは無限にある。そしてその多くは他人からもたらされる。人間は苦痛を嫌い、苦痛から逃れるためならば必死になるものだ、と単純に考える人も多いかもしれない。人間とは常に快楽、快適さを追い求めるものだという考え方である。一生、一切何の苦痛もなければそれが一番良いというわけだ。苦痛、苦しみからは逃げたいと思うのが当然ということになる。片付けの達人、近藤麻理恵は、「ときめき」を感じない物はすべて捨てようと皆に呼びかけたことで有名になり、富を築いた。多くの人が、彼女の言葉を良き人生につながる良き助言と考えたからである。
しかし、人間とは苦痛を避け、快楽を追い求めるもの、という考えは間違いではないが、正確でもない。状況や程度にもよるが、実は人間は、身体的、精神的な苦痛、困難や失敗、喪失などを求めることもあるのだ。
自分から求める苦痛
あなたがあえて求めるとしたらそれはどのような苦痛かを考えてみよう。映画を見るのが好きな人は多いだろうが、悲しくて涙を流す映画、怖くて叫ぶ映画、見ると嫌な気分になる映画をあえて好んで見に行く人もいるのではないだろうか。悲しい歌をあえて聴くこともあるだろう。あえて痛みを感じるようなマッサージを受けることもあれば、とても辛い物を食べることも、痛いほど熱い風呂に浸かることもあるだろう。山に登る人、マラソンを走る人、ジムや道場にわざわざ殴られに行く人もいる。夢には快い夢より嫌な夢の方が多いというのは心理学者の間では古くから知られているが、実は白昼夢――これは目覚めている時の夢なのでその内容は自分で決められるはずだ――でも、その内容はネガティブなものになりやすい。この本では、そうした本来良くないはずの体験から人が喜びを得る場合があるのはなぜか、ということを書いている。適切な苦痛は、後の喜びの土台になることがある。つまり、苦痛は、将来の大きな報酬のために支払うコストだということだ。苦痛のおかげで不安から逃れられることもある。苦痛によって自分を乗り越えられることもある。あえて苦痛を味わうことが他人へのメッセージになる場合もある。自分が強いことを知らせるメッセージになることもあれば、反対に助けを求めるメッセージになることもある。恐怖や悲しみといった不快な感情は、演劇や小説などのフィクションにおいて重要な役割を果たすことがある。そうした感情によって作品に対する満足度が上がる場合があるのだ。困難に打ち克つための努力、闘いは確かに苦しいが、困難の程度が適切であれば、達成の喜びが感じられ、「フロー」という心地よい状態に達することもある。
より充実人生には、意味ある苦痛が必要
それこそが本書のテーマだ。苦しみと喜びの結びつきについて、あまり適切な表現でないかもしれないが「苦しみの喜び」を書いた本だと言ってもいいだろう。ただ、友人や同僚たちと話し、心理学者や哲学者などの研究者たちの著作を読んでいると、苦しみが喜びを生むことなど本当にあるのかと疑う気持ちも湧く。確かに熱い風呂に浸かること、悲しい歌を聴くこと、ジムや道場で殴られることが喜びにつながることはあるが、それは苦しみ全般に言えることではないのではないか。実際、私たちが求める悪い体験、苦しい体験の中には、単純には幸福などの良い感情につながらないものも多い――それでも私たちはあえて追い求めるのだ。苦しみを肯定し、喜びを否定することがある。苦しみの中には、自ら望んで受けるものもある。人は、特に若い男性たちは、自ら望んで戦争に行くことがある。何も怪我をしたい、死にたいと望んでいるわけではないのだが、それでもあえて戦争に行きたがることがあるのだ。あえて困難や恐怖に立ち向かい、苦闘したいと望む――使い古された表現だが、「火の洗礼」を受けたいと望むわけだ。それがどれほど大変なことか知っていても、子供を持ちたいと望む人は多い。幼い子供のいる何年かは、人生の他の時期に比べてストレスが増える、という調査結果も得られている。それを知っている人も少なくないだろう(そんな調査を知らない人でも、子供が生まれればすぐに大変さを理解することになる)。それでも、子供を持つという自分の選択を後悔する人は稀である。しろ苦しみと犠牲を伴うその出来事を自分の人生の中心に位置づける人が多い。仮に子育てが容易で楽だったらそうなっただろうか。
苦しみが人生において重要というのは古くから言われていることだ。宗教の教えにもある。たとえば、聖書の創世記にも、人間には原罪がありその罰として生涯苦しむ運命にあると書かれている。仏教にも「四諦」という考え方がある。苦しみが大切という考えは、マックス・ウェーバーの労働倫理の中核にもなっている。
他のあらゆることで意見が合わない研究者でも、苦しみに価値があるということに関しては意見が一致する場合が多い。私が本書の大半を執筆したトロントでは最近、カナダの心理学者で著名なポストモダニズム批評家であるジョーダン・ピーターソンと、有名な極左哲学者であるスラヴォイ・シジェクが討論をした。討論の主題は「幸福」だった。「ザ・クロニクル・オブ・ハイアー・エデュケーション(The Chronicle of Higher Education)」紙に掲載されたこの討論についての記事では、二人の人物像とそれぞれの意見を紹介した上で、両者の類似点も指摘していた。二人がいずれも「苦しみ」を重要視していることは明らかだった。
ピーターソンは「人生の目的は、自分がどのくらいの重荷を背負えるかを見極め、実際にそれを背負うことである」と記している。一方のシジェクは「人生に深い満足が得られるのは、絶え間ない苦しみの人生を送った場合のみである」としている。この言葉はさすがに極端ではないかと私は思う――苦しみは絶え間なく続かなくてもいいのではないだろうか――が、ともかく、苦しみを重要と見ている点は二人とも同じである。
苦しみを多面的に考察する
私がこの本で書いていることは複数の種類に分けられる。多くの部分では私が興味深いと思い、読者も同じように思うであろういくつかの「問い」に注目している。たとえば、「なぜホラー映画を好む人がいるのか」、「なぜ自らの身を傷つけたがる人がいるのか」、「なぜBDSM(緊縛、調教、サド、マゾ)に惹かれる人がいるのか」、「望まない苦しみ―たとえば我が子の死―は本当に人を強くするのか」、「苦しみが人を優しくすることは本当にあるのか」、「給料が二倍になれば幸福も二倍になるのか」、「子供を持つと人生に意味を感じるようになるというのは本当か」といった問いである。本書で私は人間というものをできる限り多面的に理解しようと努力している。人間は苦しみを求めるもの、と考える人がいる一方で、人間は生来の快楽主義者だと考える人も多い。本当のことを言えば常に快楽を得ることにしか興味がないというわけだ。しかし、どうやらその見方は誤っているようである。詳しく調べれば、人間の痛みや苦しみへの欲求が本物であることがわかるからだ。人間とは、ただ快楽を求めるだけの浅薄な存在ではないということだ。多くの人がより深い何かを求め、ある種の超越を目指している。
[書き手]ポール・ブルーム(Paul Bloom)
トロント大学心理学教授。イェール大学心理学名誉教授(ブルックスおよびスザンヌ・レーゲン冠教授職)。道徳、アイデンティティ、快楽の心理学を探求している。学術誌『ネイチャー』や『サイエンス』のほか、『ニューヨーク・タイムズ』『ニューヨーカー』『アトランティック・マンスリー』にも寄稿している。著書に『ジャスト・ベイビー―赤ちゃんが教えてくれる善悪の起源』(NTT出版)、『喜びはどれほど深い?―心の根源にあるもの』(インターシフト)、『反共感論』(白揚社)などがある。
ALL REVIEWSをフォローする