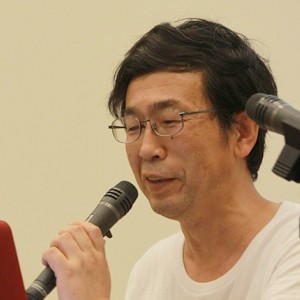書評
『理系の読み方: ガチガチの理系出身作家が小説のことを本気で考えてみた』(誠文堂新光社)
理系作家が発散する「人間のにおい」
理系と文系という問題設定は、古くて新しい。古くは第二次大戦後のイギリスにおける、いわゆる「二つの文化」の知的分断を論じた、C・P・スノーの古典的な論考が有名だし、新しいところでは、大学改革が進行するなかで、理系と文系の二分論を克服するような学際的あるいは領域横断的な知のありようが求められるようになった。そういう観点から、科学が人文学研究にどのような新しい視座や方法をもたらすか、という問題意識から書かれたものも、最近ではよく目にする。こうした議論は問題が一般的で大きすぎるので、フォーカスをしぼって、文系というくくりを文学、さらには小説に制限すれば、理系のバックグラウンドを持つ現代作家は、トマス・ピンチョンやリチャード・パワーズなど決して珍しくはないし、ロシア・フォルマリズムや構造主義批評、ナラトロジーなど、科学的と呼んでもよさそうな論理システムの側面を持つ文学理論もある。
ここで取り上げる大滝瓶太(びんた)『理系の読み方』は、大学院生時代に熱力学や統計力学を研究していたことがあり、後に小説家になったという経歴を持つ「ガチガチの理系出身作家」である著者が、小説を読むこと、小説を書くことに関わるさまざまな問題に、なるべく既存の方法論を使わず、素手で取り組んでみようとする、小説論の勇敢な試みである。「講義編」と「実践編」に分かれてはいるが、書物全体としては理系人間が得意とするようなシステマティックな構成を取らず、むしろ著者が興味を持つテーマからテーマへと自由に動いていく印象が強い。それは、「自分はもっといいかげんな方が向いている気がする」という著者の自認のあらわれかもしれないが、そのおかげで、本書は理系と言われただけで怖がって引いてしまうような一般読者にもとっつきやすいものになっている。それは、本書の弱みでもあり、強みでもある。
あえて言うなら、本書は理系人間が小説を読めばどういう反応を示すかという問題を扱うときに、大滝瓶太という特異な一個の個体を対象に選んでモデリングした結果の考察である。その意味で、本書でいちばんおもしろいのは、講義編の冒頭に「小説を『解く』」という表題で置かれた、カフカの『変身』論だ。大学院生のときに初めてこの小説を読んだという著者は、「なんだか分子シミュレーションみたいな小説だな」という感想を抱き、しかも「カフカを読んでこんな感想を持てなかったら小説なんてさっさとやめていたかもしれません」とまで思うほどだったという。分子シミュレーションとはどんなものか、知らない読者は煙(けむ)に巻かれたような気分になるかもしれないが、著者による図入りの説明は親切丁寧で、『変身』が「(1)閉じた系(2)非平衡(3)非定常の問題を扱った小説」だと言われれば納得できる。寓話(ぐうわ)を「世界のある一面をフィクションでモデリングしたもの」だというのが著者の解釈だが、わたしたち読者は、著者による『変身』のこの独特な読み方を、理系人間による小説の読み方の、それこそ寓話だと受け取ればいいのである。『変身』が分子シミュレーションのような小説かどうかはさほどの問題ではない。大切なのは、大滝瓶太という一読者が『変身』をそう読むことで腑(ふ)に落ちたという、その事実だ。
「自分に似ているひとがいないからこそ、いま考えていることが『世界で自分しか知らないこと』に思えてきます」と著者は書く。その線に沿って、『変身』論に見られるような、本書の言葉を借りれば「能動的」な読者としての大滝瓶太にしかできない読み方をもっと展開してもらいたかった、という恨みは多少残る。メタフィクションの見本とも言うべきイタロ・カルヴィーノの『冬の夜ひとりの旅人が』、さらには本格ミステリやSFといったジャンルを論じるときは、そうした対象が理系マインドの持ち主には親和性が高いだけに、どうしても既視感がつきまとう。ただ、そうした考察を通して、「純文学―エンタメ統一理論」を夢想しているところに、著者の将来性が見いだせるだろう。
著者の読み方に信頼が置けるのは、小説の急所をつかんでいると読者が感じるような瞬間が随所に見つかるからである。たとえば、チェーホフのある短篇を読んで、そこの「暖かい風が吹いていた」という何気ない一文に敏感に反応し、「分析的に考えると『難しい』ことでも、特別な言葉などひとつもない素朴な一文でそれができてしまうことも『小説』の不思議のひとつです」と述べるところがそうだ。
「文理横断ブックレビュー」としてはさみ込まれた小文のひとつは、「執着からは人間のにおいがする」と題されている。それはまさしく大滝瓶太にも当てはまるだろう。小説という、役に立つのかどうかわからないものを、本気で考えようとする著者の姿には、人間の強烈なにおいがする。それと同時に、ひとつのことに熱中する人間には、自然にユーモアというかおかしさが滲(にじ)み出る。それが本書の美点であることは言うまでもない。
ALL REVIEWSをフォローする