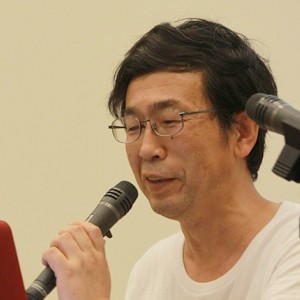書評
『田中小実昌哲学小説集成 Ⅰ』(中央公論新社)
ふらふらと進む「コミマサ節」
<田中小実昌哲学小説集成>が全三巻で出版されるはこびになった。評者は、一九七〇年代の終わりに泰流社から出た、短篇集『新宿ふらふら族』や、直木賞受賞作を収めた『香具師の旅』でコミさんこと田中小実昌のファンになった世代の人間である。ベンヤミンのいう「フラヌール」(遊歩人)を文字どおり体現しているみたいに、夜の新宿界隈(かいわい)をそれこそ「ふらふら」と飲み歩くコミさんの姿がうらやましく思えて、まだ行ったことのないゴールデン街が聖地に見えてきたほどだった。そんなイメージが頭にあったものだから、文芸誌『海』に発表された代表作の「ポロポロ」に出会ったときには、まるであの「コミさん」が突然「田中小実昌」に変身したような感じをうけた。こんど「哲学小説」としてシリーズの扱いを受けた晩年の作品群は、はたしてあのコミさんとどうつながっているのか、そんな興味で第一巻を読んでみることにした。
哲学小説といっても、そういう呼びかたでいいのかどうか。ここに集められている作品群は、コミさんが電車やバスのなかで、ショルダーバッグに入れていた文庫本の哲学翻訳書を読んで考えたことが主に語られている。どうして哲学書なのかといえば、小説の「しゃべりかた、息づかい、生あたたかいにおい」が感じられなくなったからで、哲学の本のほうが「おかしなにおい」がするという。小説からにおいが消えてしまえば、そこには物語しか残らない。矛盾しているようだが、それはクサい物語だ。だからコミさんの小説は、物語になることを拒否していて、読んだあとでなんの話だったか忘れてしまう。
コミさんの書くものを支えているのは、まず目や、耳や、鼻や、口だ。とりわけ、映画を見ているときに発揮される、ことばに対する目や耳のなんと鋭敏なこと。哲学書を読んでいてもそうで、たとえば本書に収録されている「カント節」と題する短篇では、カントの『プロレゴメナ』の一節「しかし、理性はいかなる権利をもって、最初の何か或(あ)るものがこのような性質(原因と結果との必然的連結)をもち得ると思いなすのか、と問うのである」といった、コミさん流にいえば「うなりかた」におかしさを感じて、それを「カント節」と呼んでいる。難解そうなことばのむこうにいるカントの大マジメぶりと、その息づかいを楽しんでいるコミさんを見ると、読んでいるこっちまで楽しくなる。
コミさんの文章は、感情の起伏が乏しいおかげで、絶対に酔わないお酒を飲むみたいに、いつまでも読んでいられる。とりとめもない話をしている最中に、ふと真顔に返って、「ただ一つの道だろうとなんだろうと、道ってのは、ぼくは好きではない」といった、ドキッとすることばが出てくるのもコミマサ節だ。
ライプニツの『単子論』を読みながら、「わかったような気になるが、またくるっとわからなくなる」とコミさんはつぶやく。コミさんを読んでいると、なんだかよくわからないが、そのわからなさがおもしろい。この「哲学小説」が小説かどうかはどうでもよくなる。そして、コミさんの小説は、いつも話を適当なところで切り上げて、ふらふらと店を出て行くように終わるのだった。
ALL REVIEWSをフォローする