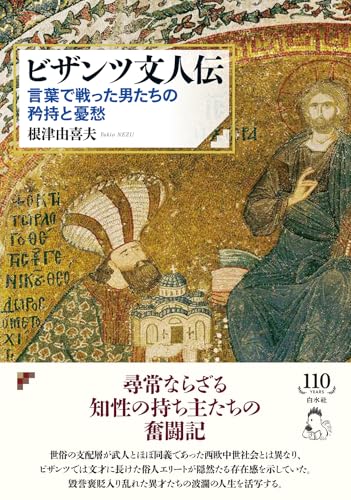書評
『いかさま師ノリス』(白水社)
懸命な「悪人」弱さに共感
かつて中野好夫は、「悪人礼賛」というエッセイで、こう書いた。「オセロとともに天国にあるのは、その退屈さ加減を想像しただけでもたまらぬが、それに反してイアゴーとともにある地獄の日々は、それこそ最も新鮮な、尽きることを知らぬ知的エンジョイメントの連続なのではあるまいか」。まことにそのとおり。『オセロ』のイアゴーの他にも、『オリヴァー・ツイスト』のフェイギン、『第三の男』のハリー・ライムといったぐあいに、英文学は魅力たっぷりな悪人たちの宝庫である。そして、『さらばベルリン』と並んでクリストファー・イシャウッドの代表作とされるこの『いかさま師ノリス』に登場するアーサー・ノリス氏も、そうした有名な悪人たちの仲間に加わるだけの資格を充分に持っている。物語の舞台は、一九三〇年、華やかなワイマール文化に翳(かげ)りが見えだし、混乱や破局へと向かいつつあったベルリン。そこにやってきた語り手の英国人ウィリアム・ブラッドショーは、列車の中で出会った同郷人にして自称紳士のノリス氏とつきあうようになる。「あぐらをかいた大きな鼻に、横にずれたような顎(あご)」の持ち主であり、かつらをかぶっているこの奇妙な男は、パスポート検査であたふたする。貿易商の表札を出しているが、どんな商品を扱っているのかはわからない。SMの嗜好があり、その手の好色本のコレクションを所蔵している(後になって、実はそのうちの一冊は自分が書いたものだとノリス氏が告白するくだりは、この小説で最もパセティックな場面のひとつだ)。金に困っているかと思えば、なぜか大金を手にしている。そして、パリにいるマルゴという女性(?)と、なにやら暗号で書かれているらしい秘密の通信を交わしている。
何から何まで怪しげなこのノリス氏に対して、語り手は肩入れする。「知性に優れ、慈悲に篤く、人間の本質に深く通じている」と自認する彼は、祖国に書き送った手紙の中で、ノリス氏のことを「名うてのペテン師」だと呼んでも、「それは私が彼という人間を栄光に包まれた存在と思いたがっていたことを意味するにすぎない」と言う。そんな語り手を、人生経験不足だと非難することは簡単だろう。しかし、読者もこの語り手と同じように、ノリス氏に対して共感に近いものを覚えるのは、彼が人間の弱さをあからさまに露呈してしまうからである。みえみえの嘘を平気でつける政治家のような真似は、彼にはできない。神経の脆弱な「いかさま師」、それがノリス氏であり、世間的には悪人であっても、いかにも人間らしい。
この小説には、普通の意味での善人はごくわずかしか出てこない。登場人物たちはみな喜劇的小説らしくデフォルメされているように見えるほどで、その中では一人まともに見える語り手ですら、ノリス氏の「取引」の片棒を担いで、刑事に尾行される身となる。そして、バルザック風の人間喜劇を想わせるこの小説は、一九三三年、ナチスが政権を完全に掌握し、ユダヤ人や共産主義者の排斥が始まって、「感染性の高い恐怖」がベルリン市内にじわじわと広がっていくところで幕を下ろす。そうした激流のような時代にあって、世間を泳ごうとした「いかさま師」ノリス氏の肖像は、一読忘れがたい印象を残すのだ。
ALL REVIEWSをフォローする