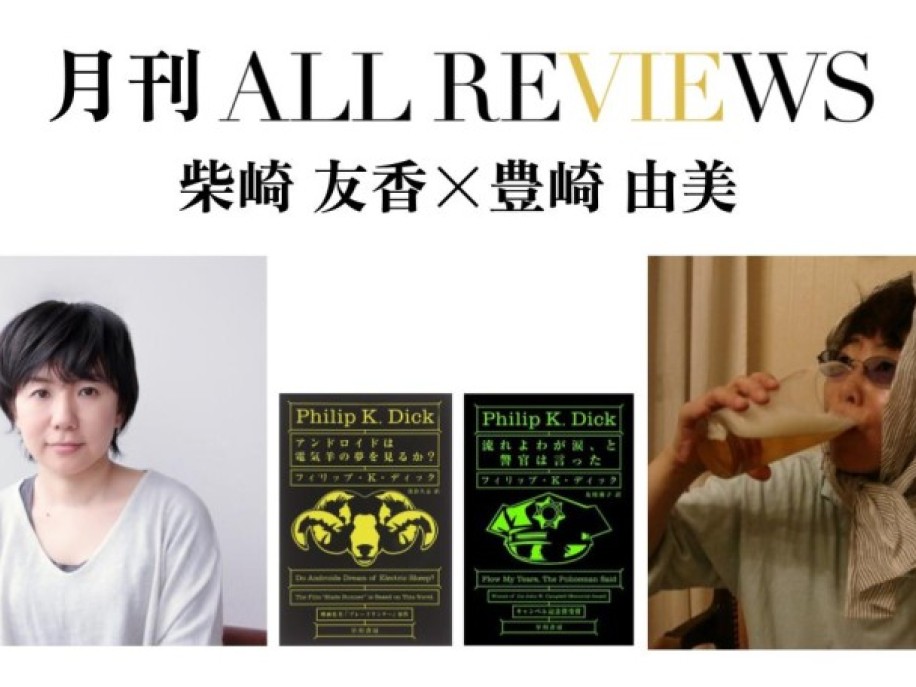書評
『待ち遠しい』(毎日新聞出版)
漠然とした心もとなさを癒やす庭の存在に惹かれる
噛み合わない相手とは接触を避けたり、会話を交わさずやり過ごしたり。とかくストレスの多い昨今、どうにか機嫌よく暮らすためには、他人と関わりすぎないのも自己防衛のうち-そんな風潮が強くなっている気がする、私自身を振り返ってみても。トシのせいもあるのかな。でも、と思う。それを続けていたら、閉じた貝殻みたいになってしまうし、まわりの空気も硬くなってゆくのではないか。柴崎友香著『待ち遠しい』は、同時代を生きる世代も価値観も好みも違う女性たちの、噛み合わなさそうで、でもナニカが触れ合う、繊細な揺れのなかでの交流を描く長編小説だ。とかく言葉が生まれにくい溝や隔たりのなかから、小説家は掬(すく)い上げるようにして言葉を見いだし、繋げてゆく。
三人の女性たちが登場する。
三十九歳の会社員、春子。ひとり暮らし歴十年、趣味は消しゴムはんこ作り。感情の起伏が苦手で、自分のペースを大切にしながら暮らしている。
六十三歳のゆかり。二年前に夫を亡くし、春子が借りて住んでいる離れの母屋(おもや)に、大家として引っ越してきた。
二十五歳の沙希。ゆかりの甥の妻で、新婚。早く子どもが欲しいと思いつつ、どこか頼りない夫に不安を抱えている。
世代も価値観も趣味も違う三人が、目と鼻の先に住む偶然によって、おずおずと交流が始まる。食事にこないかと盛んに誘う母屋のゆかりに、最初は抵抗を感じていた春子は少しずつ胸襟を開いてゆく。自分を守りながら生きてきた春子は褒められるのも苦手で、とかく「自分なんて」。閉じかけていた三十九歳の殻に、折に触れ、ゆかりがおおらかな空気を通す。しかし、そのゆかり自身が抱えているのは、亡夫への後悔の念や実の娘との絶縁状態だ。ささやかな日常のなか、探り合いながらも、見知らぬ他人同士だったふたりが距離を縮めてゆくさまを、定点カメラの視点が描いてゆく。
若い沙希は、過激なふるまいと物言いでふたりに関わってくる。長年ひとりで暮らす年上の女性は、沙希にとっては不可解な存在だ。「春子さんて実はすごい冷たい人なんちゃう」と言われ、「そう思われるところはあるかも」と応じる春子の言葉は、曖昧だけれど、とても率直だ。
とくに大きな恋愛もしてこなかった春子が、友人に吐露する場面に心動かされた。
「(前略)わたしはどこか欠けてるんかな、人間として足りへんのかな、ってずっと思ってて。このまま、自分は、条件満たしてない存在として生きていかないとあかんのかな」
結婚や仕事をしていても、していなくても、どこか似た思いを抱えながらひとは生きている気がする。おぼろげな不安や欠損を補い合ったり埋めたりするのが、血の通うナマの言葉なのだろう。たとえそれが不器用であっても。
春子が住む離れとゆかりが住む母屋とのあいだに、小さな庭が広がっている。その庭の存在がとてもいい。風穴のような、空気の通り道のような、ときには逃げ道のような装置。ひととひととのあいだには、回路としての庭が無数に用意されていると思うと、胸のつかえが取れる。読後、そんな庭の訪れもまた「待ち遠しい」と思った。
ALL REVIEWSをフォローする