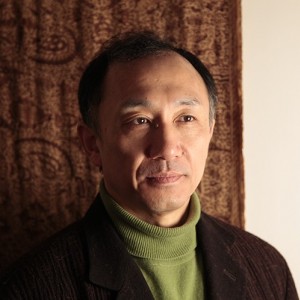書評
『ファスト化する日本建築』(扶桑社)
見栄えではなく、あるものを活かす手法
昨年来、SNSで「腐る建築」が話題になっている。ある公立美術館で屋根や壁に配された木が朽ち、次々に剥落したのである。築後24年で3億円もの改修費が必要となったが、設計者が新国立競技場を手がけた著名建築家だったことも注目された。同じ建築家の作品を追ったニュース番組は、ある私鉄線の駅舎では柱が築後9年で黒く変色し、市庁舎では庇(ひさし)の裏側の木が築後6年でカビにより腐ったと報じた。共通するのは表面に塗膜のない無塗装の白木の角材で、専門家が「格子や簾(すだれ)のごとくに美しい」と評し、伝統的な日本の木の文化を現代に蘇らせたかのように称えた。日本建築の伝統では、木造の寺社が数百年、千年以上の風雪にも耐える。一連の「腐る建築」は、日本建築の伝統に何か異変が起きているのかと懸念を呼んだ。
この問題で多くコメントしてきた森山高至氏は、『ファスト化する日本建築』でその入り組んだ背景を解説している。伝統建築は、世界中で異なる気候や地形がもたらす寒熱や乾湿を和らげる技術をそれぞれに進化させ、資材には地元産の樹木や石材を用いてきた。
なかでも日本の気候は高温多雨を特徴とし、伝統的な木造家屋では茅葺(かやぶ)き屋根が雨を防ぎ、湿度を調整した。ススキやヨシを湿原から毎年採集し、大工の職人技はその「重ね」と「勾配」で雨を受け流し、屋内への浸入は「水切」りで外に逃がした。柱や床の木材は50年ほどのサイクルで育て、定期的に入れ替えた。カビや菌類を防ぐため、時の循環に沿って樹木を育て製材し、茅を葺き替える工夫を行ったのである。
ところが近代に入ると建築には重大な転機が訪れ、化学的に合成された素材が登場した。石灰岩を焼いて粉末にし、液体にして型に流し込むコンクリートは、固体の組み合わせではなく気密性の高い建築を実現し、合成樹脂系の防水剤も継ぎ目を密封したため、四角く自由な造形が可能になった。これらの素材により、世界各国のいかなる気候や自然においても住空間として均質な人工環境が得られるようになった。
「腐る建築」は、内部をコンクリートや合成樹脂、ガラスやサッシュで構成している。外部には伝統を装い木の薄板を貼り付け、それでいて草木を時間の経過とともに循環させることには労力を割かなかった。伝統から白木だけ真似る「ポストモダン」建築だったのだ。
だが本書の核心はその先にある。環境に即して長持ちさせるために時の経過や循環を用いる伝統が、長く続く不況のただ中にあって、短期的に利益を上げる目的から日本建築のあらゆる方面でうち捨てられつつあるという。それが「ファスト化」だ。
短期的に見栄えがするが長期的には「腐る」公共建築。建築物の外観を街並みに揃える手間暇を省き、一望できないほど巨大化した「ショッピングモール」。大規模改修が必至であるのに全世帯での積立金が覚束(おぼつか)ない「タワーマンション」。大工の棟梁のように現場全体の責任を担う人がいなくなった「建築人材」。共有されてきた神社や公園の土地を不動産会社が私有化する「都市再開発」。景気対策にすらならない五輪大会を誘致した「国家」。持続可能性の低い建築が蔓延しつつある。
では近代建築の利点を取り込みつつ、伝統建築の美点を継承する建築家は現存しないのか。社会思想家の中島岳志氏は『建築と利他』で、そうした一人として堀部安嗣氏を遇している。堀部氏は評者所有の「阿佐ヶ谷書庫」を含め住宅を多数手がけ、代表作は高知の竹林寺納骨堂。庫裏をはじめ、同寺全体に改修を施した。
中島氏は、納骨堂へのアプローチの道を「木の根っこを避けるように曲」げた点に注目している。土地を更地にして新しいものをつくるのではない。すでに「あるものを活かす」、周りの環境や土地の来歴、生えている草花などに沿う建築手法である。
伝統建築の職人は、施主である旦那から求められてもできないと断ることがあったという。自然の摂理や住民の過去の記憶を個人の趣味嗜好(しこう)よりも優先するためで、堀部氏も風呂、洗面所といった身体に即したユーティリティや納戸を先に配置する。その方が具合良く余白が残るからで、その後に居間の食洗機や床暖房を当てはめていく。設計の急所は「配置計画」にある、と断言する。
一部で対談に加わる竹林寺の住職は、堀部氏が境内を歩いたり佇(たたず)んだりに時間をかけ設計したと証言している。本坊を深く掘り下げたところ地中から鎌倉時代の石垣が出て、当時の表玄関と判明した。土地の来歴を正しく掘り当てたのだろう。
現在の日本社会は、樹木を伐採する再開発を乱発している。黄昏時や木漏れ日の記憶は現実にたどり返せなくなるだろう。記憶の手がかりを捨て去る社会は危うい。この二冊はそう教えてくれる。
ALL REVIEWSをフォローする