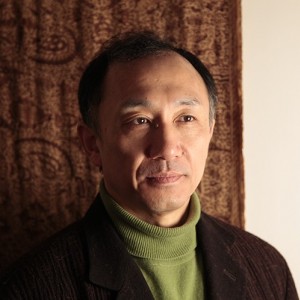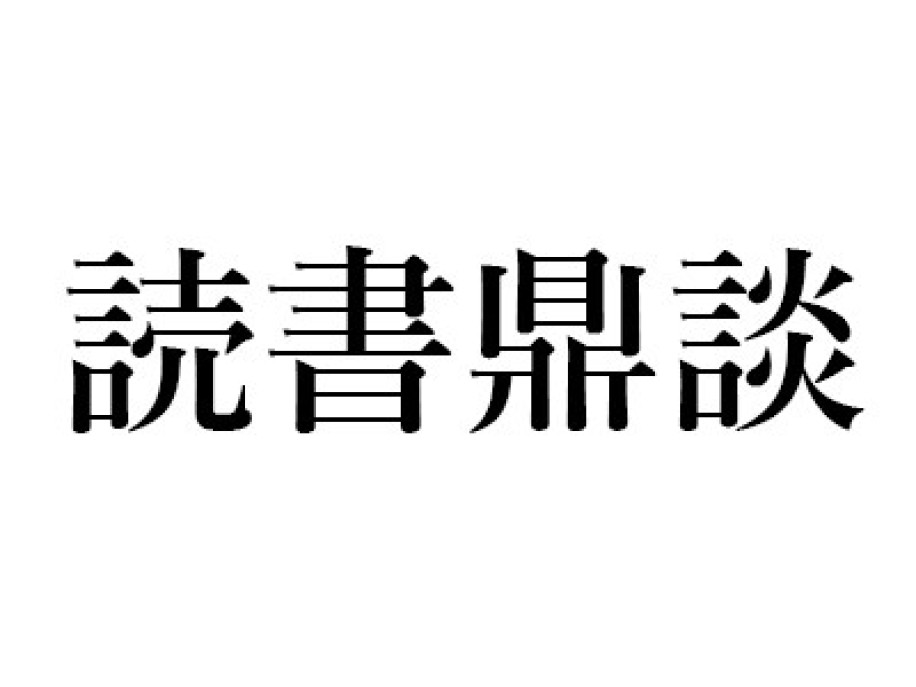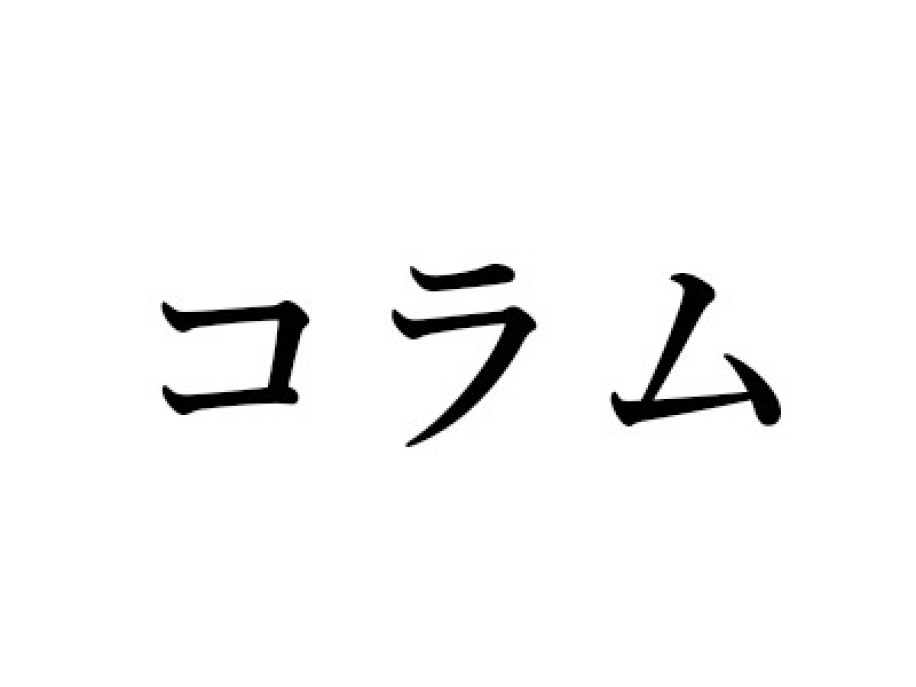書評
『未完の建築――前川國男論・戦後編』(みすず書房)
余白、敷地の外へも、人の温かみ
前川國男(1905~1986年)は「近代建築のひとつの頂点」(加藤周一)と評される京都会館(1960年竣工)や「音楽の殿堂」東京文化会館(1961)等、多数の作品を設計し日本の建築文化をリードした大建築家である。本書は晩年の事務所に6年間在籍した著者が、『建築の前夜 前川國男論』に続き足跡をたどる戦後編。前川建築が市民に愛されるのには秘密がある。それでいて没後には前川のモダニズムを冷笑するかのようなポスト・モダニズム建築が流行った経緯がある。著者の前川論が併せて1100ページを超える大部となったのは、前川建築の秘密を解き明かし、前川への批判が有効でないことを論じたからである。それでも本書が一気読み出来てしまうのは、文体に建築評論にありがちな難渋さがなく、前川と対峙(たいじ)するかのごとく作品ごとにコメントを付しているからだ。
戦後で圧巻なのが、前川が建築技術を進化させていく1970年ころまでのモダニズムの進展だ。伝統的に日本では地震のため骨組みが超重構造であり、建築単価が高くなっていた。そこで前川は高性能軽量資材を追求、鉄筋コンクリートからサッシュ、ガラス、タイルまでつぶさに検討した。漏水や汚れやすさといった欠点が生じれば修正し、炻器(せっき)質タイルを打ち込む構法に到達して、おおらかで自然な美しさを獲得した。この構法により、岡山県庁(1957)や熊本県立美術館(1976)の壁には独特な温かみがある。
一方、設計上の技法として、戦前から引き継いだ「空間構成」がある。前川は「日本的なもの」として日本画の「余白」、すなわち図と地の関係を見る。そこから自邸(1942、江戸東京たてもの園に現存)や在盤谷(ばんこく)日本文化会館(コンペ、1943)では、敷地内に引き込まれる「建築外的空間」と、敷地の外へと広がる「環境的空間」を有機的にむすびつけ、全体の空間を構成した。さらに戦後になると、人の歩みによって内外の風景が流れるように展開する「一筆書き」の技法が開発された。その到達点として実現したのが埼玉県立博物館(1971)で、その場に立って初めて体感しうるため写真には撮影しづらく、包み込まれるような空間構成となった。
評者は経済学者だが、経済には経済だけでは完結しえない矛盾が秘められていると考える。市場は効率的であっても将来の不確実性が高まると、将来不安から人口は減り労働力は不足する。競争は自然資源の乱獲を促進するし、規制が緩いと金融取引は危機に瀕する。前川が魅力的なのは、建築は目立つだけの、たんなる商品にはなりえないと洞察したからだ。
建築は一面において商品だが、住宅が環境やコミュニティから切り離され町の一部でなくなると、住民は愛着を持てなくなる。そこで前川は建築家に「人間的な温かみ」を付加する配慮を「社会的使命」として求めた。そうした使命を不要とみなすポスト・モダニズム建築は商品化に走りやすく、「嫌なものを見てしまった」と評する人もいる。
近年では公共建築でも竣工して数年もしないうちに雨漏りし、装飾の木材が腐る例が後を絶たない。役所も早々に取り壊そうとする。前川が建築に夢見た永遠性は朽ち果てようとしている。
ALL REVIEWSをフォローする