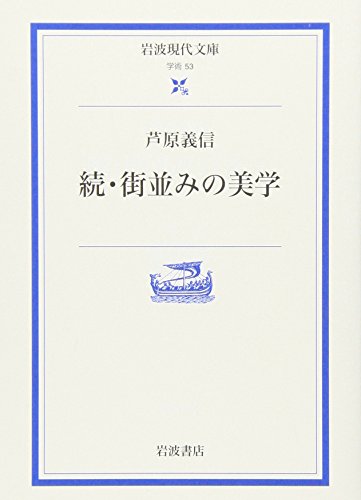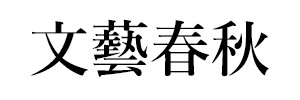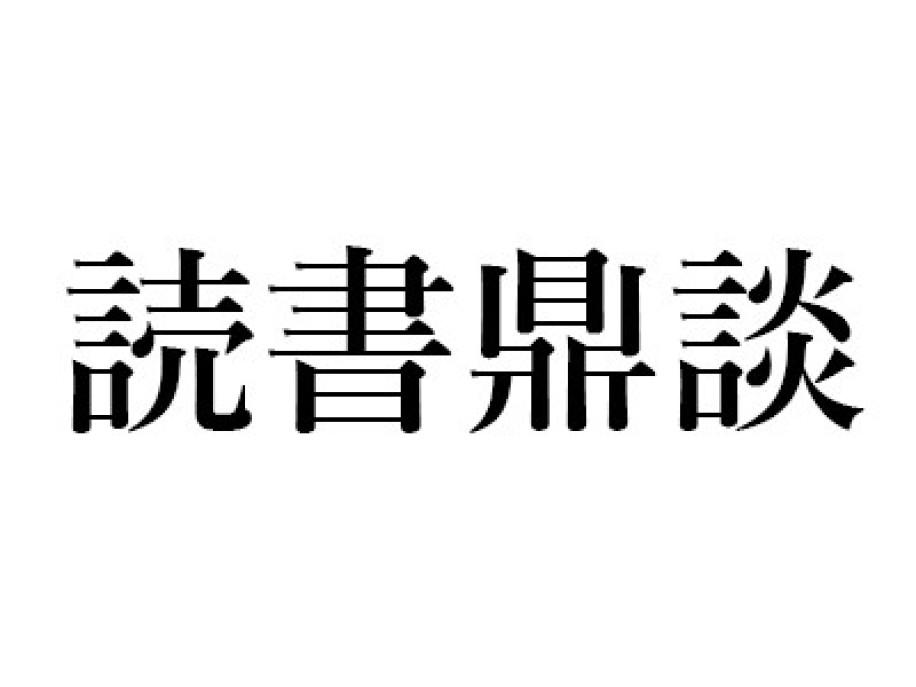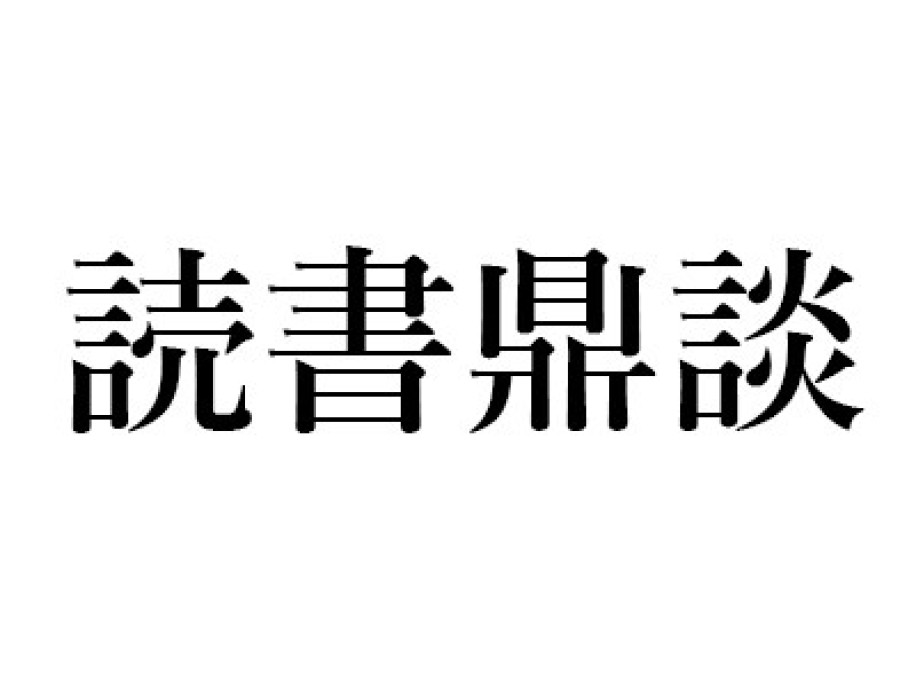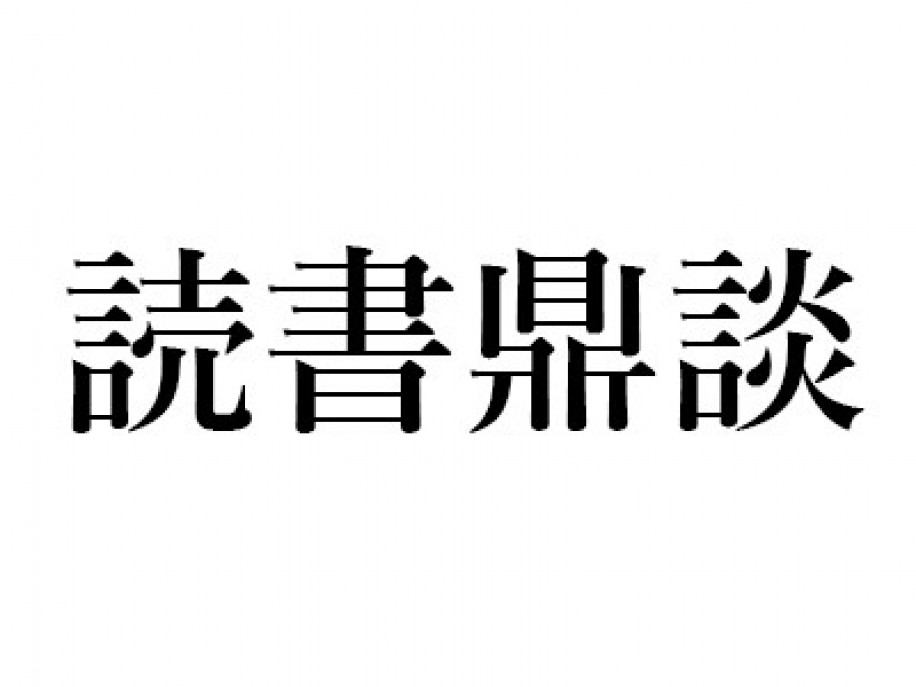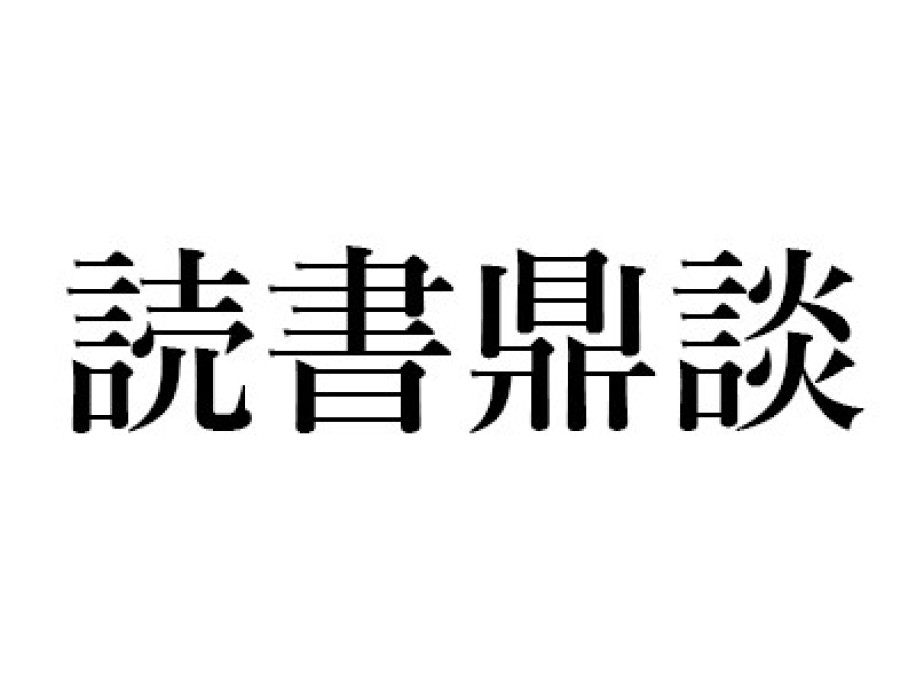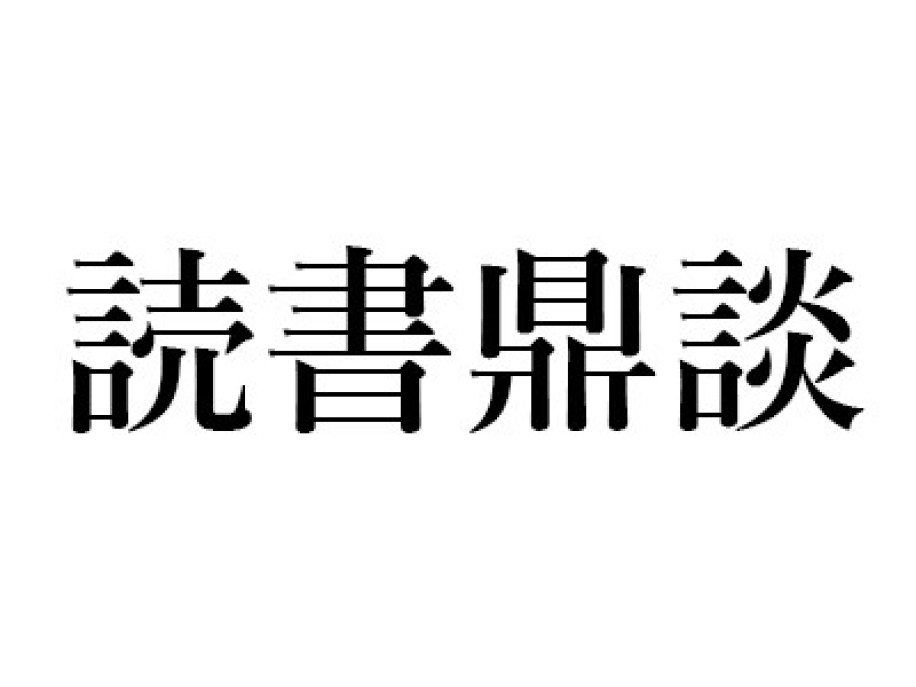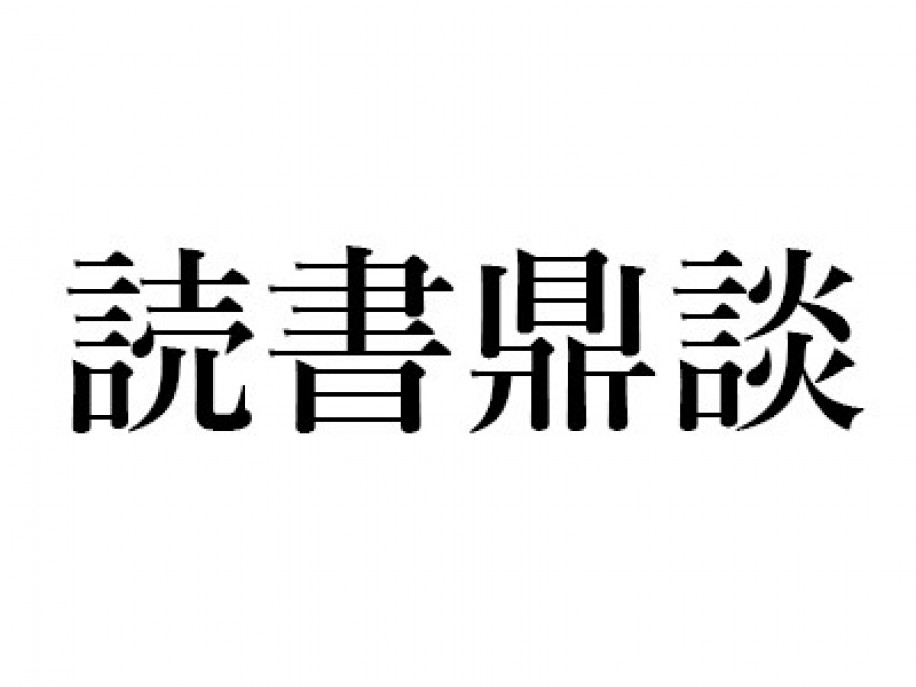対談・鼎談
芦原 義信『続・街並みの美学』(岩波書店)|丸谷 才一+木村 尚三郎+山崎 正和の読書鼎談
木村 著者の芦原さんは、国立歴史民俗博物館や金沢市の文化ホール、第一勧銀本店などの優れた建築設計で知られ、昨年度の芸術院賞を受けられた、現代日本有数の建築家です。
五年前に出された『街並みの美学』は毎日出版文化賞とマルコ・ポーロ賞にかがやきましたが、その続篇がこの本でして、日本と欧米の街並みを比較し、都市美を考察した、すぐれた文化論になっております。
まず芦原さんは、西欧の建築を「壁の建築」、わが国の建築を「床の建築」として把えます。
西欧の建築は外壁がしっかりしていて、その連続として街並みが表現される。いわば線的な要素が重視されるわけです。
それに対し、日本では、床が地面より一段高くにあり、そこへは土足で入らない、というふうに、床という領域が重視されます。そして壁より床に執着した点に、日本で整然とした街並みができにくかった理由があるというわけです。
その違いは、たとえば住居表示にも表れておりまして、西欧では通路に名称をつけ、順番に住居表示(ハウスナンバー)をつける線的システムが本流になったのに、わが国では、◯◯県、××町、△△番地という領域システムを採用しているし、日本ではまた家の中に対し道路は下位の空間でしかないから、道路に名前をつけるという発想も少なかった、と説くのです。
さらに、欧米では外からの景観に重点がおかれるのに対して、床の上に生活する日本では、内から眺める景観が重視され、外観には無頓着でした。
こういう都市のあり方を別の局面からいうと、日本の都市には中心がない。それは、〈都市空間における自己の滅却であり、個人は大きな空間の全体性の中に溶けて平均化してしまう〉という日本独得の性格によっている。〈わが国の都市はこのように、中心性を欠き常に変貌しながらスプロールし、骨のない軟体動物のように、しかも、毀されても、焼かれても、再び蘇生してくるアメーバのような一体性をもっている〉。――ヨーロッパの都市が教会や市庁舎を中心に配置されているのとは、大きな違いです。
このことをビーフステーキとすき焼きという、ロラン・バルトが使った比喩で説明しています。ビーフステーキの料理にはビーフステーキという中心があるのに対し、すき焼きは、牛肉、野菜、豆腐、こんにゃくが渾然と一体化して、何が主役か分らない、というわけです。
その上で、日本の雑然とした都市を少しでもよくするために、様々な提言がなされています。たとえば、都市の色について考えてみたらどうか。パリでは白から黒にいたる無彩色が街の基調をなしているため、パリジェンヌの唇の赤や華やかな衣服がよく映えるのに対し、極彩色が氾濫する日本では、どんな美しい服装をしてもひきたたない。スペインには赤褐色の瓦色が、ギリシャでは真白な壁が、街の色をなしているけれど、日本には人を美しく見せる街並みがない。
そのほかにも、都市を緑化する、都市の中に水を流し、昭和の大運河を作る、自動車より人間を優先する道路を作る、電柱や醜い屋外広告物を撤去するなど、街並みを美しくする数々の具体的提案がされています。
結局のところ都市の建物はすぐれて文化的な問題で、パリのエッフェル塔と東京タワーを比べると、エッフェル塔をなくせば、パリがパリでなくなるのに対し、東京タワーを取りのぞいても、テレビが見えなくなる以外、街並みには何の影響もないだろう。つまり東京タワーが「技術」の産物であるのに対し、エッフェル塔は、「技術」に対する「文化」の優位性の象徴だ、というわけです。
しかし著者は、単に日本の街並みを悪しざまに批判しているわけではありません。近代建築の精神――重力よりの解放、流動性のある空間、といった精神は、すでに日本の伝統的木造建築に存在していた。一見雑然としている日本の都市も、見ようによっては民主的であり、表現の自由があり、バイタリティにあふれている……。といった具合に、現代の日本の都市のいい点と欠点を共に見すえた上で、これからの都市づくりを提言した本です。
丸谷 日本の学者が社会に向けて発言すると、以前は、おおむね、抽象的・観念的な説教になるのが普通でした。ところが最近、具体的な提案をするようになってきた。
その一例としては、経済学者の伊東光晴さんの『経済学は現実にこたえうるか』という岩波書店から出た本がありますけれども、もう一つその手の本を挙げるとすれば、芦原さんのこの『街並みの美学』正続二巻だろうと思うんです。いつも具体的に語って、しかもそれが高い識見に支えられている。学者が社会にむかって物を言うときの態度として模範的なものだという感じがしました。
具体的な提案については、いま木村さんの紹介の中にありましたが、一つだけ繰り返しますと、街中の電柱を撤去せよ、といっている。第一に都市美に反するし、第二に道の幅が狭くなる。第三に、これは芦原さんが述べてないことですが、電柱にいろんなものを貼るせいで、運転手が気をとられて交通事故が多くなる。(笑)やはり、ほかの先進国なみに電柱は取っ払ったほうがいいと、かねがね僕は思っていたのですが、ここに頼もしい援軍をえました。(笑)
実はある席で「電信柱は全部取っ払うべきだ」と私がいいましたら、電電公社の偉い人が、「電電公社の電柱は全国で千四百万本もあって、取り払うには四兆円かかる。とてもできるものではない」というんです。私は貧しい小説家ですので、つい家計と比べ「四兆円、それは大変だ」と思ったんです。(笑)ところが同席した経済学者たちは「あ、たった四兆円ですか」とこともなげに言いました。(笑)
ただし四兆円には、電力会社の電柱は入ってませんから、もっとお金がかかりますよね。仮に十兆円だとしても、都市部の電柱だけなら六兆円くらいで済むんじゃないか。いまの日本の財力を考えれば、大したことないと思うんですよ。
山崎 電柱がなくなると、犬が小便するのに困るという説があります。(笑)
丸谷 スズメのとまる場所がなくなるとかね。(笑)私の意見は単に電信柱撲滅論にすぎないけれど、芦原さんの意見には、東京タワーは巨大な電柱である。そして巨大な電柱にすぎない以上、街並みの美学のためにはあれだって無いほうが望ましいという一段次元の深い、鋭い指摘がある。都市美に反する醜悪なものが戦後にそそり立ったということ、あるいはそそり立つことを許した日本人の感性、それを批判する視点があるんですね。
最近、「資産倍増論」とかいう議論があって、風景美を高めることが資産になるという主張がその中にあるらしいんですが、日本の政治家がそのようなことを言い出したというのは大変いいことですね。政治家たちは、ひとつこういう本を読んで、大いに刺激を受けてもらいたい。
聞くところによると、銀座の若旦那衆たちがつくっている会があって、芦原さんを顧問格に招いて、銀座の美化と取り組んでいるそうです。これは大変結構なことで、そういう努力を日本じゅうの町の若旦那がするべきだと思います。
山崎 都市景観についての具体的な提案を含んでいますけれども、それと同時に、比較都市論、比較建築論であり、また日本文化論になっていて、それぞれの面から非常に面白い示唆を含んでいると思います。
西洋は「壁の建築」で、日本は「床の建築」であるという視点は、誰でも知っているようでいて、あらためてこういうふうに整理されてみると、なかなか鋭い指摘だということに気がつきます。日本の建築史を勉強した人間ならば、平安時代に中国の建築に対して和風建築が成立したとき、そのもっとも大きなポイントは、床を張ることと、屋根を水平方向に強調することであった、ということはよく知っているはずです。しかし、それを敷衍して、歴史を貫いて日本の建築の運命を決定したのは床の思想であり、それが現代の都市の日本的特色を決定しているというところまで議論した人は少なかった。コロンブスの卵ではないですが、鋭い発見は身近にあるといういい例だと思います。
要するに、床の建築の思想は、建物、あるいは世界を内側から見るということなんですね。それに対して、壁の思想は自分のいる場所を外側から眺めるということだ、というのが芦原さんの考え方です。したがって、内側から見ている限り、この世界は個人の生きる空間の数だけあることになるわけで、極めて多元的な世界ができあがる。それに対して、建物を外から見ているという姿勢は、延長していけば結局、全世界を一つの視点から客観的に見るという考え方に繋がり、そこから一元的普遍主義が生まれてくる。なかなか巧みな分析だと思います。
日本の庭は建物の内側から見るようにできていて、外からみるとつまらないというのは、その通りですし、内側から見るために空間がずたずたに切り裂かれ、一つの視点ごとに一つの視界ができるというのも、日本文化の特色の一つです。この点は、ライシャワー氏が「日本文化のコンパートメンタライゼーション」という言葉で説明しています。日本人は視点を変えて美しい部分を切り取って見るけれども、それは同時に、見ぬもの清しの思想だというんですね。他の視点からは汚いものが見えてくるんだけれども、そこはないことにしておく。したがって日本文化には美しい部分が沢山あるが、同時に汚い部分が排除されていない。
そういう多元的空間の意識が基本にあって、そこから日本の都市の良さも悪さもでてくるというのが芦原さんの考えです。
ちなみに私自身は、この問題に別の見解をもっていまして、近世以前の日本の都市は大体、盆地にできていますので、内側から見た自分の世界を限るのは、建築ではなく山並みだった。「ふるさとの山は有難きかな」というわけで、山が心理的囲いになっている。そこでは建築は衣裳のようなもので、薄くて軽やかなものでいい。山々に囲まれていれば「中心のある統一的都市構造」は必要なかったと、そう考えてきたわけです。
芦原さんの考えは、建築家らしい見方で、たいへん面白いと思います。そのうえ、芦原さんは西洋建築の教養のもとで育った人で、西洋の都市美に憧れをもっている、その観点から、日本の都市を批判します。批判しながらも、日本の都市への強い愛着を隠しておられない。
私は日本文化について、裏返していえば、それに対置される近代西洋について、こういう矛盾した感情をもたないで論じる人間を信じないことにしているんです。一方的な近代主義者は愚かですが、夜郎自大な日本文化礼賛論者も情けないと思う。どの道、我々は引き裂かれて生きるほかはない。芦原さんもそういう自覚をもっておられることで、その主張は健全だという安心感をもちました。
木村 「壁の文化」「床の文化」という指摘は、本当に我々をドキリとさせるものがありますね。ヨーロッパの場合、堅固な壁に囲まれた個々の家が、さらに連続して都市美をつくり出せたのは、地続きという状況の中で、都市全体を厚い城壁で囲む、「囲みの文化」というものがあって、点と線の国際的ネットワークを作り出し、外側から自分を見る厳しい目を養わざるをえなかったからだと思います。同じく国際組織を作り出したヨーロッパの修道院も、「囲みの文化」ですね。日本の都市は幸か不幸か海に囲まれた島国にあり、十七世紀からすでに政治統合が実現されてしまうわけですから、対外的緊張感が稀薄で、外から自分を客観的に見つめる必要はなかった。ただたとえば金沢、京都のような、自然の厳しさへの緊張感とか、自然の城壁としての山に囲まれている所では、市民相互の連帯感が生まれ、ヨーロッパとあい通ずる都市美を育てたんだろうと思います。
それにしてもこの本には、日本の現状を変革して都市美を作り出す具体的な提言のあることが、私にはとても嬉しいことでした。
丸谷 まったくその通りで、具体的提案には一々賛成なんですよ。日本の駅前はどこも同じである。駅の前に木を植えるようにしたら、それぞれ印象も違ってくるだろう、ということなどは非常に説得力がありますね。
理論のほうも概(おおむ)ねいいと思うんです。しかしヘンだと思うところもありますね。住居表示で、日本人は個我の意識が乏しいから、まず県がきて市がきて町がきて番地がきて、最後に名前がくる。西洋では反対に人間の名前が最初にくる。これは個我の強さの表れである、とおっしゃる。果してそうだろうか。
日本人に個我の意識が乏しいのは事実です。しかし住居表示が日本式と西欧式で違うのは、単に遠心的か求心的かということであって、どちらかを先にするしかないんだから、こんなふうに理屈をつけるのは、どうも話がおかしいと思う。
もっとおかしいのは、西洋にドゴール空港とかケネディ空港がある。日本の空港はみんな地名で、たとえば千利久空港なんてのはない。これは空港の名前によって「個人の尊厳と存在」を裏づける西洋風の考えと反対のものである、といっているわけです。
しかし、人名より地名を空港につけるのは、能率を重んじるからでしょう。日本人にとって飛行機は能率性の象徴であることを第一に表現している。第二に、その飛行機を地霊によって祝福したいという古代的心理がいまも日本では生きている。古代的なものと現代的なものがうまく融合しているのが日本の空港だ――という理屈だってつけられないことはない。少なくともこの理屈のほうが、芦原さんの理屈よりは少しうまくできている。(笑)
木村 うーん、いろんな理屈があるもんだなあ。(笑)
山崎 私も、芦原さんに敬意を表するがゆえに、いささか勇み足を修正したいと思います。われわれは建築や都市の構造を論じると、それをすぐ世界観、人間観に結びつけたがるんですね。それは健全な学問的衝動ではありますが、常に警戒が必要です。
たとえば床の建築は壁の建築と歴然と違いますが、これはそのまま日本対西洋の違いではなく、日本と他の東洋世界との違いでもあるんですね。中国の建築は壁の建築であり、その都市は城壁に囲まれて、まさに整然とした中心を持つ合理的都市ですけれど、唐も明も清も、専制絶対権力の世界で、およそ個人主義とは縁もゆかりもない。だから、都市に一つの中心があって一元的世界観をもっているということと、個人主義の成立とは重ならない。
それに西洋の場合も、そういう中心をもった一元的都市というのは、古代ローマとナポレオン以降の近代都市なんですね。その中間は、中世の町でも、ルネサンスの町でも、必ずしもそうではない。たとえばフィレンツェのドーム、あのお寺を全体として眺めようとしても、近くまでぎっしり家が建っていて、統一的に展望できる場所はどこにもない。西洋の都市は地図に書いてみると、なるほど中心をもった合理的構造をしているけれど、それを目で確かめる場所は意外にないんですね。
丸谷 そうねえ。ロンドンなんて、きみの言うとおりだね。
山崎 ロンドン、ボストンといった、港に沿ってできた街は、中心がなくて蠢(うごめ)いている。これは世界共通なんですね。
だから西洋の都市は中心があり、日本の都市は中心がない、とは簡単にいえない。これは芦原さんがいけないんじゃなく、ロラン・バルトがいけない。(笑)
丸谷 あ、賛成だねえ。
山崎 西洋人の思想家には、西洋文明について観念的にしか知らない人が多すぎる。それが東京を見たりして新鮮な感じをうけると、もっともらしいことを言う。
丸谷 しかも日本に一週間くらいしかいなくて何か言うわけでしょう。大体、態度が不真面目だよ。(笑)
木村 芦原さんがヨーロッパという場合、十九世紀以降の近代ヨーロッパを考えていらっしゃると思うんです。個人主義が徹底したのは十九世紀以降で、だからこそ通りの名に人名がつくんですね。つまり近代ヨーロッパは世界史のなかでただひとつ、個人が前面に出て緊張的に全力投球し、市民が共感抜きの共存の形式を作り出したときですね。そこから、やはり芦原さんの言われるように、人名、地番を先にした住居表示も生まれるし、都市美も生まれると思います。にもかかわらず、中世の町でもカテドラルが都市の中心にあることは間違いなくて……。
山崎 それは観念的な中心でしょう。
木村 いや、必ずしもそうではなく、地面からはおっしゃるようにカテドラルが見えない場合でも、上に上がれば都市が全部見えるわけです。客観化という度合からすると、近代ほどではないんですけれど、やはり中心は中心です。
遠くから町を見ますと、たとえばシャルトルの町が典型ですが、まずカテドラルが見え、近寄るとほかの家並みが見えてくる。それはカテドラルと同じ高さの建築を許さなかったからです。今でもパリが六、七階になっているのは、ノートル・ダム寺院より高い建物を建てることを許さなかったからですね。
山崎 それを言うなら、日本でも大体の城下町で天守閣は見えたに違いない。その程度の中心性は日本にもあった。
木村 なるほど。でも町を囲む城壁がなく、荻生徂徠が『政談』で述べているように、江戸は北は千住から南は品川まで野放図に家が建ってしまう。木戸を設けてここから内が江戸、外は田舎とせよと徂徠は提言するのですが、結局今日までしまりがありません。島国にあるロンドンがやはり雑然として、よく似ています。
丸谷 無限に膨張していくから、中心が埋没しがちになるということは、日本の場合いえますね。でも、芦原さんがおっしゃるほど話ははっきりしていないと私も思う。
山崎 芦原さんは、建築とそれを取りまく空間――道路や広場などを、ゲシュタルト心理学の「図」と「地」という概念で考えることが有効だとおっしゃっている。そこに光栄にも私の著書が引用されているわけですが、私自身は「地」と「図」というより、その中間の世界が、肝要な問題になっていると思います。具体的にいえば縁側とか露路、回廊といったものですね。フィレンツェの回廊を分析して芦原さんは、〈建物の外側を街並みの内側と考えるとき、よりよい都市空間の創造へとみちびかれる〉とおっしゃっている。まったく同感です。それだけに「図」と「地」の対立ではなく、その統一をもっと論じてほしかったという気がいたします。
木村 新地域主義(ネオリージョナリズム)ということを芦原さんは提唱されています。地域の風土や歴史に根ざした人間味あふれる建築が、この高度工業化社会では望ましいというわけですね。その考えはまさに「地」と「図」の統一だと思います。実は来年(昭和六十年)筑波で開かれる科学万博の基本テーマ「人間・居住・環境と科学技術」というのも、同じ発想だと思うんですね。科学技術は普遍的なものですが、アフリカはアフリカで、日本は日本で自然条件も歴史も違う。科学技術を土地ごとにキメ細かく適用することでどうしたら最適の環境を作れるかというのが、本来の趣旨だったはずです。それが忘れられて、ロボットとかエレクトロニクスだけが騒がれているのは遺憾です。それはともかく芦原さんの本は、近代主義と美的感覚、そして風土性がみごとに融け合っていて、これからの美しい都市づくりに最良のテキストですね。
山崎 いまの日本の都市を美しくするためにやるべきことは、実は小さなことなんです。日本は変な国でして、公と私をわけますと、どちらもうまくいってるんです。世界のどこにくらべても企業はうまく回転しているし、国家の治安は保たれている、大抵の国に比べて離婚率は低いし、不良児も少ない。さて、どこがいけないかというと、公と私の中間がいけない。おしめを窓の外に干して平然としている。インテリアショップはあるがエクステリアショップは一軒もない。猫の額ほどの庭を汚いコンクリート・ブロックで囲む。人が見るのはそのブロック塀だけです。そういうことはわりに具体的な小さな知恵で解決できるということを、芦原さんはいくつも例をあげて主張しています。日本の都市を考えるとき、やたら大きな文明論を引っぱり出して、悲憤慷慨して何もしないというのは、いささか情けないと思っていましたので、この本には教えられました。
丸谷 西洋人はよくアパートの外側のところに花を飾る、と書いてありますね。これなんかはまさに「図」と「地」の中間だと思うんです。それで考えてみますと、花は飾りはしなかったけれども、日本でも昔の家は、黒板塀に見越しの松……。
山崎 それはお妾さんの家でしょ。(笑)
丸谷 まあまあ。ぼくの関心のある部分を強調しているわけで……。(笑)その見越しの松なんてのも「図」と「地」の中間のところとして都市美に貢献していたわけです。
一般に、明治維新以前の日本には、西洋の都市美と共通するものがかなりあったと思うんです。ところが妙な形で西洋がドッと進入してきて、日本的な美意識はもうダメだとみんなが思ったとたん、普遍的な美意識も失ってしまった。それが最も極端になったのが、大戦以後からついこのあいだまでの日本の都市美であった。それがここのところで少しずつ反省が出されているような気がするんですね。その反省をもう一つ深めたり進めたりするためにこの本は大変役に立つ。いろいろ批判はしましたが、しかしこれはいい本です。(笑)
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする