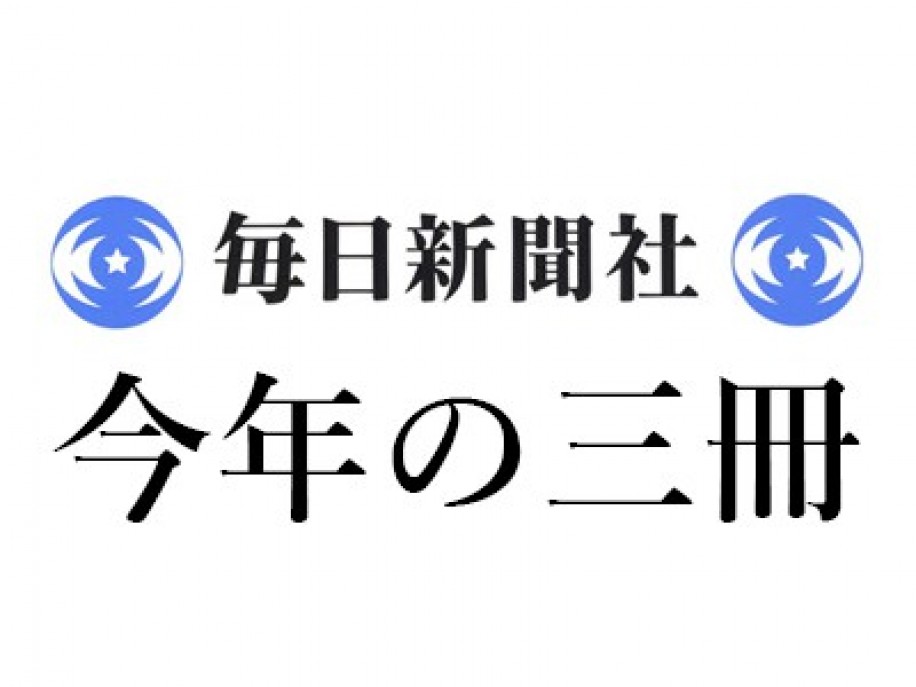対談・鼎談
長谷川 幸延『大阪芸人かたぎ』(読売新聞社)|丸谷 才一+木村 尚三郎+山崎 正和の読書鼎談
山崎 これは、長谷川幸延さんの最後の小説集となった本です。これを取りあげたのは、この本が二つの意味で、ある時代の終わりを記念する性格をもっているということです。
まず第一には、よき時代の大阪あるいは大阪文化、先代の鴈治郎と初代の春団治と通天閣によって象徴される大阪、そういう世界が失われたということは、いまの大阪の人にとっては共通の意識でして、挽歌というような気持をこめて、これを長谷川さんがお書きになっていることがよくわかります。ですから、小説とはいうものの、かなりの程度に実録として読める面がありまして、特に各作品のうしろに付け加えられている後記の部分になかなかおもしろいエピソードが秘められております。
もう一つの意味でこれが記念碑だというのは、いわゆる「大衆文学」というものの一種の挽歌であるという感じがします。良きにつけ悪しきにつけ、いまは言葉さえなくなった「大衆文学」の最後の作家の一人が長谷川幸延さんだろうと思います。その方が亡くなったということは、そういうジャンルを生かしていた時代が終わりになったということを感じさせるわけです。
わたくしのいうカッコ付きの「大衆文学」というのは、いわば型のある物語といいますか、昔の歌舞伎役者が見得を切っているような型がありまして、そこのところが、性格の描写とか、時代背景の説明などよりも遙かにおもしろい。そういう型のある文学と、かつての大阪という、いわば型のある生活の世界とが、うまく重なっていまして、それがこの作品にわれわれの感慨を一層深くする要素をもたらしているんじゃないかと思います。
まず、失われた大阪ですけれども、確かに先代鴈治郎の芸がなくなり、初代春団治の芸がなくなったということが、直接の問題であるわけですけれども、それと同時に、わたくしなぞ特に大阪へ移住してきた人間の目から見て、大阪というのは都市文化そのものを失ったんだなあ、という気がします。
たとえば道頓堀にカフェー・ド・パノンという店があったというのですが、これが、いまあるような俗臭フンプンたる道頓堀ではなくて、趣きのある川に面して、芝居茶屋の並んだ軒並みに、三角のランタンをかかげ、薄桃色の壁にビアズレーの版画をかけるといった雰囲気で、東京のカフェー・プランタンを思わせた。そこへ大阪の文化人、芸能人が集まるのですが、ここでたいへん有名だったのが五色の酒といいまして、比重の違う洋酒を同じ杯に注ぎまして、赤、緑、白、黄、茶が層をなしているのを飲む。いかにも大正文化の軽薄な側面を代表しているような飲みものですけど、東京では、パンの会(明治末期の耽美主義的な文芸運動。美術の石井柏亭、森田恆友、山本鼎、文学の木下杢太郎、北原白秋らが創立期の中心人物)の連中が喜んで飲んでいたんですね。当然、狭い日本ですから、東京と大阪に同じものがあったのでしょうけれども、いい意味でも悪い意味でも華やいだ精神の状況が、当時は東にも西にもあった。
一方、もう一つの世界、すなわち、型のある文学の世界と申しましたけれども、これを読んでいると、いかにも新派の舞台に登場してきたり、あるいは新作落語の世界にそのまま出てきそうな物語がいろいろとあります。
中村梅玉が終戦直後、東京で芝居をやって、たまたま停電になった。足もとのおぼつかない役者がどうするだろう、何秒経っても電灯がつかない。と、当時、お客たちは夜道を帰るために懐中電灯をもっていて、みんなでその懐中電灯を面明りのようにつけて役者を助けた。梅玉の目に涙が浮かんでいた。
これなんかも、ちょっといまの小説家がまずは書かないエピソードですが、いかにも型になっています。
全編こういう筆致で書き進められているんですが、おもしろいことに、その筆致は、素材が新しくなってくると思わしくなくて、たとえば沢正の場面とか、あるいはアチャコのお話などになると、若干違和感が残ります。ですから、まさにこういうものの見方自体が、その世界とともに去っていったのだな、という一抹の感慨を残した次第です。
丸谷 芸の話のときはいいんだけれど、芸術の話になるとダメですね。
山崎 おっしゃるとおりです。
丸谷 芸術という概念の安っぽさにはイヤになりました。沢正だって、松井須磨子だって、いくらなんでも、これほどひどくはないと思う。沢正や、松井須磨子程度の知性すら作者はもってないという感じがしてしまうんです。これでは大阪に歌舞伎役者がいなくなるのも当り前だという感じですね。東京の歌舞伎が何とか生命力をもってきたのは、芸という概念だけに寄りすがらないで、芸術という概念をカンフル注射みたいに打ちながら、もちこたえてきたからだと思うんです。
それが典型的なのは、左団次がやった岡本綺堂の芝居で、特に『修禅寺物語』なんか、芸術という概念がなければ、話がもともと成立しないようなものでしょう。あの芸術という概念がはたしてどれだけ高級なものか疑わしいのだけど、まあ芥川龍之介の『地獄変』の芸術という概念も、ほぼあれに近いですよね。でもそれを取り入れることで東京の歌舞伎は何とか時代に適合していった。
山崎 たしかに、この中に出てくる当代鴈治郎の青春期の話で、何かわかるような気がしますね。
この人は「中ぼん」という雑誌をファン一同で作って新作歌舞伎に熱中した人で、子供の頃は、「日本少年」に投稿してメダルをもらうのが愉しみで、という文学青年でしょう。わざわざ自分の後援会をお茶屋でやらないで、カフェー・ド・パノンでやるわけです。そういう姿勢が、東京では軽薄は軽薄なりにある種の果実を生んだのだと思うんですけど、関西では、まさにこの鴈治郎が芝居の世界から飛び出して映画のほうへ行かざるを得なかったという現実に、どこかで繋がっているのだろうと思いますよ。
木村 わたし思いましたのは、一行ないし二行程度の会話がずうっと続いていて、ちょっと見の印象は非常に通俗的に見えたんですけど、読んでみると、なかなか惹きこまれるものがあるんですね。その中で、大阪のゼニ勘定のがめつさと美しさが一緒になっていて、いわばそういった大阪の美というものがだんだん滅んでいくのを非常に惜しんでいる姿が、ここによく出ているように思うんですね。
そういう意味では、春団治の話も梅玉の話もいいんですけど、二代目春団治の話――。二代目としての厳しさ、淋しさ、結局グレて、最後は病院で死ぬわけですが、ああいうところにかえって、わたしは惹かれるものがありますね。
二代目は初代と違うんだということを小畑という人が説教しているところがあります。先代の芸をのみこんで、それを時代に合わして吐き出していく蚕みたいなものが芸人だ、といって諭すわけです。これはいつの時代にも通じることですが、しかし、初代に偉い人がいると結局、看板の重みに耐えられない、その苦しさと淋しさみたいなものが、ここに非常によく出ているような気がして、わたしはたいへん惹かれたところです。
丸谷 第二のポイントの「大衆文学」が問題なんですけど、さっきの芸と芸術の話に、また戻っちゃうんですよ。長谷川幸延の沢正と抱月の出会いと別れとのところを読むと、芸術というものの格をむやみに上げていて、通俗というものをむやみにおとしめている、その把握のしかたが、さながら小島政二郎氏の態度によく似ている。
山崎 なるほど(笑)。
丸谷 小島氏は、自分が『人妻椿』を書いたということを、やたらに卑下するわけです。わたしは芸術小説を――芸術小説って言葉は普通の小説家は使わないんだけど――書きたいのに牧逸馬みたいな通俗小説を書けといわれた。
しかし、わたしはそこを頑張って、せめて菊池寛程度にして書いたら、それっきり通俗小説作家にされてしまった、というんです。で、ときどき彼は思い立って、芸術小説なるものを書くわけです。ところが書くべきことは何にもないんだなあ。あれだったらむしろ『人妻椿』のほうが、ずっと自慢になると思うけどねえ。
山崎 そうね。長谷川幸延さんの場合には、一方では、術抜きの芸の世界というものに対する、非常に確たる信念があると思うんです。で、そういうものがすでに滅びてしまったものだ、という哀しみもあるんですね。これと小島政二郎を足したものが大正から昭和にかけての、広義の大正文化というものだろうと思う。
丸谷 そう。つまり、小島政二郎があれだけ芸術に憧れることができたのは、やはり、芥川龍之介という先輩が、芸術に熱烈に帰依して、それに身を殉じる生き方をしたからでしょう。
ぼくはそれを、一概に笑う気はしないんです。ただ、芸術という概念の抽象性、観念性を支えるのに、芸というものがあると、何とかうまく処理できるんですね。安定する。谷崎潤一郎は、芸術に憧れていたけど、芸のほうもねらっていたから、そこのところをあっちへ行ったり、こっちへ行ったりすることで、非常にうまく具体的に文学を書くことができたと思うんです。
山崎 われわれは、ついこのあいだまで、というよりいまもなお、二重生活をしているわけでしょう。背広と浴衣とか、芸と芸術とか、義理人情と近代的自我とか、そういう二重生活をいろいろやってきて、やっとその両方を辻褄合わせて、何とかひきむしられるような思いはしなくなってきた。そういう意味で、この本はまた、典型的な二重生活をやった最後の人の記念碑かもしれませんね。
木村 でも、この方は和服着ていますね。わたしらは、洋服を着て畳に坐るでしょう。ズボンがしわになるわけですよ。これ、どうするかというと、あとで女の人が伸ばしているんです。そういう二重生活の無理を、いまのわたしたちもまだ克服できていない。その意味では和服の長谷川さんのほうが、むしろ正直に生きている(笑)。
山崎 でもやはり、幸延さんは非常な無理をしていると思うんです。彼の書いた『春団治』という芝居は、それなりの傑作だと思うんですね。それと同時に、やはり彼は五色の酒が飲みたかったんです。それを生涯もち続けて亡くなった人ですよね。
木村 春団治の話でも、女の人をたくさんこさえて、最後はこの人たちが死のベッドにみんなきて、「おい」と春団治がいったら、「はい」とみんな一緒に返事をしたとか(笑)、そういうむちゃくちゃな生活を描きながら、芸人の孤独さが、非常にリアルに出ている。そういう芸人の姿は、もういま、なくなったんじゃないでしょうか。
山崎 そうでしょうね。
丸谷 長谷川さん自身は小島政二郎みたいな気持はないのね。そこがヘンなんですねえ。芸という概念のおかげですよ。
山崎 一つは、長谷川幸延という人は、作者部屋出身ですから、彼は生々(なまなま)しく昔の芸の一端に触れていて、一方で、いまの鴈治郎と芸術青年に憧れるという体験をしていますから、ズブ小説家育ちの小島さんとは違うんじゃないでしょうか。
丸谷 そうね。ところが芸術にいっぺん酔ってみたいという気持はかなりある。だから沢正の悲劇にうっとりするわけですよ。
山崎 この人は臆面もなく二重生活をした人だと思います。そしてその二重生活というのは、じつは、大阪の一つの体質ですね。たとえば東京では舶来に対立する土着の側のアクが強くない。それにひきかえ大阪というのは、初代春団治にせよ二代目にせよ、殊更に臭い。先代延若がいうように、「臭い芝居」のできる役者だけが、その悪口をいってみろ、というような風土がある。そこヘカフェー・ド・パノンが入ってくるわけですから、この懸隔は非常に大きかったと思うんです。
丸谷 困るだろうなあ(笑)。
山崎 日本の近代文化がもっていた矛盾を極大まで拡大して体験して、とうとう股が裂けてしまった文化かもしれませんね。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする