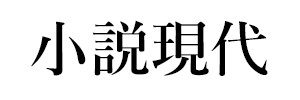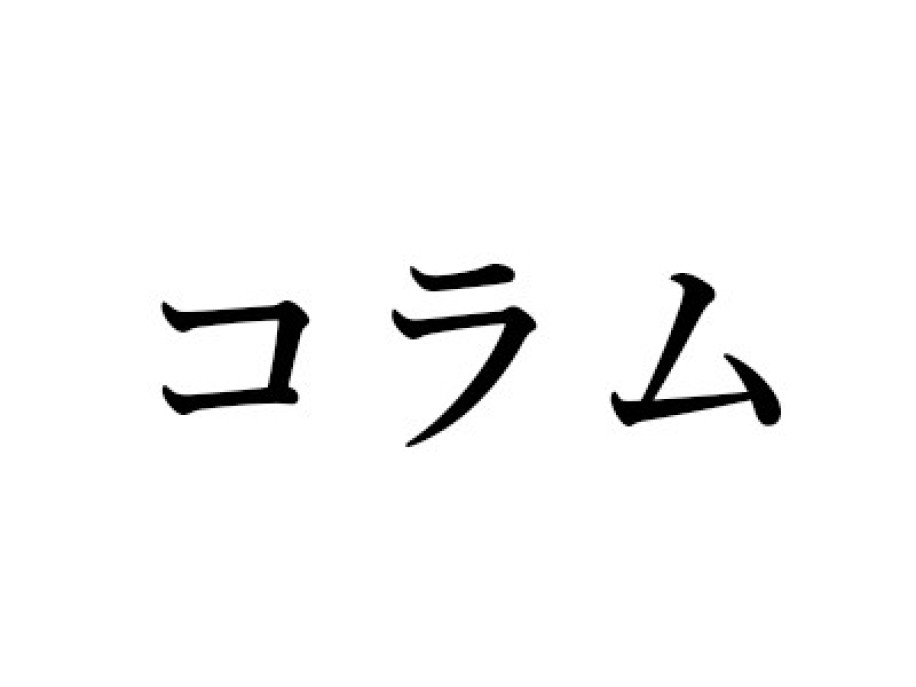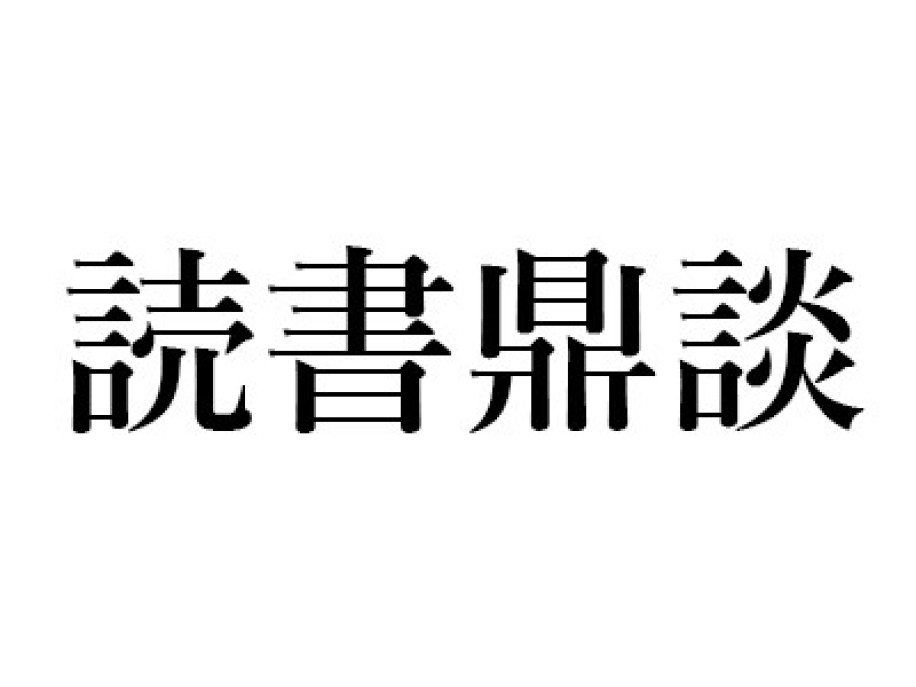コラム
エリザベス・キューブラー・ロス『死ぬ瞬間』(中央公論新社)、岩井寛・松岡正剛『生と死の境界線』(講談社)、柳田邦男『「死の医学」への序章』(新潮社)
病とともに生きる
がんは日本人の死因の上位を占めるだけあって、私のまわりでも患う人がときどき出る。家族ぐるみの付き合いをしている男性は、五十歳の夏に発病、医師から「年内もつかどうかでしょうなあ」と言われたそうだ。地方から出てきて、小さな会社をつくった頑張り屋。
いつでも元気で、彼あるところに笑いあり、といったタイプだったが、一時はさすがにがっくりときていた。
が、そこは経営者、従業員や会社の今後を考え、
「私亡き後も、ひとつよろしく」
と挨拶回りをはじめ、
「えらいもんだ」
「冗談ばかり言ってたけど、あんなたいした人だったかね」
と周囲を唸らせたのである。保険にはやたら入っていたので、妻子についてお金の心配がなかっただけでも、心が少しは軽かったかもしれない。
末期患者へのインタビューに基づく、E・キューブラー・ロス著、川口正吉訳『死ぬ瞬間 死にゆく人々との対話』(読売新聞社)は、がん宣告を受け死に至るまでの心理的プロセスを、五段階に分けている。否認、怒り、取り引き、抑鬱、そして受容。
本が書かれたアメリカとは背景を異にする日本で、どれだけその通りに進むかはわからないが、秋に、一時退院した彼を家に訪ねたときは、少なくとも「怒り」はもう過ぎていた。お茶をいれる奥さんを、
「いいよな、お前は未来があって」
とからかう彼には、がんになる前の笑いをとる話し方が戻っていた。
彼によれば、大部屋に入れられたのが、救いになった。実は彼は神経がこまかく、人に気をつかう方なので、はじめはいやでたまらなかった。が、しだいに変わっていった。
同室の十二人の男たちに共通するのは、がん患者という点のみ。若い医師もいた、酒屋のご用聞きもいた。大企業の役員だったという老人は誰かれ構わず威張り散らし、何とか組のヤクザは、看護師の口のきき方に腹を立て、点滴のチューブをつけたまま、ハサミを握って、ナースステーションにどなり込んだりした。
昼間はそんなふうでも、夜、消灯時間を過ぎてまっ暗になると、布団をかぶりすすり泣く声が、どこからともなく聞こえてくる。部屋に満ちる嗚咽の中にいると、
「人間、病気になれば、社会的地位も何もない。皆、同じだ」
と深いところで感じるものがあったそうだ。
ある日、彼はベッドの上で水虫の薬を塗っていた。ふととなりを見ると、酒屋の若造が、頭に毛生え薬をかけているのと、目が合った。
「なんだって、ムダな努力を。何か月かで死ぬってのに、髪なんか生やしたところでしようがねえだろ」
「そっちだって、同じでしょ」
健康な人に言われたら、家族だって我慢ならないそんな言葉も、自然に交わすことができたという。
「見て、これ全部、見舞いの人が持ってきた本」
私に、足もとのダンボール箱を指さした。闘病記をはじめ、「私が励まされた言葉」「生かされて生きる」「真の知恵」といった類のもの。
「お気持ちはありがたいけど、そういうのばかりだと、やんなっちゃう。がんになったからって突然、悟りを開くわけじゃなし」
そりゃそうだと、思わず声を立てて笑ったのだった。
【文庫本(改版)】 【単行本(新版)】 【単行本】
私がこれまで読んだがん患者による本で、強く印象に残っているのは、岩井寛、松岡正剛による『生と死の境界線』(講談社)。精神医学者である岩井が、全身をがんに冒され、五十五歳で亡くなるまでの数か月、松岡を対話者に選び、語り続けた。「心」の専門家が、刻々と死に向かいつつある自分の内面を凝視した、類まれな本だ。
発病以来、岩井はこの本の前に三冊を口述筆記により著している。三冊めの『森田療法』(講談社現代新書)を口述中は、すでに目が見えず、片耳も聞こえず、下半身がまったく動かなくなっていた。
いつ言葉が奪われるか、いつ脳細胞が破壊されるかわからない、それでも「最後まで人間として意味を求めながら生きたい」から口述を続けるのだと、『森田療法』のあとがきに述べている。身体の機能をひとつひとつ失っていく中で、人間はどこまで「自由」であり得るかを、極限の形で追究した、他に例のない実験の書といえるだろう。
医者を志す前、美学を学んだ岩井だけあって、松岡との話は哲学、宗教、日本文化論と広範囲にわたる。語り手、聞き手ともにレベルが高いので、はじめのうちは、
「えっと、この語は、教養課程の授業で出てきた覚えがあるけど、なんだったっけな」
といちいち考えなければならず、ついていくのがたいへんだった。
それが、五章のうちの四章めあたりから、岩井の一回あたりの話が長く続けられなくなるに至って、
「あっ、いよいよ臨終に向かっていくんだ、この本を読み終るとは、すなわち、ひとりの人の死に立ち会うことなんだ」
と、そのことの重みが、どっと胸に迫ってきた。後は、まるで病の進行に追い立てられるように、聞き手もろとも加速度的に最終ページへとなだれ込んでいったのである。
「すごい本を読んでしまった」
しばらくは呆然としていた。自分はその任に耐え得る者かと、常に問いつつ、死にゆく者の言葉を、全人間性をかけて受け止め続けた松岡にも、尊敬の念を抱いた。
柳田邦男著『「死の医学」への序章』(新潮文庫)は、やはり精神科医で、四十八歳で自らががんにかかったことを知った西川喜作の生き方を中心に、クオリティ・オブ・ライフへの取り組みを書いた本だ。西川による闘病記、『輝やけ 我が命の日々よ』(新潮社)も出版されている。
西川が、月刊誌で柳田の『ガン 50人の勇気』(文春文庫)を読み、手紙を書いたことから、二人の交流ははじまった。強がりを言わない率直な人がらが、柳田をひきつけたようだ。それは、文章のはしばしから、わかる。
柳田のすすめで、闘病記の出版が具体的になるにつれ、西川は心配する。「少しも売れなくて、しょげかえるだろうか」。逆に「世間に知られ、ジャーナリスティックにもてはやされてしまう時、自らを毅然と律することができるかどうか」。
死に直面したからといって、聖人君子になれるわけではなく、俗っぽい心配もすれば、弱みもみせる。愛すべき「ふつうの人」がそこにいる。シリアスなテーマなのに、ほっとするものが流れているのは、そのせいか。
夏に「年内もつかどうか」と言われた知人は、正月を妻とハワイで過ごし、春を迎えてもなお、一家、一事業所の主として、子どもたちや従業員が自分の言うとおりやっているかどうか、しっかと睨みをきかせている。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする