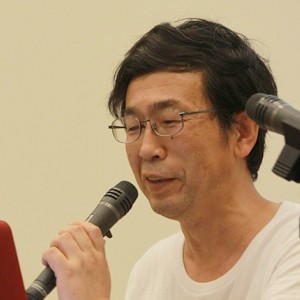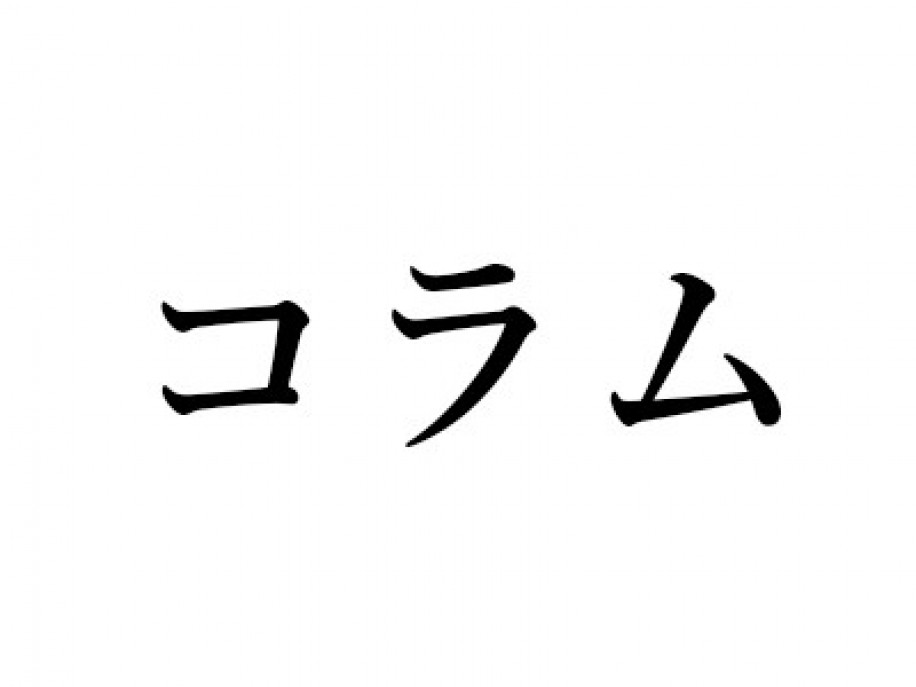コラム
松岡 正剛『世界のほうがおもしろすぎた ゴースト・イン・ザ・ブックス』(晶文社)、松岡 正剛『百書繚乱 松岡正剛のヴィジュアルブックガイド』(アルテスパブリッシング)
「編集工学」を説く先にある日本文化論
一九七〇年代に伝説的な雑誌『遊』の編集長として知られるようになり、その後は自らが提唱した「編集工学」の研究所所長を務め、二〇〇〇年からはウェブ上で「千夜千冊」の連載を行うなど、多方面にわたって活躍した松岡正剛は、ロングインタビュー『世界のほうがおもしろすぎた』の中に出てくる話によれば、「たぶん好奇心の天才なんだろうと思う」と雑談で自分自身を語ったことがあったという。まさしくそのとおりで、タブロイド新聞「SANKEIEXPRESS」に連載されていた「BOOKWARE」を編集しなおした『百書繚乱』を眺めていると、持ち前の好奇心を発揮してカバーしている領域のとんでもない広さに圧倒されるばかりだが、強く印象づけられるのは、ネーミングの天才だなあということだ。「本にまつわる多様な関係世界のいっさい」を「ブックウェア」と言い定めるセンスの良さ。そもそも、松岡正剛の出発点となった「工作舎」も、当時に流通するようになった「ワークショップ」という言葉の意訳だし、編集という営為をエンジニアリングに見立てた「編集工学」ももちろん造語だし、すでにわたしたちが日常的に目にするようになった「ジャパネスク」も、元はと言えば、「方法としての日本」を追求した彼が、八〇年代に日本様式を表す言葉として名付けたものだった。
造語の才能というものは、それまでになかったものを生み出す力に他ならない。それは既存の理路整然とした体系からははみだしていく。松岡正剛が工作舎時代に出したなかで、おそらく最も有名な本であるレオ・レオーニの『平行植物』は、架空の植物の生態を学術的な体裁で記述したものだったが、そのレオーニとの対談本『間(MA)の本』では、想像力が実在するものではなく実在しないものへと向かうことが語られている。アナロジーや連想からつながった、松岡正剛本人の言葉を借りれば「フラジャイル」な、もろいもの、はかないものである。しかし、われわれの頭の中にある、多方向に広がった知識は、本来ノンリニアなものだというのが彼の捉え方であり、「イメージを組み合わせて動かしてみる」そのプロセスをシステム化するのが編集工学の基本的な方向だった。「あらゆるメディアアートにちょっかいを出し」た葛飾北斎を取り上げて、彼はこう言う。「ぼくが思うに、真にクリエイティブな仕事とは、世の中に新たな『見本』を提案することだ」
「間」あるいはあわいの領域への関心から、松岡正剛の思考と文章が最も精彩にあふれているのが日本文化を論じたものなのは、不思議でもなんでもない。蕪村が牡丹(ぼたん)を詠んだ句から説き起こして、「思索と仕事と表現のあいだに、科学やアートやコンピュータのあいだに、『寂(せき)』や『絶間(たえま)』や『おもかげ』がのこるようにしたい」と書くのは松岡正剛の真骨頂とも言えるもので、方法としての日本文化を模索した彼の思考は、とかく「日本を巨大化してしまう」昨今のナショナリズムとは大きく異なっていたのだ。
ALL REVIEWSをフォローする