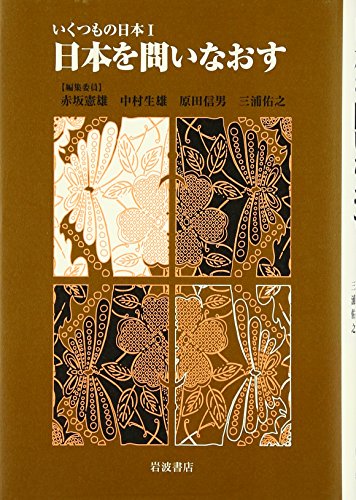書評
『わたしの城下町』(筑摩書房)
なぜ城は現在まで生き延びてきたのか
「お城」という響きには特別なものがある。かつての城下町に住んでいる人々にとって、懐かしくも憩いの場という雰囲気があるようだ。かくいう私もお城の側に育って、花見に、虫取りにと、お城は小さい頃の絶好の遊び場だったのである。そんな特別な思いが、人々のなかにどう育ち、そのための城再建への取り組みがどう行われたのか、探ったのが『わたしの城下町』である。日本美術史を専攻する著者が、江戸城(皇居)に始まって、各地にある名城、迷城、ホンモノ、ニセモノなど様々な城をめぐる風景などから、そこにかかわった人々の思いや活動を掬(すく)いあげている。著者は浜松城の近くに育った。
副題に「天守閣からみえる戦後の日本」とあり、その始まりが皇居のお濠端の第一生命館に陣取ったGHQの本部であることからうかがえるように、戦後史を探る試みでもある。からくりなどの見せ物、作り物などに注目してきた美術史家らしく、奇手、妙手などいろいろな小技を繰り出し、城を求め、天守閣を求める様々な人間模様を浮かびあがらせている楽しい読み物となっている。
たとえば皇居を考える際に周辺の銅像のなかでも特に裸像に目をつけたり、小田原城を考えるにあたっては、小田原駅前の小便小僧像から探ったりという趣向である。城と城下町の特質を考えるために、その近くにあるモニュメントとの関係や対比を上手に利用しながら分析を加えてゆく。その小気味よい叙述運びが絶妙である。
取り上げられた城は、前記のほか、熱海城、下田城、駿府城、掛川城、長岡城、名古屋城、松代城、伊勢神宮、清洲城、墨俣城、彦根城、伏見城、大阪城、尼崎城、姫路城、洲本城、広島城、福岡城、高松城、熊本城、佐賀城、首里城などだが、どれだけ読者は見、知っていますか。
考えてみるに、城は戦国時代に特に発達をみた軍事施設であったが、やがて城を中心とした町づくりが行われるようになり、統治と同時に町のシンボルとなっていった。明治維新とともに軍事的な意味を消すべく城が壊されたり、払い下げもあったが、奇跡的に残されたり、潰(つぶ)されてもやがて新たな都市の形成にあたって様々な意味が込められ、城の再建が行われてきたのであった。
そこからは城や天守閣を求めて城づくりにあたった人々の、悲しくも切ない喜劇がすけて見えてくるのだが、読んで浮かんできたのが「人は石垣、人は城」と語ったといわれる甲斐の戦国大名の武田信玄である。まさに「人は城」である。
天守閣(天主閣)を本格的に築いた織田信長によって滅ぼされた武田氏については、県史編纂(へんさん)により文書が網羅的に集められ、『甲陽軍鑑』などの書物の研究も進み、テレビドラマによって何度も取り上げられたこともあって、多くの知見が明らかにされつつある。著名な信玄の画像はどうも信玄のものではなさそうだということも。
そうしたなかで著された『武田信玄と勝頼』は、副題に「文書にみる戦国大名の実像」とあるように、信玄と勝頼が発給した文書を徹底的に読むことを通じて、その実像を明らかにしたものである。文献をきっちり読むことを通じて、そこから歴史像を構築しようという文献中心の歴史家らしい本となっていて、先の美術史家の本とは対照的な作りとなっている。
戦国大名の書状をいかに読むのかという基本的な問題に全体の六割近くが割かれており、大名文書入門の趣があるが、それを通じてしだいに信玄の人となりに近づいてゆき、やがて「信玄とはこんな男」の第四章で、信玄の性格や人間関係について読みとり、最後に戦国大名として歩んだ道、天下取りを目指す道(?)を跡づけてゆく。
新書の体裁のため文書の写真が小さいのは難点だが、多くの真偽不明な史料に基づいて行われている研究のなかにあって、文書を精緻(せいち)に読みとろうとした努力は貴重で、文書を読む面白さを堪能させてくれ、新知見にも満ちている。
ただ信玄をめぐる人間関係の分析で、教雅という僧に関して「そういう身分の者が、仕返しのために調伏を企てたり、それを平気で語ったりするのは、あまりにも生臭過ぎるように思う」と評価するのは、やや甘過ぎないか。
しかしそれはさて、信玄は大きな城を造らなかったが、近くに織豊政権大名によって甲府城が造られた。そこに今、天守閣を設けようという運動がおこっている。町おこしのシンボルとして天守閣は欲しいものらしい。
ALL REVIEWSをフォローする