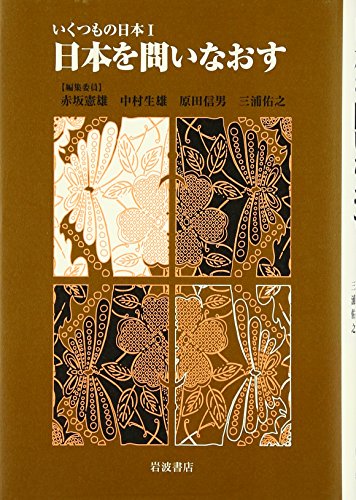書評
『ゴードン・スミスの見た明治の日本 日露戦争と大和魂』(KADOKAWA/角川学芸出版)
外国人の目に映った、日本の国民性と信仰
大英博物館の標本採集員であるゴードン・スミスが初めて日本を訪れたのは明治三十一年(一八九八)のことであった。その後、数度の帰国を経て神戸で亡くなるが、その日記には、今はもう失われた明治の日本の姿が記されている。伊井の著書は、この日記を読み解いたものである。スミスは博物学者として新種の魚類や動植物を求めて標本を集めるかたわら、各地に赴いて見聞したことなどを日記に書きとめ、またその風景を絵師に描かせたが、この絵や手紙、新聞の切り抜きなどもこまめに日記に貼(は)り付けていた。なかで特に目立つ記事が日露戦争の記事である。
そこで著者は、スミスがこの戦争に何を考え、どう行動したのかを中心に探っている。スミスの祖国イギリスは日本と日英同盟を結んでおり、傍観者たりえなかった。時にイギリスは同盟国なのにそれにふさわしい動きをしないと歯ぎしりしたりする日本びいきとなっていた。
スミスは日本人の国民性として従順さやモラルの強さを見、戦争での勇猛さに「大和魂」「武士道」の精神を見いだして絶賛するようになったが、それにいたる心の動きや、日露戦争後には帰還した傷病兵のために多額の寄付をするなど積極的に活動していった背景を紹介している。
本は手際よくまとめられており、戦争当事国に住む外国人の心の動きもよく浮かんでくる。さらにスミスの日記の全体像を知りたい、という思いに駆られる本となっている。
ところでこの本の冒頭は、京の石清水八幡に集う群衆の叙述から始まるが、八幡神は武の神であって、日露戦争の開戦になると、多くの人がここに祈りにやってきたのである。その日本の神々に興味を抱き、それらの性格を探ったのが、ドイツ人宣教師ゲオルク・シュールハンマーである。
彼はフランシスコ・ザビエルの伝記を書くことを誓い、その足跡をたどり、また十六・十七世紀に日本に渡ったイエズス会の宣教師たちの報告を探し出して読むなかで、『神道』を一九二三年に出版したが、その翻訳が『イエズス会宣教師が見た日本の神々』である。
日本の神話に始まって、神々とそれを祀(まつ)る社、菅原道真・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康など歴史上の人物が神として祀られた例や自然崇拝の様相、さらにはミカドの崇拝のあり方、礼拝の仕方などにいたるまで、宣教師の数多くの報告を丹念に読みこんでまとめている。
日本の文献には見られない記述が多くあり、戦国時代に神々を宣教師がどう捉えていたのか、実に興味深いものとなっている。著者自身が同じ宣教師だけに、宣教師の立場から何に興味を抱いていたのかもうかがえて関心をそそる。
なかでも神のように崇拝された動物、たとえば狐(きつね)・猿・鹿・蛇・亀・牛・兎(うさぎ)・鼠(ねずみ)などや、自然の木や山などの崇拝について説明している部分、また日光の東照宮について詳しく記して賞賛している部分などは特に目をひく。ミカドについて「本来は高位の神官であり、民衆の名前で一定の礼拝行動をしているにすぎない」と指摘しているのも印象的である。
翻訳は、訳注が本文のなかにあって、時々原注なのかと間違いそうになる問題点はあるものの、「あとがき」を読むと、本書の翻訳に注がれた訳者の情熱に脱帽する。
ALL REVIEWSをフォローする