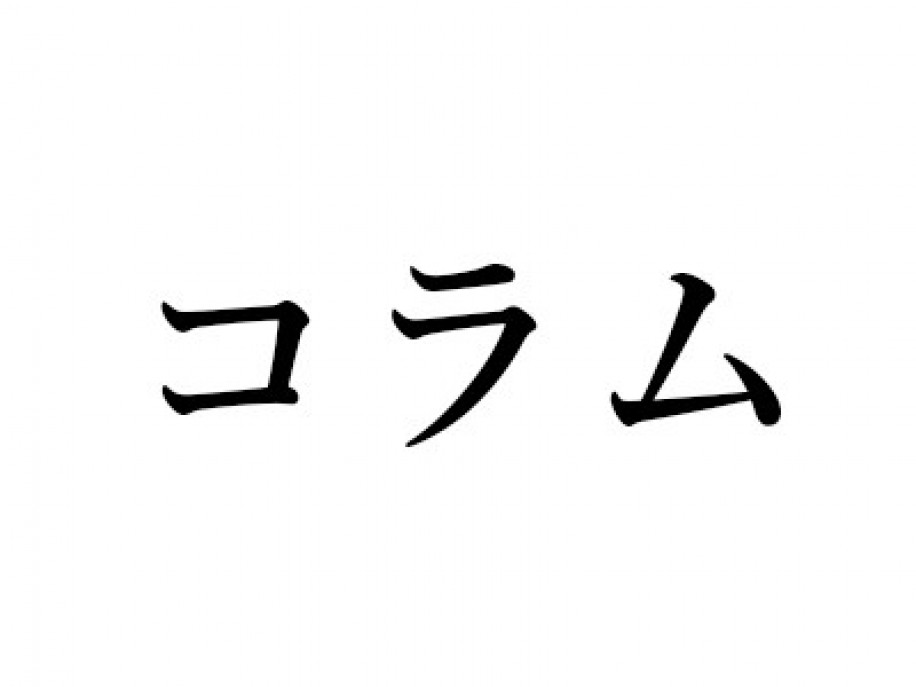書評
『新古今集 後鳥羽院と定家の時代』(KADOKAWA/角川学芸出版)
帝王と歌人が火花を散らした黄金期
帝王を中心として和歌の文化が絢爛(けんらん)として花開いた時代。『新古今(和歌)集』の撰集(せんしゅう)されたこの時代は、しばしば新古今時代と称されるが、この時代を本書は見事に活写している。何よりも後鳥羽院と藤原定家という君主と歌人との取り合わせから描いているところが秀逸である。この時代を描こうとすると、どちらかに比重を置きたくなる。特に後鳥羽院は自らが主催して和歌の試験を行い、廷臣たちが行ってきた影供歌合(えいぐうたあわせ)や百首歌の歌合、詩歌合などを積極的に取り入れ主催する、まさに歌の帝王だったから、後鳥羽院に焦点をあわせるのが普通である。
しかし著者はそうはせずに、二人の強烈な個性の衝突に目をこらす。そのために『新古今集』撰集の時期の二人の交流ばかりでなく、承久の乱により隠岐に流された後鳥羽院と京にあった定家の二人の動きを対比しており、そのことによって新古今時代がどのような時代であったのかが鮮明に浮かびあがってくる。
もちろん、二人だけに目がゆくのではなく、後鳥羽院の歌壇からはじかれ、去っていった鴨長明や源顕兼(あきかね)などの人々の行方にも注目する。院には、歌の体(てい)を愚弄する目的で、古い歌詠みを集めて歌合を行わせるなど過酷な面があったのだ。また目をかけられて登用された俊成卿女(しゅんぜいきょうじょ)や宮内卿(くないきょう)などの女房歌人たちの動きにもしっかりと目を向ける。院は、女性の歌詠みを積極的に評価する傾向があった。これらにより、単に和歌だけでなく、時代の文化の広がりが明らかにされている。
この時代を探ってゆくためには、文学と歴史学の二つの学問分野を横断する視野の広さと分析の鋭さがなくてはかなわないのだが、著者は和歌文学の研究者であることから、『新古今集』がいつ完成したのかといった重要な指摘をはじめ、歌合や和歌集、歌論書の分析はもちろんお手のものだが、さらに書状などの文書や定家の日記『明月記(めいげつき)』からその心の内実を明らかにするなど、歴史的な分析もまた冴えている。
しかも和歌の細かいところの解釈にこだわって、読む人を飽きさせるようなことはしないし、日記の解釈にこだわって、読む人を辟易(へきえき)させることもない。文章がきびきびしていて、読者を次々と新たな世界にいざなってくれる。そう考えるならば、こうしたことがさらに知りたいと思っていると、次にそのことが触れられている。まことに読んでいて飽きさせないのである。
本書は全部で十二章からなる。最初の三章で『新古今集』が生まれてくるまで、次の三章でその撰集の時期の動きをあつかっている。さらに続く三章において、撰集以後の文化の傾向を探り、最後の三章では、承久の乱後の後鳥羽院と定家の動向を見つめる、という綺麗(きれい)な四部構成になっており、全体が過不足なく論じられ、その点でもよくできている。
もう少し触れてほしい、と思ったのは、後鳥羽院と定家の交流が始まる前の時期であろうか。というのも読むうちにどうしてこのような激烈な精神の持ち主と、強固な魂とが生まれてきたのかと思ったからである。もちろん、それは後進が考えるべきことであろうが。
いい本は、時々著者の分身のような人物がそのなかに登場するものだが、本書からは俊成卿女がそのように見えてくるというのは読みすぎであろうか。激しい個性の衝突を見つつ、毅然(きぜん)とした生き方をしたのが俊成卿女であった。
ALL REVIEWSをフォローする