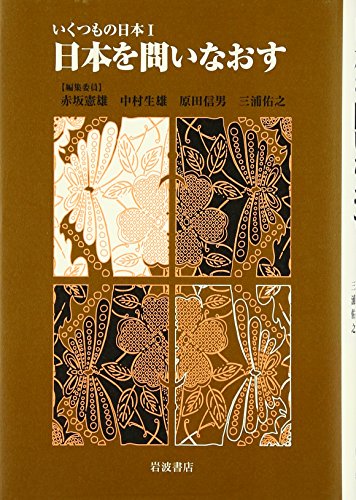書評
『いくつもの日本 1』(岩波書店)
「単一神話」の不自然さと根深さ
日本論や日本人論は社会の転換期になるといつも現われる。自画像がゆれ動き、新たな自画像をつくろうという試みが始まるからであろう。本書もそうした動きのなかのシリーズと理解されようか。その際、日本を単一のものとして捉えるのでなく、「いくつもの日本」と銘打っているごとく、多層性、多様性、複雑系として把握する。近代になって国民国家を形成するなかで、日本は単一のものであることが自明のこととされ、学問もそれを無意識のうちに前提として進められてきた経緯がある。したがって今、「いくつもの日本」を考えるためには、それぞれの学問分野での自己検証が大事になってくる。歴史学・民俗学・人類学・考古学・地理学・言語学といった分野において、それぞれに問いなおす試みが必要となる。
本書はそうした各分野からの報告からなるもので、まず民俗学の赤坂憲雄が柳田國男の民俗学に顕著な「一国民俗学」の方向性を批判して、折口信夫や岡正雄の論考や発言などを吟味しつつ、「いくつもの日本」を掘り起こす作業のあり方を論じて本シリーズの立場を表明している。
次に多様性の発見という点から、人類学の埴原恒彦が、科学的に検証可能な仮説として、縄文人と渡来系弥生人とからなる「二重構造」の人類史を提唱するとともに、それにはおさまらぬ地域的多様性を探る。
考古学の藤本強は、「北の文化」「中の文化」「南の文化」という列島の三つの文化を想定し、さらにその北と中の間、中と南の間にもそれらともやや異なる「ボカシの地域」があるとして、そのあり方を探る。
さらに民俗学の野本寛一は、列島の各地の植生と民俗との関わりに注目して、特に落葉樹林帯や広葉樹林帯との関連から多様性を指摘する。
続いて、境界の地に視点をおいて探る試みからは、まず考古学の工藤雅樹が藤本のいう「北の文化」である蝦夷とアイヌの問題を考え、同じく考古学の安里進が「南の文化」の琉球文化圏について考察し、地理学の出口晶子が丸木舟と筏(いかだ)舟の分布や構造のあり方から、東アジアの交流の様相を多角的に探る。
こうした考察を見ると、日本が単一であるという考え自体の不自然さがくっきりと浮かび上がってくる。よくよく見ると実に多様性にあふれており列島の豊かさは多様性にあることを実感する。
しかし日常に戻ると、多くの人は再び単一性の枠組みにとらわれてゆくのである。そこにこの問題の難しさがあろう。単一神話から抜け出すのはなかなか厄介なことである。
人は一度思い込むと、その思考の枠組みから容易に抜け出せない。したがって研究者もこの問題に立ち向かうには、柔軟な学際的協力とともに、違った学問領域からの主張や成果についてはそれをきちんと検証して使う態度が望まれよう。自分の学問領域ではそう考えていなくとも、時流に乗った主張にのまれてしまうことはよくある。
そうした意味から、最後の、近代の学問研究のあり方の検証に基づいて、日本思想史の中村生雄が指摘する国民国家論における陥穽(かんせい)や、言語学のイ・ヨンスクが指摘する日本人論における陥穽、また歴史学の菊池勇夫の指摘する、東北史という地域史の提唱に含まれる陥穽などは、重要な問題提起である。研究においては一字一句や微細なモノ、傷痕なども見逃さない研究者が自らの思考の枠組みに不注意なままでは困る。
「いくつもの日本」が一つの日本にからめ取られることなく、どう展開してゆくのか楽しみにしたい。
ALL REVIEWSをフォローする