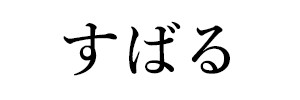作家論/作家紹介
沢村 貞子『わたしの献立日記』(中央公論新社)、『貝のうた』 (河出書房新社)、『老いの道づれ』(筑摩書房)、山崎 洋子『沢村貞子という人』(新潮社)、他
四日間の空白――沢村貞子の日記文学
鳥追い女のような編笠(あみがさ)をかぶせられた私はしんと静まりかえった廊下を、奥へ奥へとみちびかれた。きこえるのは、あけしめする錠のキンと高い音と、自分の藁草履(わらぞうり)のペタペタという低い音だけである。〈お取り締まりさん〉と呼ばれる五十ぐらいの女看守の草履の裏はフェルトらしい。足音はほとんどきこえない。それに、笠の下からそっと見ると、しのび足の癖がある。 (『貝のうた』)
衿(えり)に縫いつけた白木綿に、墨文字で一三五番。二十三歳の「私」は昭和七年、治安維持法違反容疑の思想犯として独房に収監された。いったん釈放されたが公判闘争を経て地下へもぐり、ふたたび逮捕。獄中生活は通算一年八カ月におよんだ。
およそ五十年後。そのひとが七十代のとき書いたエッセイは、こんな書きだしではじまっている。
あさ、床の中で眼をさまして、一番さきに私の頭に浮かぶのは、今日の夕飯は何にしようかしら……ということである。
雨戸の隙間(すきま)から、明るい陽の光が洩(も)れていれば、久しぶりでちらしずしはどうだろう、と思い、うす暗くシトシトと雨の音がきこえれば、おでんの煮込みでもこしらえようか……などとうつらうつらと思い迷うのも、また楽しい。 (『わたしの台所』)
わずかな数行が、焙(あぶ)りだしのように軌跡を浮かび上がらせている。前半生、冷えのきつい独房で食べるアルミの食器入りの麦飯と切り干しだいこんの煮つけ。後半生、床のなかで思い描く夕餉(ゆうげ)のちらしずし、あたたかなおでん。振幅のおおきい食卓のあいだに横たわる半世紀五十年の歳月のなか、脇役女優として、随筆家として、生一本(きいっぽん)に生きた人生がある。しかも、後半生二十六年のあいだには膨大な献立記録が遺(のこ)されており、世にふたつとない日記文学の体をあらわしている。
その六冊め、昭和四十五年七月にとつぜん現れる四日間の空白に八十七年の生涯を雄弁にものがたる鍵(かぎ)があったことは、のちほどゆっくりと書くことにしたい。
沢村貞子(さわむらさだこ)、明治四十一年東京浅草生まれ。座付き狂言作者だった父、竹柴傳蔵(たけしばでんぞう)は、四人兄弟の次女として貞子が生まれたとき「チェッ、女か」。なにしろ父の悲願は「自分の子どもはみんな役者にする」で、執念通り兄と弟は役者になり、兄はのちの四代目澤村國太郎、弟は加東大介。母、マツは、玄人の女たちにちやほやされて浮気三昧(ざんまい)、しかし芝居のことしか眼中にない父に滅私奉公し、それこそ身を粉にしてひたすら尽くした。
そのひととなりを読み解くうえで重要な一冊が『貝のうた』である。この処女作には、生まれ育ちから終戦までの前半生が綴られてくわしい。六歳ごろから“お貞(てい)ちゃん”は長唄(ながうた)や踊りの稽古(けいこ)に通いはじめ、家では母から家事をきびしく仕込まれたから尋常小学校一年ですでにひとりで夕飯のしたくをこなしていた。大正十年、浅草七軒町東京府立第一高等女学校入学。家庭教師をして月謝と本代を稼ぎながら、昭和元年、教師の夢を抱いて日本女子大学師範家政学部に入学。二十歳のとき教師への夢を断ち、築地(つきじ)小劇場の女優、山本安英(やまもとやすえ)に「新劇の女優になりたい」と手紙を送って女優の道へ足を踏みだす。兄はちょうど若手女形として人気がでて映画界へ引き抜かれ、弟も真剣に役者に取り組もうと決意を固めた時期だった。ところが、入った新築地劇団で左翼思想に近づき、大学を自主退学。思想運動の一翼をになうつもりで運動仲間と結婚したのは、世間知らずの二十二のときだった。しかし結婚半年め、築地小劇場入口で逮捕、収監。
『貝のうた』から垣間見えるのは、潔癖、努力家、几帳面(きちょうめん)、生真面目(きまじめ)、一本気。下町の女の性分といってしまえばそれまでだが、下町気質とだけでは括(くく)れない個としての特質をかんじる。なぜなら、これらの特質こそ、のちの二十六年に亘(わた)る献立日記の礎石だから。じっさい、終戦間近のもどかしい胸のうちを自身でこう書いている。
私が可愛げのない女だということは、自分でもわかっている。理屈っぼくて潔癖で……自分にも人にもきびしすぎて……。でも、もし、私の地貝(じがい)にめぐりあえれば、そのときこそ、私は、女らしい女になれるような気がする。素直でやさしく、可愛い女に……。私の白く固く冷たい心のすぐ下に、うすく色づいた弾力のあるやわらかい心があることを、私は自分で感じている。 (『貝のうた』)
「地貝」とは、出貝(だしがい)と対(つい)をなす貝の半身のこと。結婚も離婚も経験したのにいまだ恋は知らず、仲間を守るために獄中で口をつぐんで耐えたが夫にも同志にもあっさり裏切られた。もはや誰も信じられなくなっていたけれど、それでも、終戦があらたな光明をもたらしてくれはしないかと、三十代後半の自分を鼓舞したのである。そう遠くないうち、恋しい「地貝」にめぐり会える予感があったのだろうか。
じっさい生涯の伴侶(はんりょ)と出逢ったのは終戦直後、昭和二十年のことだ。國太郎、大介とともに京都座で芝居を打っていたとき取材のために楽屋を訪ねてきた新聞記者、大橋恭彦(おおはしやすひこ)とのあいだに恋愛感情が生まれた。そして、駆け落ち。大橋恭彦は新聞社を辞職、妻子を置いて家をでた。沢村貞子は当時二度目の結婚をしていたが、すでに別居状態だった。ふたり身を潜めるようにして東京の経堂(きょうどう)で暮らしはじめるのだが、正式に夫婦となるのはそれから二十二年六カ月後の昭和四十三年、沢村貞子が六十歳のときである。大橋恭彦がゆずり受けた「映画芸術」の赤字補填(ほてん)、長年離婚を承諾しなかった大橋の妻への毎月の仕送り、住宅費、生活費……経済のすべてを背負ったのは沢村貞子である。だから、撮影所をいくつも掛け持ちして懸命に働く必要があった。それを支えるマネージャー、山崎洋子(やまざきようこ)の働きぶりもたいへんなもので、「かけもちのやりくりで、毎月、二足の靴を履きつぶした」と、のちに述懐している。テレビや映画で名脇役としてしきりに顔をだした背後には、そのような家庭の事情が隠れていたのだった。
稼ぎはすべて沢村貞子に頼っていたが、家のなかで大橋恭彦は「殿(との)」だった。じっさいにも「殿」と呼んでいたというから、気の遣いようにおどろいてしまう。しかも、そのあつかいにはずいぶん苦労したと『老いの道づれ』『老いの楽しみ』などに率直に書いている。
いつも、玄関に置く二人のサンダルも――あなたのものは、キチンと、真中にそろえておかないと「履きにくい」と、眉(まゆ)をひそめる人だったから――洗面所の、あなたの手拭(てぬぐい)も、かならず、上座(かみざ)……引き戸をあけてすぐのところにかけておくように、気をつかったものです。
とにかく几帳面で潔癖で、とても情にもろいところがあるくせに、恰好(かっこう)の悪いことは大嫌いな、かなり頑固なスタイリストのあなたは、うちの中では、けっこう、威張っていたということ。そして私は、いつでも何でも……できるだけ、あなたの気持に添うように気をつけていましたから、まずまず、天下泰平ということでした。 (『老いの道づれ』)
「殿」は女優の仕事にも口を出した。泊まりの仕事は御法度(ごはっと)、どんなにやりたい役柄でも「殿」の許可が下りなければ、ツルのひとこえで泣く泣く断った。さすがにマネージャーの山崎洋子の目にも傍若無人に映ったが、しかし、当の本人にとっては人目などどうでもよかった。だれがどういおうと、自分との恋を成就するために家庭も仕事もいっさいを捨てた男なのだ。その一点に、どんなことをしても報いるという決意と覚悟があった。それは、仲間を裏切るまいと獄中でいっさい無言で通した一年八カ月の潔癖、一本気にも通じる律義さと似ている。
昭和三十二年以来、公私ともに約四十年の交流があった山崎洋子が著す『沢村貞子という人』に、こんなくだりがある。
よく、
「決めたことだからね」と言ったが、
決めたことがよほど難儀なことであっても、よくよく考えての「決めたこと」だから変更はない。
決めたことだから。背後のない一語のうえに、「沢村貞子という人」がすっくと屹立(きつりつ)している。そもそも「決めたこと」という言葉には、あらかじめ複雑な感情がたっぷりふくまれている。決意するまえにさんざん逡巡(しゅんじゅん)して、苦しんで、足掻(あが)いて、そののち歯を食いしばりながらようやく選びだした言葉。だからこそ、自分を律する覚悟がみっしりと、ある。そこで、わたしは思いいたる。「決めたこと」は、沢村貞子にとって、自分の心張り棒を手放さないための知恵ではなかったか。つまり、逡巡がもたらす苦しみや悪足掻きを遠ざけ、潔く生きたいと願うときのよすが。いったん決めたと思ってしまえば、ほかの選択は脳裏に浮かべなくてすむ。その意味で営々二十六年、三十六冊の献立日記は「決めたこと」のかたちなのだった。
献立日記をもとにして編んだ『わたしの献立日記』をはじめて手にとったのは、たしか二十代のときだった。それより以前、わたしも十八歳から数年間、大学ノートに献立日記をつけていた。親もとを離れて暮らしはじめた気負い、おぼつかなさ、解放感、うれしさを日々の食べたものに託して書きつけた数年間があったからこそ、この本を親身にかんじた。そもそも『わたしの献立日記』には、他人の目を意識するようすがまったくない。ごはん、汁、おかず。淡々とつづく食卓の記録を読むうち、励まされるような、安心するような、なぐさめられるような、または目くばせしたり、にこっと笑いかけられたり、日常から洩れつたわってくる息遣いにじかに触れる読みごたえを、わたしは受け取っていた。
第一冊め、書き初めは昭和四十一年四月二十二日、五十七歳のとき。せりふで頭がいっぱいの朝、毎日の買い物を頼んでいる通いのお手伝いさんに「奥さん、今日のお献立は?」と聞かれてぐっと詰まり、そうだメモがわりに献立日記を書いておけば便利だと思いついたという。
4/22(金)
牛肉バタ焼き
そら豆白ソースあえ
小松菜・かまぼこの煮びたし
わかめの味噌汁(みそしる)
翌朝、四月二十三日は、前日の夕食の献立を見ながら決めた。
4/23(土)
豆ご飯
いわし丸干し
かまぼこ
春菊のおひたし
大根千切りの味噌汁
ごくふつうの飾り気のないおかずが、ひたすら季節に寄り添いながら進む。春の「グリーンピースご飯」「ふき、厚揚げ煮つけ」「新わかめの茶碗(ちゃわん)むし」、初夏の「アスパラゆで物」、真夏の「焼きなすのとろろかけ」「セロリ、揚げ玉の味噌汁」「枝豆塩ゆで」、秋が深まると「栗(くり)赤飯」「里芋ととりのなすのはさみ揚げ」、師走は「鯛(たい)ちり鍋(なべ)」「シチュー」「大根のかす汁」「湯豆腐」……とくべつなものではない、どれもこれも日本人の食卓になじみぶかい、ほっと落ち着く味ばかり。ただし、ごはん、おかず、汁の取り合わせ、つまり献立にこまやかな配慮と工夫が見てとれる。おいしく食べたい、楽しく食べてもらいたいという気遣いが洩れつたわってき、質素で始末のいい台所のようすも目に見えるようだ。ただし、自分流の「ぜいたく」は惜しまなかった。
ほんとに――ほかに道楽はない。住むところはこぎれいなら結構。着るものはこざっぱりしていれば、それで満足。貴金属に興味はないから指輪ははめないし、貯金通帳の0を数える趣味もない。いわば、ごく普通のつましい暮らしをしている。ただ――食物だけは、多少ぜいたくをさせてもらっている。 (『わたしの献立日記』)
その「ぜいたく」とは、たとえば出入りの魚屋から旬の魚を買うこと。とびきり新鮮なものを選んで、刺身にしたりてんぷらにしたり。朝餉夕餉のささやかなよろこびを「ぜいたく」として享受した。相手のよろこぶ顔を見れば、自分もうれしい。外食を嫌い、おなじ料理が食卓につづけて並ぶのをこのまない「殿」のための備忘録でもあった。プライベートな時間をともにすることも多かった山崎洋子の文章が、素顔をいきいきと伝えている。
食事がととのうと、たすき、またはかっぽう着をはずし、首にかけた手ぬぐいで、ぐいと汗をぬぐいながら、
「さっ、たべましょっ」と叫ぶ。
箸(はし)をとると、さながら猛禽類(もうきんるい)が獲物にとびつくごとくで、何故(なぜ)かこの時、目が真ん中に寄るのであった。一口ほうりこむと、
「む、んまい」
と言い、それからこっちを向いて、
「んまいよぉ、食べてごらん」と言う。
かたわらの大橋さんは、箸の先を一センチ程汚しながら、黒豆を一つぶずつ口にはこんでいるのであった。 (『沢村貞子という人』)
いま山崎さんは、東京西麻布で秋田の郷土料理の店「鹿角(かづの)」を経営している。開店は平成五年、八十一歳の沢村貞子が女優業を引退して四年後である。西麻布の路地をはいったところに暖簾を掲げる「鹿角」は、秋田の山菜やきりたんぽ鍋をだす小体な店で、食材に神経が行き届き、すっきりと洗練された味わいが小気味いい。「いらっしゃいませ」とあたたかく出迎えてくださった女主人は、白髪をさらりと結い、濃紺の紬(つむぎ)の着物に身を包んでいた。
「やっぱりね、稀有なひとでした」
開口一番の言葉である。
「できますか、ふつう。二十六年間毎日ですよ。朝出かけるとき、その日の献立のメモをお手伝いさんに渡して出かけ、毎晩それを自分で清書するんです。ただ、仕事で夜遅くなるときもあって、ときどき『溜めちゃったわ』と言うのを聞いたこともあります。でも、止(や)めなかった。つくる料理はね、これはもう見かけからしておいしそうなの。外で食べないのに、なぜこんなすてきに盛りつけられるのか、つねづね不思議に思っていました。沢村さんは、料理をつくるとき、いつでも全身全霊でした」
三十六冊の直筆の献立日記や終生愛用した裁縫箱などをたいせつに保管しているのは、山崎さんである。この日、ぶしつけを承知で献立日記を拝見したいと申しでると、「沢村さんを知っていただくためなら」と、快く預からせてくださった。
その三十六冊が、いま目のまえにある。大学ノートに一冊ずつ、すべての表紙にぐるりと芹沢銈介(せりざわけいすけ)のカレンダーの一枚が貼りつけてある。手触りのよいやわらかな風合いの和紙。表紙の右脇にブルーのマジックで「昭和四十一年四月~四十二年一月」。左脇には鋏(はさみ)でちいさく切った長方形の和紙を貼り、おなじく手書きで「壱(いち)」。自分でこれと決めた手づくりの意匠だ。
一冊ずつ手にとってめくりながら丹念に献立を追う。すると、料理の羅列の奥のほうから微妙な変化がつたわってきた。当初書き入れたのは夕食だけ、翌年の二冊めから朝食も記しはじめ、縦の罫線(けいせん)が一本増えて日付、夕食、朝食の順番に三つの欄ができたのは三冊めから。昼はかるいものをこのみ、「おやつ」と呼び慣わして朝食の欄に書き添えている。昭和四十年代は料理の本もおおいに参考にしたようで、「かにのピラフ(おそうざい外国37頁(ページ))」、「すずきのサンゼルマン(フランス71頁)」などとメモ代わりの書きこみがある。けっして欠かさなかったのは朝のサラダ、夜の味噌汁。食卓のととのえかたに、自分の流儀が一本通っている。
「拾七(じゅうなな)」巻、昭和五十四年一月。
1月23日 (火)
ぶりとひらめのおさしみ がんもどきの煮つけ しらすときゅうりの酢のもの みそ汁(大根 千六本、ゆず)
朝
バターロール レタス きゅうり セロリー ピーマン なし りんご バナナ ブロッコリー むしやきたまご
おやつ
あずき おもち
いっぽう「参拾(さんじゅう)」巻、ちょうど九年後のおなじ日。
1月23日 (土) 曇のち晴(12℃)
かんぱちのおさしみ たこと赤貝の酢のもの 焼さつまあげの大根おろしそえ おみおつけ(春菊 油あげ)
朝
食パン 牛乳 ハムエッグ ピーマン サラダ菜 バナナ いちご りんご
おやつ
クッキー 紅茶
味噌汁を「おみおつけ」と記すようになったのは、昭和五十七年五月三十一日からである。繰りまわしの工夫はみごとなもので、出入りの魚屋から鯛一尾を買うと、当日は刺身や「しほやき」、そののち煮付け、うしお汁。「ぜいたく」をしても、両足はきっちり庶民の暮らしに根ざして離れることがない。正月元旦、自分でこしらえたおせちの欄を特別に赤いボールペンで囲んでいるのも、こころなごむ。
削ぎ落とした事実の連なりには真実の重みがあり、巻を追うほどリアルに迫りくる。はっとして目を見開いた箇所が、あった。第「六」巻、「昭和四十五年一月十三日~十月まで」の夕食の欄。
7月13日 月
(主人旅行中)くさやの干物 つくだ煮
7月14日 火
(主人旅行中)たらこのやきもの くさや
7月15日 水 (旦那様(だんなさま)旅行中) 外食
7月16日 木 旅行
ぽっかり空欄の四日間。三十六冊中たったいちどだけ、献立日記が緩んでいた。そののち最後まで、このような空欄はどこにも見つからない。わたしは四つの空欄をじっと凝視した。文字は記されてはいないが、とてもたくさんのことが書かれている空白だったから。
いったんつづけると「決めたこと」、それは、ともに生きると「決めたひと」が傍らにいてこその日記なのだった。だからこそ、「旦那様旅行中」では意味を欠く。もちろん食べることは日常の楽しみではあったけれど、きっとそれ以上に、誠心誠意の報いなのだった。自分との生活を選ぶために家庭も仕事もいっさいを捨て去った、そのひとに向けての。だから、食卓は、ふたりの生活を守り通すための盾であり矢なのだった。周囲の雑音などどこ吹く風、「殿」と呼んでとことん気遣うのは、無理をしているのでも自分に厳しさを課しているわけでもない。沢村貞子にとって、それこそが「いったん決めたこと」にたいする自然な身の律しかた、愛情の流儀にほかならなかった。つまり、身をもって恋を終生つらぬいた。
でも、ちゃっかりくさやを焼く愛嬌がある。「殿」はくさやが大嫌い。それを、留守中に二日つづけて、ひとりで食べている。じつは同じ年の二月十三日、「旦那様外食」のとき、機を逃さずくさやの干物を焼いているのだが、たぶんこのとき味をしめちゃったのだ。このときとばかり取りだしたくさやを焼いて齧り、肩をすくめてほくほくしているおきゃんな仕草が目に浮かぶ。
「殿」は「殿」で、そのような沢村貞子というひとを万事承知して、悠然と「殿」の大座布団にのっかってみせたのだろう。余人が分け入る隙のない関係である。
思い起こす本がいくつか、あった。一冊は映画監督、新藤兼人が妻である女優、乙羽信子(おとわのぶこ)への愛惜を綴った『愛妻記』。日常生活でも「乙羽さん」「センセイ」と呼び合ったふたりが結婚したのは、新藤兼人が離婚した七年のち、二十七年めだった。『愛妻記』には余命一年あまりと宣告された妻との日々が描かれるのだが、さらに新藤兼人は病気を告知しないまま妻主演の映画「午後の遺言状」を撮ろうと決意、撮影に挑んで完成させ、壮絶な関係をつらぬく。関係を全うする意味を、あとに残された当時八十代の老監督がしずかに問いかけてくる一冊である。
二冊めは昭和の大ベストセラー、田宮虎彦(たみやとらひこ)・田宮千代『愛のかたみ』。昭和三十二年四月一日初版発行、同年八月の奥付には「五十六版発行」とあるから、すさまじい人気ぶりがうかがえる。田宮虎彦は明治四十四年生まれ、『足摺岬(あしずりみさき)』『絵本』『菊坂』『銀心中(しろがねしんじゅう)』(新藤兼人が監督して映画化されている)など人間の孤独をテーマに小説を執筆した作家である。昭和三十一年四十五歳のとき妻、千代が先立つ。亡妻への想いを身も世もなくせつせつと綴って生前の往復書簡まで収録した『愛のかたみ』は、発売されるや世間の耳目を集めたが、いっぽう、なりふり構わぬ悲嘆ぶりに批判も集まった。その先鋒(せんぽう)が文芸評論家、平野謙(ひらのけん)による「誰かが言わねばならぬ――『愛のかたみ』批判――」(「群像」昭和三十二年十月号)。筆致は容赦なし。「こういう特殊な、不自然な、變態的な書物が、なにか普遍的な、正常な、純愛ふうの物語として、世にうけいれられているらしい事實に、黙つていられぬ氣がしてきたのである」。平野謙は筆の勢いに乗せ、田宮虎彦は妻の死がもたらす一種の解放感から目をそむけている、時間の流れのとどまった夫婦関係は人間的な限界のあらわれ、とまで書いたから田宮虎彦の厭世観をいっそう煽り、文壇から遠ざからせた。男が書く追慕の記には、つい気を弛(ゆる)めるとなまなましい自意識が噴出してしまい、うっかり顔をのぞかせてしまう一種の危うさがある。それこそが読みどころでもあるとわたしは思うのだが。
いっぽう、田辺聖子『残花亭日暦』には、容赦のない現実を受け容れて生きる気丈な精神にこころ打たれる。夫「カモカのおっちゃん」の介護と看護、多忙な作家稼業に忙殺される日記の現実感、日常感が、ぎゃくに別れの哀切をつよく滲ませる。「カモカのおっちゃん」といっしょになってとつぜん四人の子持ちになり、つねに「臨戦態勢の非常時」の人生を生きてきた。刻々と近づく別れを間近にして、「彼」はひとつの言葉を口にする。それは、通い合わせたすべての情の発露、または田辺聖子との関係の収斂(しゅうれん)としてのたまもの。
〈かわいそに。
ワシは あんたの。
味方やで〉
平成二年。その前年に女優を引退した八十二歳の沢村貞子は、大橋恭彦とともに長年住み慣れた東京代々木上原の家を引き払い、生涯を終えるまでの六年間を葉山で暮らす。老後は海の見えるところで暮らしたいという一念で思い立った引っ越しだが、八十を超えてそれまでの暮らしをばっさり切り捨て、蝉(せみ)が殻を脱ぎ捨てるようにまっさらになるのだから、みごとな気概と実践というほかない。最初はさすがに惜しむようすを見せたが、腹を括ってからは一気呵成だった。食器はぜんぶ三枚だけと決め、鍋釜や包丁も半分、ベッドや家財道具はあらかたテレビ局の美術部に引き取ってもらい、着物はいまの白髪に似合うものだけ、思い切りよく処分して自分を身軽にした。
興味ぶかい対談が『老いの語らい』のなかに残っている。相手は幸田文。おなじ明治生まれ、育ちや環境はちがいこそすれ、暮らしかたそのものに自恃(じじ)の境地を持っていたふたりである。
沢村 (前略)私なんか主婦でしょう、そして女優でしょう。女優という商売は、物質的にも精神的にも、とても面倒な商売ですからねえ。そこを両方やって、それで人間らしくゆっくりした気持をもって生きようと思うと、年中捨ててなくちゃならないんですよね。毎日毎日が捨てる生活みたいな気がします。私は、いろんなことが重なっている間(あいだ)で、今、どれが一番大事かしらんと、こう思うんです。そして今一番大事なことだけするんです。そのあとでもしも時間の余裕があったら、二番目をするんです。
幸田 つまり沢村さんは、選ぶことのよくできる人なんじゃないの? 何が大切っていうことを選ぶこと、その訓練ができてるみたい。長年のしきたりで、そういうふうにおなりになったのでしょうね。
水を向けられて、「すぱっすぱっと切りかえていく」母の捨てかたに学んだと明かしている。
母マツこそ、沢村貞子のすべての著作に味わいぶかい陰影をもたらす存在である。なかでも、「暮しの手帖(てちょう)」の花森安治(はなもりやすじ)に勧められて綴った代表作『私の浅草』に活写される母のけなげさ、働きぶり。「こんにちさまに申しわけないからさ」が口ぐせで、浮気者の父に耐えながら毎日の繰りまわしに追われた。そのすがたは戦前の下町で身を粉にして生きた女たちに重なり、この一冊にほのかな哀調をも漂わせて、代表作たらしめている。それは、母はけっして報われてはいなかったという娘としての思いが、沢村貞子にあるからだ。
父と母は、一生、仲のいい夫婦にはなれずじまいだった。やっぱり、星のせいかも知れない。けれど、母は、心の底では、父に惚(ほ)れていたような気がする。 (『私の浅草』)
母の献身的な働きぶりが随所に書かれるだけに、胸を突かれる。母に学んだのは、暮らしに始末をつけてゆく思い切りのよさだけでなく、このひとと決めた相手と仲睦(なかむつ)まじく過ごしたいという切実さだったのだ。
部屋から海が眺められる念願の葉山に引っ越し、夫婦水入らず、夢のように楽しい日々を過ごしたのち、四年後の平成六年、大橋恭彦が逝去(せいきょ)。五十年をともにしたひとへの想いを『老いの道づれ』にあますところなく綴りおえて筆を擱(お)き、みずからすべての幕引きをするかのように沢村貞子が世を去るのはその二年後である。ふたりの遺骨は相模湾(さがみわん)に散骨された。
長年に亘った献立日記は、蝋燭(ろうそく)の火が消えるようにある日ふっと消えていた。最後に夕食の献立を書いたのは葉山での生活の二年め、平成四年十一月二十二日。
11月22日 (日) 晴
ひらめのうすづくり うなぎのザクザク かぼちゃの甘煮 おみおつけ(大根千六本)
数え切れないほど何度も食卓にのぼった、つくり馴れた料理ばかりである。
つぎのページをめくる。すると、もう一字一句なにも書かれてはいない。無言のうちにただ残された鉛筆書きの罫に囲まれた白い欄の連なり。なにかが崩れていた。果てていた。それまでの三十五冊ぜんぶに律義に貼られた民芸カレンダーもおもての表紙にはなく、むきだしの大学ノートのままであった。
【この作家論/作家紹介が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする