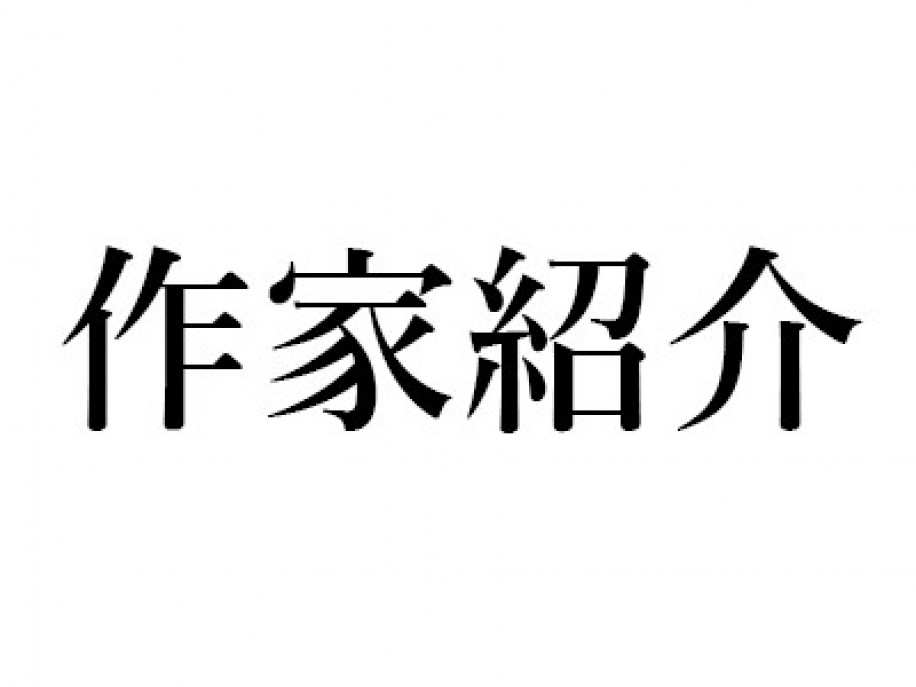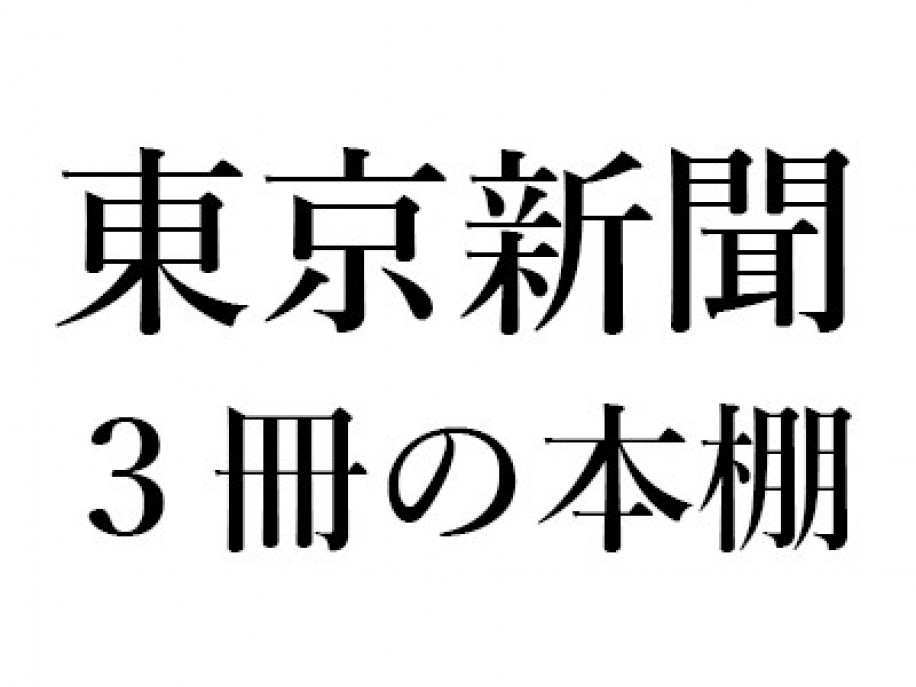書評
『床下の小人たち―小人の冒険シリーズ〈1〉』(岩波書店)
早く老人になりたい
前回、カズコ・ホーキの『ロンドンの床下』(求龍堂)をとりあげて、そのタイトルがメアリー・ノートンの『床下の小人たち』にちなんでつけられたことを書いた――のはいいのだけれど、実はその『床下の小人たち』を読んでいなかったので、家人から顰蹙(ひんしゅく)をかってしまったのだった。「メアリー・ノートンはルイスやジョージ・マクドナルドと並ぶ児童文学の古典中の古典よ。へえ、そんなの読まなくても作家になれるのお」というわけである。
まあ、作家なんて本を読まなくても務まるんだけれど、そういうほんとのことはいわずに、遅ればせながら『床下の小人たち』(林容吉訳、岩波少年文庫)を読み、いやあ面白いなあとすっかり感心したのだった。イギリスの児童文学の古典は、どれも読んでいて贅沢な気分にさせてくれる。それは作品の中に贅沢な時間が詰まっているからで、中でも、なんでもよく知っているおばあさんが登場してくると、それだけでぼくはワクワクしてくるのだ。
『床下の小人たち』も例外ではなくて、この話をしてくれるメイおばさんは「年をとっていて、節々もかたく、そして――きびしいというのとはすこしちがうのですが、そのかわりに、けっこう、しんにしっかりしたところがありました。……。そしてメイおばさんは、かぎ針編みのほかにもいろいろのことを教えてくれました。毛糸を卵型にまるくまくのは、どうやったらいいかとか、いろいろの縫いかたや、つくろいのしかた、それから、ひきだしの片づけかたや、またいれたもののうえに、つるつるしたうすい紙を一枚、おまじないのようにかけて、ほこりを防ぐ方法などを、おしえてくれました」。
こういう、児童文学の本の中で活躍しているおばあさんたちも、かつてはぼくたちの周りに実在していて、いろんなことを教えてくれたり、話をしてくれたりした。いま、その姿を見かけることが少ないのは、核家族化の進行でおばあさんの姿が隠されてしまったからだ。しかし、そんなことぐらいでへこたれるおばあさんじゃない。元気なおばあさんたちがヴェールをはねのけ一斉に外へ飛び出してくる……そんな気がするようになったのは、幸田文さんが亡くなった後、続々と新刊をヒットさせた頃から。幸田文を筆頭に野上弥生子、宇野千代、森茉莉、武田百合子、白洲正子、等々。ご存命の方とすでに鬼籍に入られた方を一緒にくくるのは申し訳ないが、こういうてだれのおばあさんたちの書いたものを読んでいると、年をとるのも悪くないと思えるばかりか、年をとった方が楽しいんじゃないかとさえ思えてくる。向田邦子が生きていればさぞや楽しいものが読めたろうとか、二十年後の金井美恵子はどんなものを書くであろうかと想像しながら、いま楽しみにしているのは沢村貞子さんである。
『老いの楽しみ』(岩波書店)には、同行二人、八十を越えた老夫婦の暮らしぶりが描かれている。ぼくの記憶違いでなければ、ついこの間、このご本に書かれたご主人はお亡くなりになったのではなかったか。もちろん、ここにはそんな不吉な予感はなく、ただ静かにエンディングに向かって着地してゆく老人の気持ちが静かに語られる。ぼくはページをめくるたびに、「早く年をとりたいなあ」と呟いたのだ。しかし、おばあさんと違って、おじいさんはあまりサマにならないことも忘れてはなるまい。高井有一も谷崎潤一郎も耕治人も、読んでいてそういう老人になりたいとは思えないものなあ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする