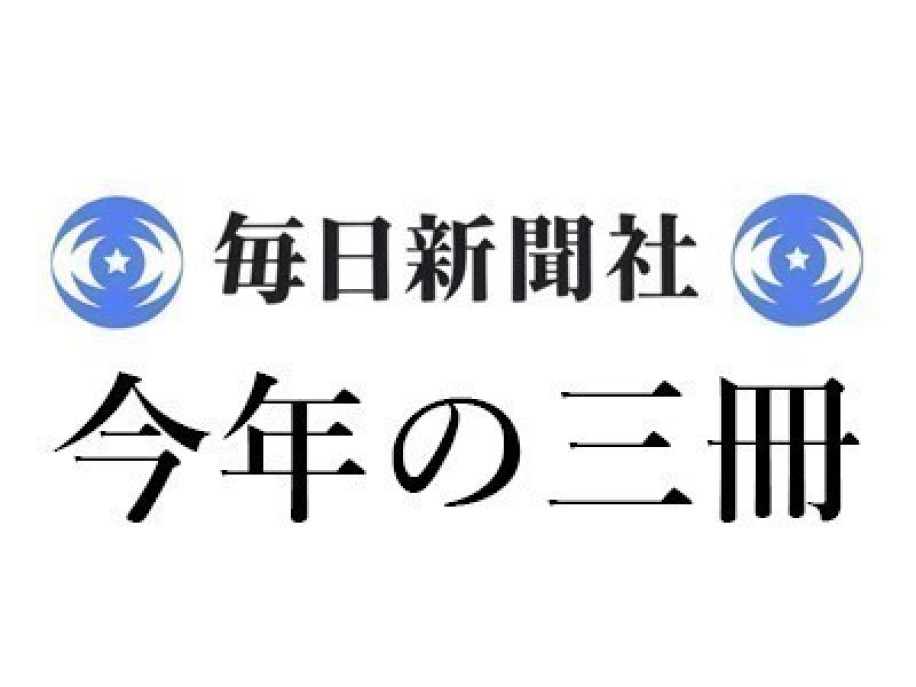書評
『0』(集英社)
世紀末の傑作、川崎徹の『0』を心して読め
こういうコラムを連載していると、まだ単行本になる前の作品をゲラの段階で読むことができる場合がある。だが、とりあえずみなさんの手に入らない本のことを書くのは失礼だから、いくら面白くてもそういう本は取り上げないようにしてきた。しかし、今回は特例である。いくらわたしでも、これほどのものを読ませられたら、黙っていられるわけがないじゃありませんか。問題の物件は川崎徹さんの中編小説集『0(ゼロ)』(集英社)である。
まず作品集のタイトルにもなっている「0(ゼロ)」の主人公「私」は数字の「0」である。元々は数字の「1」だったのだが、ある事件のせいで徐々に減ってとうとう「0」になってしまった。
だから「0(ゼロ)」は「如何にして1である私が0になってしまったのか」ということを何百枚にもわたって綴ったモノローグなのである。
次の作品のタイトルは「穴」。この作品の主人公は巨大な「穴」である。そしてその「穴」はどうして自分がそのような「穴」であるのかを徹底的に考える。「穴」はそういう小説である。
最後の作品「シバタの主人」のテーマは「時間」である。「時間」がテーマというと、プルーストの『失われた時を求めて』を思い浮かべてしまうだろうが、それではいけない。この場合の「時間」は、そういう比喩的時間ではなく、ある特定の時間、西暦××××年×月×日の×時×分で、しかもコンニャク状の固形物なのである。
「0」に「穴」に固形状の時間。いずれをとっても、小説の主人公にふさわしいとは思えない。てゆーか、そんなものを主人公にした小説が面白いのか。読む前にはわたしもそういう危惧を抱いていたのである。しかし……これがむっちゃくちゃ面白いのだ。
この作品集のテーマを使って筒井康隆ならどう書くだろう。きっと、「1」が「0」になっていくプロセスや「穴」の自己認識や、固形物としての時間について、舌なめずりするように描写を溢れさせて書くに違いない。あるいはまたカフカならどう書いただろう。たぶん、その一つ一つの作品が大きな寓意となるように象徴的に書いたのではないか。だが、川崎徹は違うのである。川崎徹はその作品のアイデアが面白いとも、そこに大きな人生の寓意があるとも思ってはいない。彼はただ、徹底的に考えてみたいと思っているだけなのだ。では何についてか。
時々穴は自分以外のことを想像した。それはさんざん自身について考え尽くして疲れた時が多かった。時間だけはたっぷりあったから、穴である自分について、それを考える自分について、そして勿論それらを思案する穴としての自分なるものと愚直に正面から向き合った。(「穴」)
すべてが現実離れした笑い話としては読めるが、リアルな体験談としては受け入れ難い。当然である。私だって他人のこんな体験を長々披露されたら恐らく最後まで聞く忍耐力はなかった。大部分の人は疲れの深さを際立たせる為の分かり易い喩え話として理解するのだろう。しかしこれは事実を大袈裟に伝えたほら話ではない。等身大の出来事である。(「0(ゼロ)」)
何を対象にしても、人間は愚直に向かい合い、徹底的に考えるのが苦手である。だから、わかりやすい比喩を好む。文学とは人生についてのわかりやすい比喩なのだ。だとするなら、川崎徹の小説は文学には似ていない。彼は、「存在」や「認識」を直接記述しようとする。へーゲルやヴィトゲンシュタインのように。そして、不思議なことに、わかりやすい比喩よりそちらの方がずっと面白いのだ!
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする