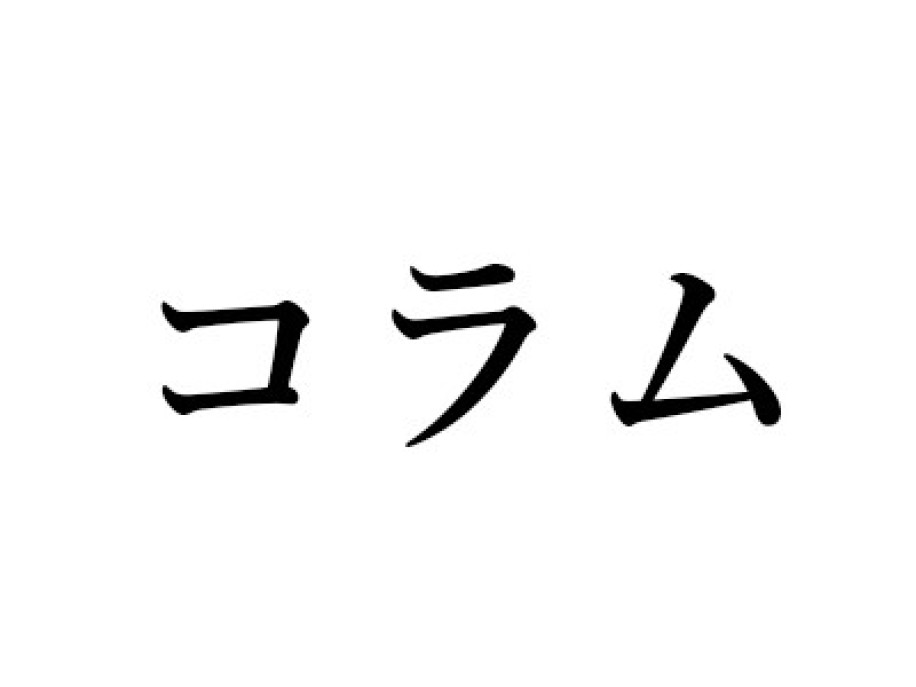書評
『死因』(講談社)
続きが読みたい!
飛行機の中で(やっと)「検屍官」シリーズ第七作の『死因』(パトリシア・コーンウェル著、相原真理子訳、講談社文庫)と、毎月「続き」が出る『グリーン・マイル』3・4(スティーヴン・キング著、白石朗訳、新潮文庫)を読んだ。『グリーン・マイル』の方の内容は……やっぱりやめとこう。一方の『死因』だが、主人公ケイ・スカーペッタは相変わらず頑張っているし、姪の天才プログラマー、ルーシーはいつの間にか二十三歳になっていて「親友」のジャネットともめ、ピート・マリーノ警部はもちろん口が悪く、FBI心理分析官のベントン・ウェズリーはいつものように渋いがとうとう離婚してしまった。要するに、「検屍官」の世界はいつものようにそこにあり、そこにある以上、川の中で知り合いの記者の死体が見つかり、その死体の発見の前に謎の電話がケイ・スカーペッタにかかってくるし、そればかりでなく同僚も非業の死をとげるのである。これで、カルト教団ニューシオニストの「聖書」が登場人物たちをこわがらせるほど十分にこわかったら文句はないのだけどただ「こわい」と書かれてもなあと途中思ったりもするがコーンウェルはキングじゃないし、とにかくそんなことを気にする間もなく話はどんどん進んでいって結末に到達し、後は第八作を待てばいいのだった。実際、読者はなぜ「続き」を読みたくなるのだろうか。
ぼくは「続き」を読みたいことにかけてはやぶさかではない方(?)で、小学校入学前から「少年」や「冒険王」といった月刊マンガ誌で「続き」を待ち、映画の「怪人二十面相」シリーズ(というか「少年探偵団」シリーズ)で「続き」を待ち、小学校三年の時に「少年サンデー」「少年マガジン」が創刊されてからは「続き」を待つのが一週間単位になった。あのいまは亡き梶原一騎原作の『あしたのジョー』のクライマックスの前の週に捕まって留置場、少年鑑別所とたらい回しされ、問題の号を手にとったのは一カ月後だったが、なによりびっくりしたのは鑑別所の同じ部屋に一緒に入った十人全員がその「少年マガジン」に同時に手を出し、その中のひとりが、
「取調べの時『しゃべったらすぐに出してやる』といわれて、『あしたのジョー』の結末が読めるなあと思ったらしゃべりそうになっちゃったよ」といったら、全員が頷いたことだった。
三カ月、一カ月、一週間と間が狭まってくると最後には一日になる。一日で「続き」が読めるのは新聞の連載小説で、三浦綾子の『氷点』が朝日新聞に連載されていた頃、やはりぼくは「続き」が読みたくて読みたくて、というか主人公の女の子が可哀そうで今日はいったいどうなっているのやら心配で、新聞が来るのをいまかいまかと待っていたのだった。
「続き」が読みたくなるのは、ミステリーが典型であるように次に何が起こるかわからなくてワクワクするから――というのはほんとうのようなウソである。なぜなら、新聞小説の大先輩、漱石の多くの作品ではびっくりするような事件はなにも起こらない。なのに、一度読みはじめると(『明暗』にしろ『それから』にしろ)止まらない。それはどう考えても「続き」が読みたいからなのだ。では、漱石の「続き」と、ぼくがいままで書いてきたマンガやミステリーの続きは違うのか。実は同じなのである。ぼくは、漱石の最大の発見はそのことなのではないかと思っている。それは微分すれば「日常」の中に見つかる「続き」性なのだが、おっと「続き」はまたいつか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする