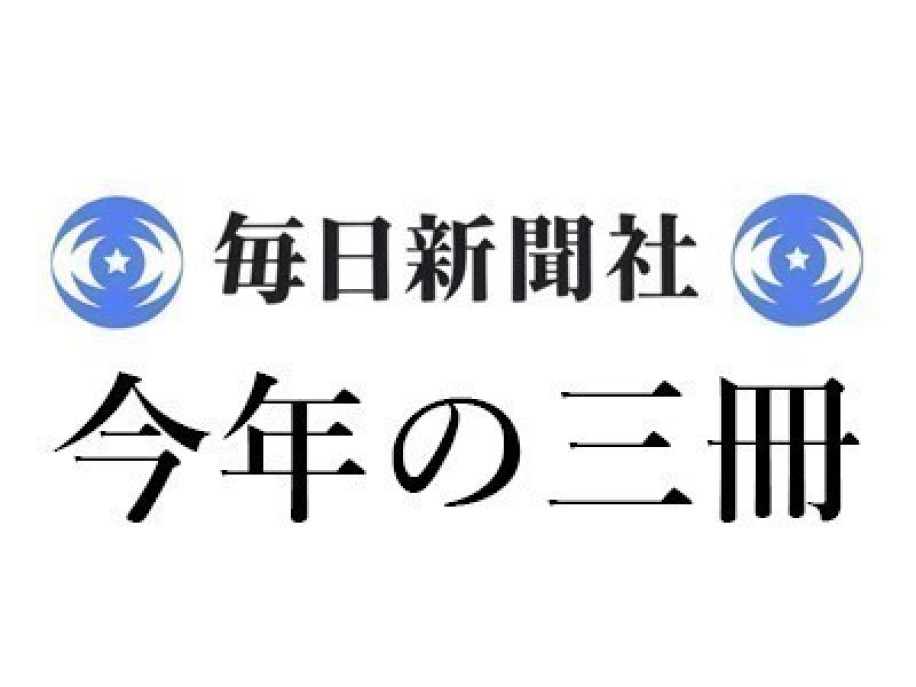書評
『斜塔から』(港の人)
十代の感度、おなじ轍踏まない覚悟
一九四三年七月、平林敏彦は友人たちと合同で詩集『詩集故苑』を限定五十部非売品で制作した。本書のタイトルは、そこに収められた五篇のうちの一篇からとられている。当時十九歳の青年は「斜塔平林敏彦」と扉書きのある自作の頁(ページ)、および奥付を切り取り、筐底(きょうてい)に秘した。うち二篇はその後雑誌に発表されているが、三篇は今回はじめて公にされたものだ。表題作「斜塔」の第三連、「わたしは蹠(あしうら)を/かすかな/思念のやうに/砂に埋めた」に惹かれる。埋めてはいるが踏み込んではいないというかのようなこの「かすかな」感覚が、他の詩篇にも通底している。「わたしはわずか祈るために/幽かに嗚咽する胸を耐え//星屑のやうにしろい/雞卵の殻を踏んで歩いた」(「径」)
斜塔の見える砂丘をひとりで歩む。祈りは「わずか」で、嗚咽も「幽かに」しか響かない。砂粒よりも輪郭の明瞭な命があけわたした空洞としての卵の殻を踏むという、このかさついた力弱い音の哀(かな)しさを平静に聴き取る十代の耳の感度は、鋭敏にすぎるほどだ。
他方、その静謐に見える胸中には、「詩 拾遺」としてまとめられたおなじく一九四三年の作品のひとつ、「熱処理工場」に記されたような「灼熱の鋼を打つ」烈(はげ)しさが潜んでいる。「白木槌が祈禱のやうな響を」というこの詩の一節が、「わずか祈る」ことと高熱の炉のなかでまじわって、つよい鋼に変わる。
そんなふうに読まなければ、応召を挟んで四年後に書かれた批評文の響きの硬さは理解できないだろう。戦後にあらわれた詩に対する激越な批判は、戦争協力の詩群やその作者たちの沈黙に対する怒りとあいまって、手で触れられないほど熱い。二十代となった詩人は、「一篇の詩を生む詩人のすがたはもっとも高度な意味に於ての個の燃焼である」(「個の発掘」)として、そっと思念を埋めた夕暮れの砂に、昼間の熱が残っていることを指摘する。
前著『言葉たちに 戦後詩私史』は、三十四年の沈黙を経て復活するまでの事情と、若いころに影響を受けた詩人たちへの想(おも)いを語る言葉のやわらかさが印象深かったのだが、これらの批評では、いくら若書きとはいえ、北園克衛、小野十三郎、三好達治、あるいは中村真一郎らに対する遠慮のない攻撃的な語調が連なっていて、読む者をとまどわせる。
ところが「斜塔」として残された十代の詩篇を読んでみると、生硬で前のめりの批評文は、眼前のむなしい現実をいったん消し去って、まだかろうじて歩を進められる砂丘にとどめておきたいという切実な願いの表出だったのではないかと思えてくる。おなじ轍(てつ)はもう踏まない、過去の足跡を認めて先へ行くほかないと、自分で自分をけしかけているかのように。
一九五二年に書かれた「小野十三郎論」に記されている「信頼」の一語は、無傷で砂に埋められていた思いのあらわれだろう。「詩」と題された九十代の詩篇がそれを受ける。斜塔の傾きがなくなり、「深夜 ひとり/灯りに向かって/ただひとりだけの人生を/留めおこうと」する語り手の視線の先には、「まだ声援を送ってくれるあなた」がいるのだ。
平林敏彦は、本書の完成を見ることなく、本年四月六日、百歳と八ケ月で逝去した。
ALL REVIEWSをフォローする