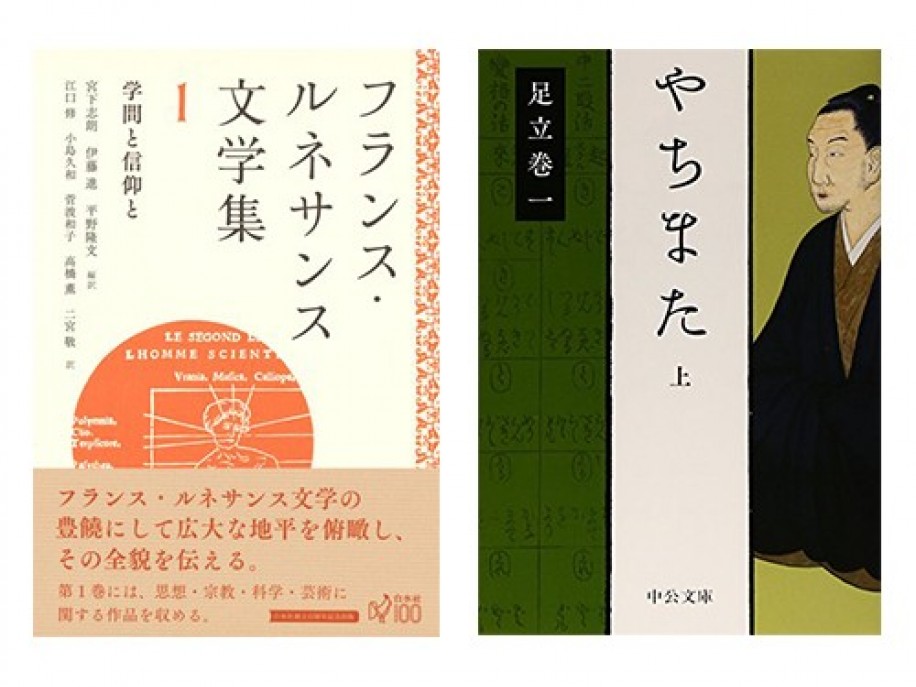書評
『敗戦日記』(筑摩書房)
1975年に見つかった「読んでもらわねば」
渡辺一夫の『敗戦日記』は、多くの日記がそうであるように、公開を前提に書かれたものではない。編者のひとり、二宮敬(たかし)氏が解題で記されているとおり、一九七五年に著者が亡くなったあと、教え子である二宮氏が、十六世紀フランスの作家ラブレーの研究に関わる蔵書を引き継ぎ、整理していたときに発見されたものである。日記が残されていたのは、一九三一年に渡辺がフランスに留学したときパリで購入した小さな方眼ノートで、中身はラブレー研究に必要な資料を網羅した手書きの書誌である。日記はその裏表紙のほうから天地を逆にして書かれていた。はじまりは一九四五年三月十一日、東京大空襲の翌日である。
この空襲によって、印刷製本が終わって刊行されるばかりになっていた、渡辺訳のラブレー『第二之書パンタグリュエル物語』が灰燼に帰した(三月十五日)。ほかならぬこのラブレーに特化していたノートの一部に私的な日記が、それも多くがフランス語による日記が残された理由は、おそらくそこにあるだろう。
時局に対する正確な判断、強固な反戦への想い、軍部とそれになびく人々への深い絶望、壊滅の先の再生をそれでも願う苦しみ。だれかに見つかれば、なにを言われ、なにをされるかわからない強い言葉が散見される。「沖縄諸島におけるまったく意味のない若干の戦果が、我々を、盲目にしている」(四月二十日)。「我が神国政府は自殺への道を歩んでいる」(五月四日)。敗戦前の六月六日に記されたフランス語の一節は、これからもさまざまな場所で引用されるだろう。
この小さなノートを残さねばならない。あらゆる日本人に読んでもらわねばならない。この国と人間を愛し、この国のありかたを恥じる一人の若い男が、この危機にあってどんな気持で生きたかが、これを読めばわかるからだ。(渡辺格・二宮敬訳)
二宮氏の教え子にあたる宮下志朗氏は、あらたに附された解説のなかで、「この発言はたまたま勢い余ってそうなったのかもしれない」と推察している。当時四十代前半の「一人の若い男」にそう言わしめた空気と怒りは、それでも生々しく伝わってくる。この一節によって、記述全体は遺書としても読みうるだろう。しかしそうはならなかったことで、べつの和製ノートに残されていた同時期の「続敗戦日記」とともに、永井荷風や高見順ら作家の戦中日記とは角度のちがう貴重な証言が遺されたのである。
この日記を補完するものとして、串田孫一宛ての書簡と、同時期に発表された文章が十数篇収録されている。一九四四年に書かれた「羈旅」のなかで、渡辺一夫は「戦乱はすばらしい美徳を見せてくれると同時に、あらゆる悪徳が匿れては居られぬようにもする」というラブレーの言葉を引いている。ラブレーというフランス・ルネサンス期における破格の作家の翻訳をつうじて時流に抗していたユマニストは、密かに綴られていた戦中戦後の日記以上に、こういうところですでに重い警告を発していた。戦乱の絶えないいまの時代にこそ、嚙みしめたい言葉である。
ALL REVIEWSをフォローする