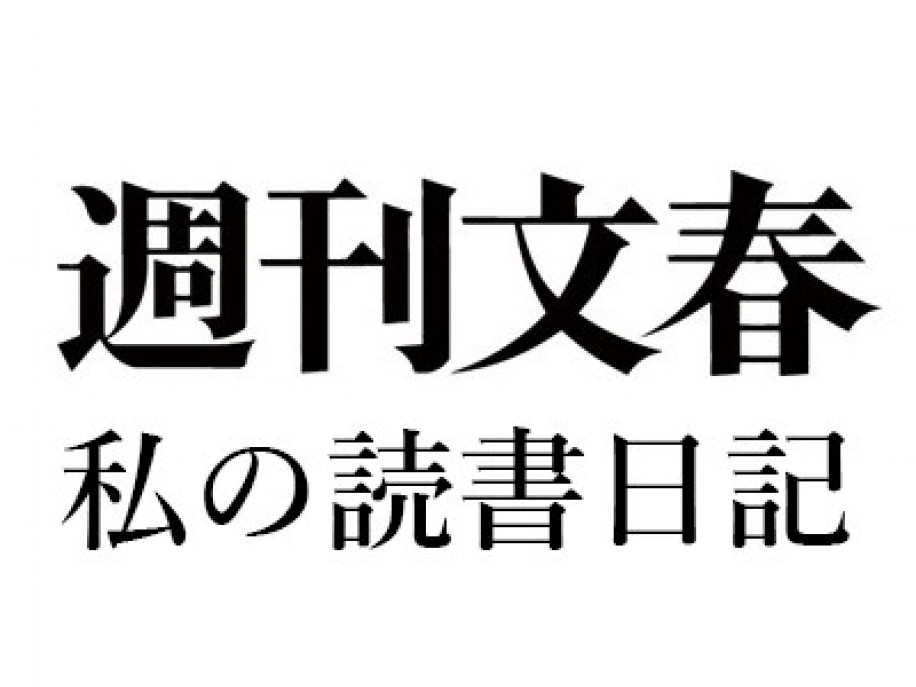書評
『長い物語のためのいくつかの短いお話』(白水社)
語り手が色づけする記憶の断片
淡々と文を重ねてできあがった記憶の層を軽く揺さぶって、細い亀裂をつくりだす。強い感情の起伏はない。程度を弱めるような心の接頭辞に目を凝らすのがロジェ・グルニエの特徴である。敬愛するチェーホフにならった人間観察をより簡素に切りつめていく「感じ」。嫉妬や憎しみ、諦念や怒りといった負の感情も描かれるのだが、なぜか最後に正になる。これはどういうことだろう。短篇の名手と評されるグルニエの小説を読むたびにおなじ感覚にとらわれる。彼の筆致に掛け算はない。なにかとなにかを掛け合わせて相乗効果を狙うのではなく、足し算と引き算を丁寧にたのしみながら書き進め、最後のあたりでふと割り算を提示する。そして、割り切れない想(おも)いに読者を導く。
そのいくらか軽みのある割り切れなさを、これまで洒脱(しゃだつ)という言葉でなんとなく片付けた気持ちになっていたのだが、二〇一七年に九十八歳で亡くなったグルニエの、生前最後の短篇集となる本書に触れて、これは「洒」ではなく、旁(つくり)に一本横棒を足した「酒」だと思った。
十三篇の、それぞれにふさわしい発酵が進んだ酒をちびちびと嘗(な)めたあと舌に残されるのは、俗気のある爽やかさ、嫌味のあるやさしさ、筋の通ったさもしさというような、相反する要素のブレンドなのだ。
基本となる味は色恋。ジャーナリストでもあった作者自身の経験が多分に投影されているようだが、登場人物とはつねに適切な距離が保たれている。なにしろ目次の前の扉に掲げられているのが「わたしは自分のことを三人称で語るのが好きだ。そのほうが都合がよい」というA・O・バルナブースの言葉なのだ。バルナブースはグルニエも愛した某作家が創造した架空の人物である。つまり三人称で描かれた短篇全体が、ひとつの長い自伝小説に切り替わりうるということだろう。
人生を最初からつづきものとしてたどりなおすことはできない。思い出せるのはいつも断片で、語り手の現在がそれを色づけする。人は記憶に支えられ、記憶に裏切られるのだ。「ある受刑者」と題された一篇で描かれるやもめ暮らしの老人は、自らが検事であり裁判官であり被告となって思い出を裁き、もはや被告には極刑たる自死しかないとの結論に達する。
問題は「弁護人が欠けていた」こと。しかしグルニエは、偶然の導きによって生まれた状況や、自分にとって不都合な言葉をも、これ以上ない弁護の材料にしてみせる。記憶の照合が好ましい結果に至らなくても、そのような作業じたいに意味があったと主人公に悟らせるのだ。「記憶喪失」という一篇の最後にはこう記されている。
みじめな結果を前にして、彼が感じたのは、自分が過去を忘れてしまったということではなかった。むしろ、過去のほうが自分のことを忘れかけている、そう思うと、彼はなんだか、とても空しい人生を過ごしたような気がした。
過去を忘れるのではなく、過去に忘れられること。かくも悲観的な結びが、読書体験としての稀有(けう)な幸福をもたらすふしぎさを、何度でも味わいなおしてみたい。
ALL REVIEWSをフォローする