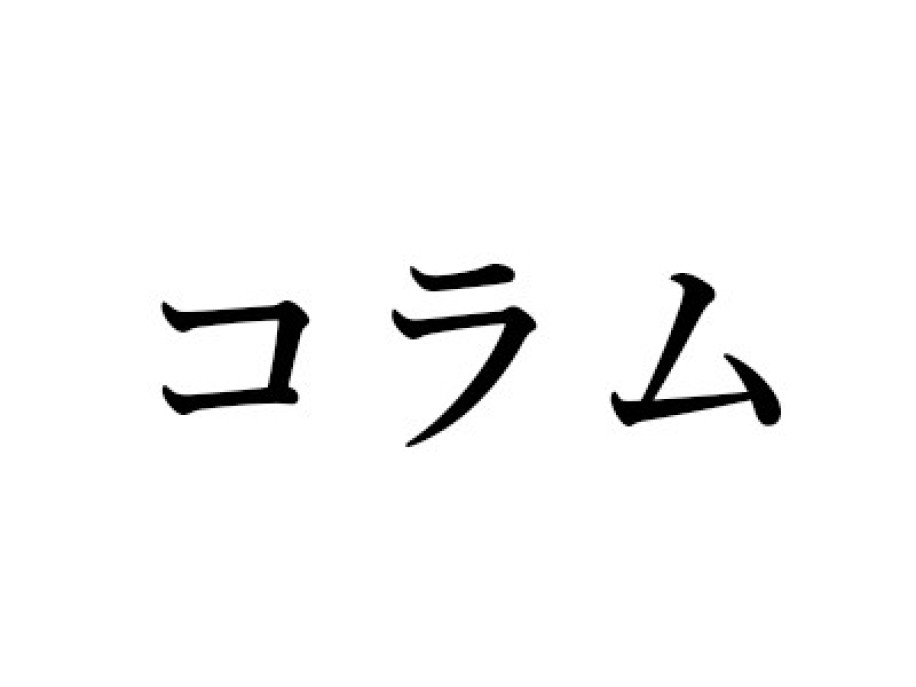書評
『立ち読みの歴史』(早川書房)
店が用意してくれた椅子、変わる人生
ぼくは20代のころ芸術書の専門店で働いていた。出勤初日に先輩社員から受けた諸注意のひとつが、立ち読み客にいやな顔をしないこと。これには次のような理由があった。店主は学生のころ銀座の洋書店で、ガラスケースの中の画集を見たいと告げた。すると店員は「買うんですか?」と言ったという。買うか買わないかを考えるために見たいのに、買わないのなら見せないという口ぶりに彼は憤慨した。その後、彼はしばらくパリで暮らした。小さな書店へ毎日のように通い、写真集を眺めていた。ある日、いつものように訪れると彼のために椅子が用意されていた。感動した彼は、帰国して書店を開いたとき、立ち読み客には親切にしようと決めた。そもそもぼくがその書店に就職したのも、毎日のように立ち読みしていて、店主から「本が好きなようだね。ウチで働かないか」と言われれたのがきっかけだった。立ち読みは人生を変える。
本書は「立ち読み」をキーワードに近代日本の出版史・書店史を探ろうというもの。著者は国立国会図書館職員としてレファレンス(調べ物相談)を15年間担当した、いわば調べ物のプロ。そのノウハウを解説した『調べる技術――国会図書館秘伝のレファレンス・チップス』(皓星社)はベストセラーになった。本書はその実践編でもある。たんに立ち読みの起源や書店の変化を述べるだけでなく、どんな史料にあたったのか、なぜその史料を採用したのかなど調べるプロセスについても詳しくかつ平易に書かれている。
立ち読みははるか昔からおこなわれていたように思いがちだが、実は近代になってからのもの。江戸時代に立ち読みはなかった。なぜなら江戸時代の本屋は現代とまったく違っていたから。本は蔵にしまわれていて、客が来ると店員が出してきた。座売りという。現代でも高級呉服店や茶道具・骨董(こっとう)店などではこの形態が少なくない。常連客が来店すると、店主や店員が好みと必要に応じた商品を奥から出して見せてくれる。立ち読みが可能になるのは、客が商品(本)を自由に手に取ることができるようになってからだ。
重要なことがもうひとつある。立ち読みには黙読する能力が不可欠なのだ。かつて本は音読するのがスタンダードだった。音読で立ち読みは難しい。いま書店の店頭で声に出して読む人がいたら迷惑だろう。
つまり、立ち読みが誕生するには、客が商品を自由に手に取れる書店空間と、黙読できる読者が必要だった。両者がそろったのはいつ頃なのかを著者はつきとめていく。なんだか探偵小説のようでワクワクする。
結論だけ述べると、社会的習俗としての立ち読みが始まったのは1887(明治20)年前後。「立ち読み」ということばの使用例は1898(明治31)年までさかのぼることができる。
立ち読みが広がり、定着するきっかけとなるのは1892(明治25)年の神田大火だという。焼けた店舗を再建する際、開架式の書棚を採用して客が自由に本を手に取れるようにした大型書店が登場し、やがて地方へも広がっていく。
書店空間だけでなく、書物の形態にも変化があった。和紙を糸でとじた和本から、固い表紙のついた洋本(洋装本)に変わる。柔らかな和本は立てて置くことが難しいが、洋本は立てて並べることができる。
明治政府が学制を制定したのは1872(明治5)年だが、読み書きが女性も含めて全国に普及するのが明治末だった。
しかし洋本が登場し、客が自由に本を手に取れる開架式の書店があらわれ、黙読できる人が増えたからといって、突然変異のごとく立ち読みが出現したわけではない。
明治時代には雑誌を専門に売る「雑誌屋」「雑誌店」というものがあった。これは書籍を中心に商う書店とは別の存在だった。雑誌屋のルーツをたどると江戸時代の絵草紙屋に行き着く。絵草紙屋が売っていたのは浮世絵などビジュアルなものと娯楽テキスト。文字を読めない庶民でも立ち読みならぬ立ち見ができた。書籍だけでなく雑誌も販売するところが日本の書店の特徴だが、雑誌店で立ち見していた庶民が近代の書店へ流れ込み、立ち読みするようになったといえる。
立ち読みをめぐって書店側の意見はわかれる。商売のじゃまをするタダ読みだという考え方と、販売促進につながるという考え方だ。1979年、コミックスをフィルム包装する機械が登場する。マンガの立ち読み対策である。一方、1990年に登場した古書店チェーンのブックオフは立ち読みを歓迎した。
その後、立ち読みならぬ座り読み用の椅子を用意する大型書店があらわれ、最近は併設したカフェに購入前の本を持ち込める書店もある。インターネット上の電子書籍書店では内容の一部を試し読みできる。
いま書店がどんどん減っているが、それは立ち読みできる場所が減っているということでもある。立ち読みで人生が変わった者としては、とても残念だ。
ALL REVIEWSをフォローする