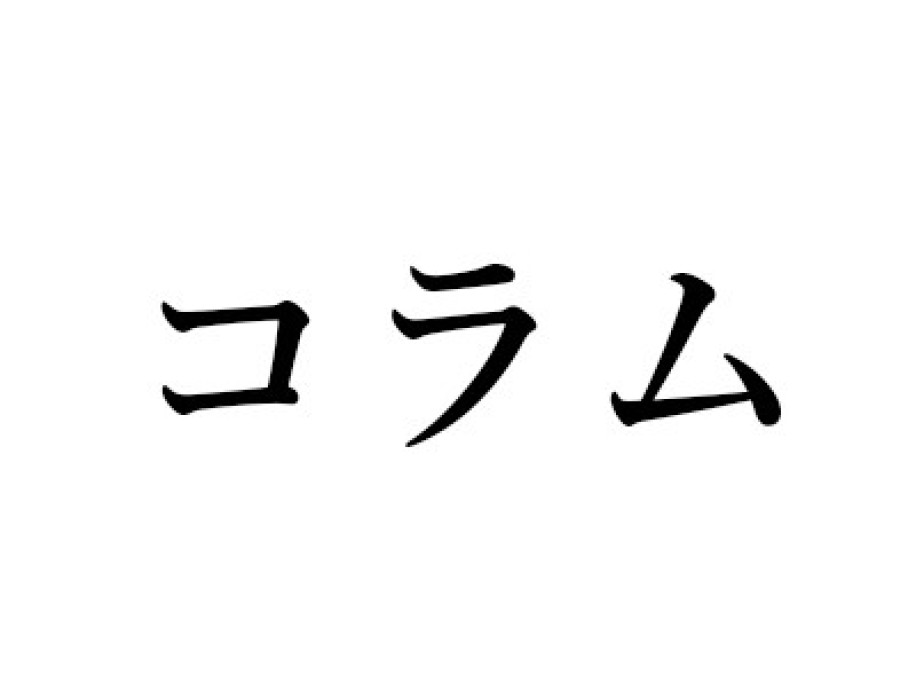書評
『涙の箱』(評論社)
思い描く涙 それが意味することは?
二〇二四年、アジア人女性としてはじめてノーベル文学賞を受賞したハン・ガンさんによる、このちいさな物語は、韓国では二〇〇八年に出版されている。ずいぶんと時間がたっているが、この日本語での出版は世界初の翻訳出版であると、訳者によるあとがきに書かれている。ある村に、「涙つぼ」と呼ばれる子どもが住んでいる。かなしくなくても、何を見ても泣いてしまうからそう呼ばれている。
子どもの住む村に、あるとき、青い羽の鳥を連れた不思議なおじさんが訪ねてくる。涙を集めて、必要な人に売ることもあるのだと、おじさんは子どもに説明する。そして「純粋な涙」をさがし求めていて、涙つぼと呼ばれるこの子どもの噂(うわさ)を聞いてこの村まできたと話す。子どもは、このおじさんとともに旅に出ることを決意する。
涙というものは、いったいなんだろうと、読んでいると疑問を抱く。かなしいから流すだけではない、うれしくてもくやしくても人は涙を流す。かなしみが大きすぎると涙が流れないこともある。
おじさんと子どもは、全財産をはたいてでも涙を買いたいというおじいさんのもとにたどり着く。髪も服も真っ白なおじいさんは、赤ん坊のころ以来涙を流したことがないと言う。そして、おじさんの持ち歩く涙の箱から、選んだ涙を飲みこんでいく――。
もしこの物語を、本国で発表された二〇〇八年当時に読んでいたら、幻想的でうつくしい童話として、さまざまな涙の不思議な色合いとともに記憶しただろう。けれどこの数年来、韓国での民主化運動や済州島での四・三事件といった、韓国近現代史に材をとったこの作者の小説を読んだあとだと、ここに登場するさまざまな涙の意味を、書かれている言葉のずっと奥に見つけようとしてしまう。時代の暴力に翻弄(ほんろう)され、このおじいさんのように、泣きたくても泣けなかった人たちを思い、恐怖や怒りやあきらめが、涙を凌駕(りょうが)してしまった人たちを思い、絶望によって涙が心の奥深くで凝固してしまった人たちを、思わずにはいられない。
さらには、私たち自身の歴史や今現在の姿、戦いの終わらない世界のありようなども、自然に思い浮かぶ。流されてきた、今なお流される涙と、流れることのできない涙。おじさんの言うように「怒りや恥ずかしさや汚さも、避けたり恐れたりしない強さ」を得たときに、私たちは純粋な涙を流すことができるのだろうか。あるいはすべての戦いが終わるとき、世界が純粋な涙を流すのか。
このちいさな物語は、私たちそれぞれの記憶や想像が自在に入りこむことを許し、「影の涙とは?」「純粋な涙とは?」と立ち止まって考えさせてくれる。大人のための童話と帯には書かれているけれど、もちろん子どもが読んでも深く心に残るだろう。
カバーのうつくしい装画は、junaidaさんというアーティストによるもので、本文にも挿絵が描かれている。挿絵はときに、読み手のイメージを限定してしまうけれど、この本での挿絵はむしろ、想像を広げるのを手助けしてくれる。読み手はこの挿絵に支えられながら、それぞれの心に涙の粒を思い描くことができるだろう。青い羽の鳥の声を聞くこともできるだろう。
ALL REVIEWSをフォローする