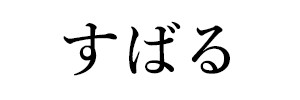書評
『山のある家 井戸のある家 東京ソウル往復書簡』(集英社)
ソウルと東京が溶け合う場所
この本に関する情報を何も知らずに読んだら、「何と豊かな小説なのだろう」と私は思ったにちがいない。けれどこの本は小説ではなく、東京に住む日本語作家の津島佑子と、ソウルに住む韓国語作家の申京淑とが、一年にわたって毎月交わした往復書簡集なのだ。なぜ、ドラマティックな出来事があるわけでもなく、二人の身近な人々や出来事への思いをつづっただけの書簡集が、小説に思えてくるのか? それは、手紙のやりとりがあまりに美しいハーモニーを奏でていて、二人の書き手というより何かもっと大きな一つの意思によって書かれているように感じるからだ。
読みながら私は、ソウルと東京が溶け合って渾然一体になっている不思議な空間にいた。そこには向かい合わせで二つの一軒家が建っていて、一つは井戸のある日本家屋の津島佑子の家、もう一つは山にあり大門(テムン)のついた申京淑の家。二つの家は魅力的な庭でつながっており、私はそこで両者の言葉を聞いていた。書簡が終わってしまうのが寂しいほど、心地よい場所だった。
何も決めずにそれぞれが思うままに書き始めたにもかかわらず、二人は同じ「喪失」と「再生」をめぐる考察から手紙をスタートする。そして、次第に具体的に、自分たちの身の上に起こった喪失と再生の体験を語っていく。その感動的なまでの誠実さ率直さは、相手への深い信頼なくしてはありえなかっただろう。
両者の言葉が意図せずに重なるとき、私は興奮に震え、希望とも歓喜とも言ってよい力をもらった。そしてこの本にはそのような瞬間が満ちているのだ。例えば津島佑子が「申さんの先月のお手紙を拝読して、子どものころを過ごした家は、そのひとにとって、本当に神話の舞台のようなものなんだなあ、と思わずにいられませんでした」【38ページ】と書けば、申京淑も「言葉に縛られず気ままに歩き回るお兄様の後を、息を切らしながら追いかけている少女を思い描きながら津島さんの作品を読むと、ふと、個性的でひととは異なる考えを持っている、さびしい存在に対する全面的な支持の出処も分かるような気がいたします。彼らを神話の世界へと導いていくそのエネルギーの源泉もです」【138ページ】と書くように。
私は日本語でこの本を読んだわけだが、韓国でも韓国語版が出版されている。韓国の読者たちも私と同じような身近さを感じながら読んでいるのだろうか、などと考え始めると、私が読んだのは日本語でも韓国語でもない言葉に思えてくる。
ALL REVIEWSをフォローする