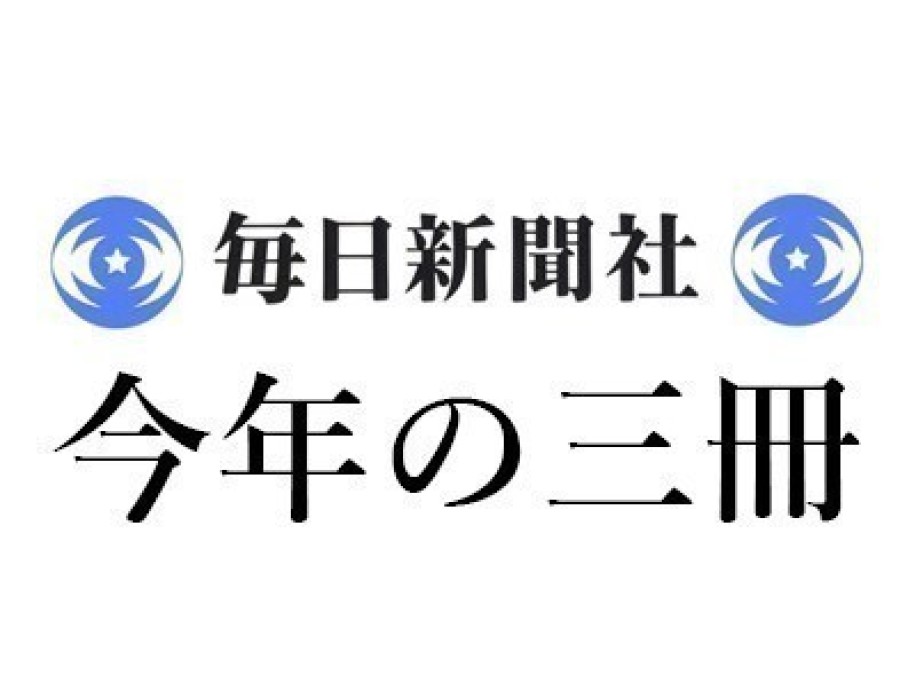書評
『地図と解説でよくわかる 第一次世界大戦戦況図解 WWI Illustrated Atlas』(ホビージャパン)
×月×日
冷戦終了を契機に活発化した地域紛争の遠因をたどっていくと第一次世界大戦にいきつくことが多いが、青島攻略くらいしか戦争に関与しなかった日本人はこの大戦のイメージをいまひとつ明確に抱くことができない。この点、マイケル・S・ナイバーグ『地図と解説でよくわかる 第一次世界大戦戦況図解 WWI Illustrated Atlas』(宮永忠将訳 ホビージャパン 四五〇〇円+税)は大戦の途方もない広がりとその影響の大きさを教えてくれる良書である。
以下、今日の関心に照らして、解説から興味深いテクストを引用してみよう。
東部戦線。
ドイツ軍は、ロシア軍に対して決定的と信じるに充分な打撃を幾度も与えたつもりでいたが、その都度ロシア軍は兵力をかき集めて軍を立て直した。ロシアの大地は、ドイツ軍がどんなに強力な攻勢に出ても、その威力を全て吸収してしまうように思われた。
西部戦線。
(イギリス軍の)戦車は有用である反面、兵器としての完成度は未熟であった。フレールで投入された45両の戦車のうち9両は前線にさえ到達できず、そのほかの戦車も間もなく故障で動きを止めてしまったのである。
オーストリア・ハンガリー帝国の解体。
バルカン半島では、セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、スロベニアを包含するひとつの大きな国を作ることで安定化が図られた。戦勝国となった列強の関与から『ヴェルサイユ国家』とも呼ばれたこの国は、1929年にユーゴスラビアとして発足した。この国は利益が衝突する多くの民族を国境の中に抱えることになったが、列強は資源や国境をめぐって絶えず争う多数の小国を独立させるよりは、ユーゴスラビアの形の方が望ましいと判断したのである。
戦争中の労働力の補給問題。
中国の指導者は、フランスやイギリスに数万単位で労働者を供給し、彼らが「西部戦線で戦闘以外の重労働に従事することで、英仏の若者の労働を肩代わりさせたのである。中国人労働者が働くぶん、英仏は若者を戦場に投入できるので、間接的な軍事支援となる理屈である。中国はこの貢献を梃子にして、日本に中国の領土などの権益を譲渡しないよう、列強に支持を求めたのであった」
巻末には第一次世界大戦における戦死者と民間人犠牲者の国別一覧が出ているが、これにはスペイン風邪の犠牲者は含まれていない。四年の間に空前絶後の数の若者が戦死、戦病死したのだから、大戦後、世界はどうしても変わらざるをえなかったのである。
週刊文春 2025年4月24日
昭和34年(1959年)創刊の総合週刊誌「週刊文春」の紹介サイトです。最新号やバックナンバーから、いくつか記事を掲載していきます。各号の目次や定期購読のご案内も掲載しています。
ALL REVIEWSをフォローする