
フランス文学者。元明治大学教授。専門は19世紀フランス文学。
1949年、横浜市生まれ。1973年東京大学仏文科卒業。1978年同大学大学院人文科学研究科博士課程単位習得満期退学。元明治大学国際日本学部教授。
『職業別パリ風俗』で読売文学賞評論・伝記賞を受賞するなど数多くの受賞歴がある。膨大な古書コレクションを有し、東京都港区に書斎スタジオ「NOEMA images STUDIO」を開設。新刊に『日本が生んだ偉大なる経営イノベーター 小林一三』(中央公論新社)、『フランス史』(講談社)などがある。
『渋沢栄一 上下』(文藝春秋)、『渋沢栄一「青淵論叢」 道徳経済合一説』(講談社)、『文春ムック 渋沢栄一 道徳的であることが最も経済的である』(文藝春秋)、『渋沢栄一: 天命を楽しんで事を成す』(平凡社)、など渋沢栄一に関連する著作も多数。〈プロフィール写真撮影:白鳥真太郎〉
- 著作:
 『チャーチル伝』(作品社)
『チャーチル伝』(作品社) 鹿島 茂
鹿島 茂一九四一年一二月七日晩の吉報小学校六年生のとき三津田健が吹き替えていた「チャーチルの大戦回顧録」をテレビで見て『第二次大戦回顧録』の抄訳二…
書評 『三島由紀夫を見つめて』(ホーム社)
『三島由紀夫を見つめて』(ホーム社) 鹿島 茂
鹿島 茂×月×日市ケ谷の自衛隊駐屯地で四十五歳の三島由紀夫が自刃してから五十五年。つまり二〇二五年は生誕百年に当たるわけで、三島関連の出版物も各種刊…
書評 『フランス中世史Ⅰ カペー朝の革新』(名古屋大学出版会)
『フランス中世史Ⅰ カペー朝の革新』(名古屋大学出版会) 鹿島 茂
鹿島 茂弱小国家の成長過程 王たちの変遷中世の長期的持続の研究を中核に据えたアナール派史学の誕生は、フランス史学とりわけ中世史が「王の歴史」に特化…
書評 『厨川白村:「愛」は人生の至上至高の道徳』(ミネルヴァ書房)
『厨川白村:「愛」は人生の至上至高の道徳』(ミネルヴァ書房) 鹿島 茂
鹿島 茂×月×日厨川白村(くりやがわはくそん)といっても、いまの日本では知る者は少ない。私は菊池寛の伝記を書いたので、厨川が京大英文科時代の菊池の恩…
書評 『凸凹で読みとくパリ: 水に翻弄されてきた街の舞台裏』(学芸出版社)
『凸凹で読みとくパリ: 水に翻弄されてきた街の舞台裏』(学芸出版社) 鹿島 茂
鹿島 茂×月×日原体験的な疑問から出発したオリジナルな労作といえば、佐川美加『凸凹で読みとくパリ水に翻弄されてきた街の舞台裏』(学芸出版社二〇〇〇円…
書評 『地図と解説でよくわかる 第一次世界大戦戦況図解 WWI Illustrated Atlas』(ホビージャパン)
『地図と解説でよくわかる 第一次世界大戦戦況図解 WWI Illustrated Atlas』(ホビージャパン) 鹿島 茂
鹿島 茂×月×日冷戦終了を契機に活発化した地域紛争の遠因をたどっていくと第一次世界大戦にいきつくことが多いが、青島攻略くらいしか戦争に関与しなかった…
書評
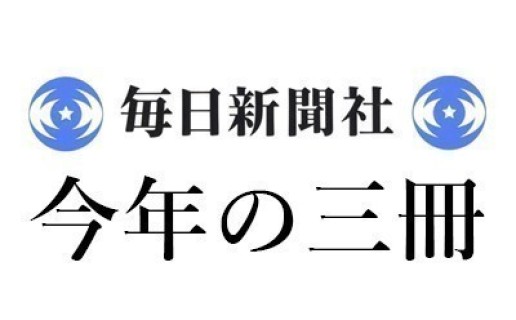
鹿島 茂「2025年 この3冊」毎日新聞|<1>佐藤 彰一『フランス中世史Ⅰ―カペー朝の革新』(名古屋大学出版会) <2>佐川 美加『凸凹で読みとくパリ―水に翻弄されてきた街の舞台裏』(学芸出版社) <3>四方田 犬彦『三島由紀夫を見つめて』(ホーム社)
 鹿島 茂書評
鹿島 茂書評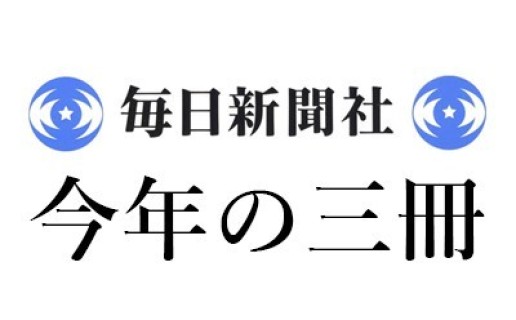
鹿島 茂「2023年 この3冊」毎日新聞|<1>山口昌子『パリ日記―特派員が見た現代史記録1990-2021 第5巻 オランド、マクロンの時代 2011.10-2021.5』(藤原書店)、<2>阿部卓也『杉浦康平と写植の時代』(慶應義塾大学出版会)、<3>ティモシー・ワインガード『蚊が歴史をつくった 世界史で暗躍する人類最大の敵』(青土社)
 鹿島 茂コラム
鹿島 茂コラム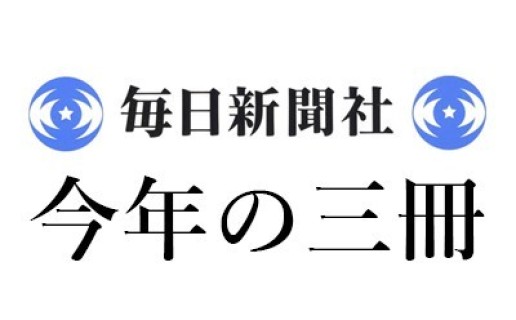
鹿島 茂「2024年 この3冊」毎日新聞|小田光雄『近代出版史探索Ⅶ』(論創社)、ポール・モーランド『人口は未来を語る 「10の数字」で知る経済、少子化、環境問題』(NHK出版)、藤原貞朗『ルーヴル美術館 ブランディングの百年』(講談社)
 鹿島 茂コラム
鹿島 茂コラム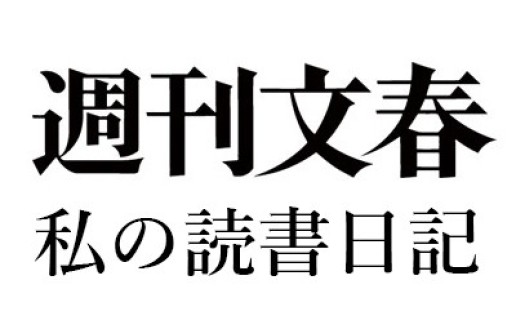
小田 光雄『出版状況クロニクルⅦ』(論創社)、仲俣 暁生『橋本治「再読」ノート』(破船房)
 鹿島 茂読書日記
鹿島 茂読書日記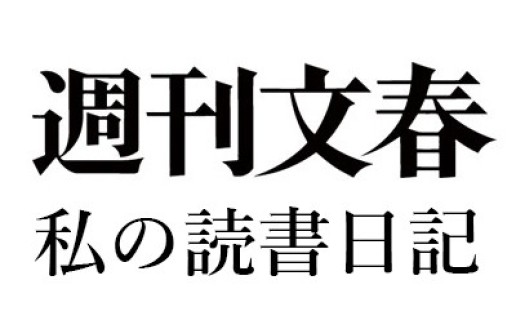
グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学へ(上)』(岩波書店)、今井 むつみ,秋田 喜美『言語の本質』(中央公論新社)
 鹿島 茂読書日記
鹿島 茂読書日記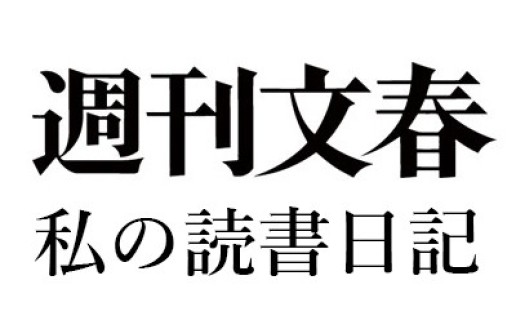
石崎晴己『エマニュエル・トッドの冒険』(藤原書店)、水原紫苑『巴里うたものがたり』(春陽堂書店)
 鹿島 茂読書日記
鹿島 茂読書日記





















