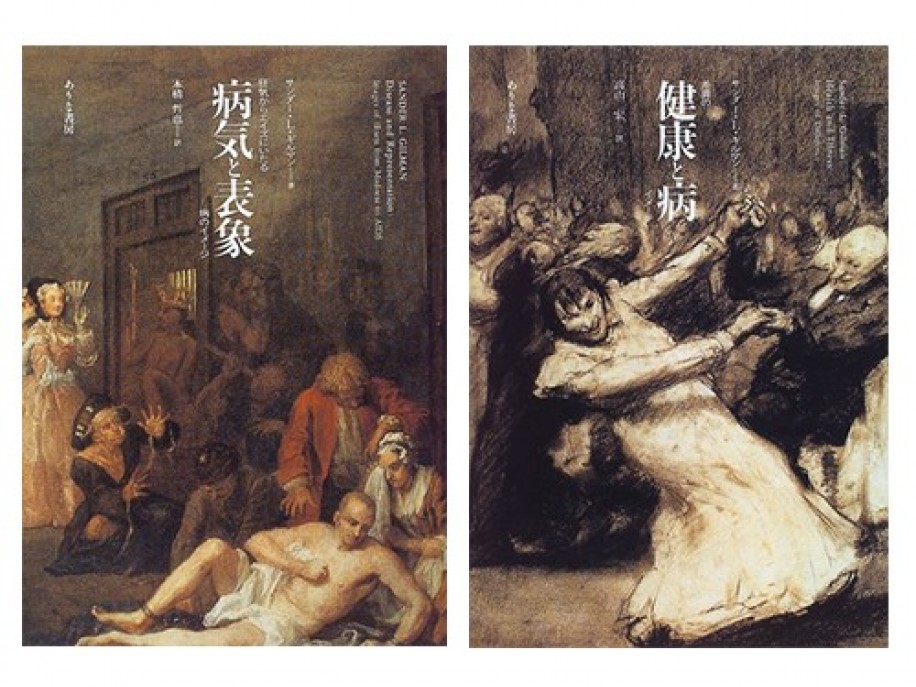書評
『人間喜劇 十九世紀パリの観相術とカリカチュア』(ありな書房)
ヴァルター・ベンヤミンの「パリ――十九世紀の首都」は翻訳でわずか二十ページあまりの小文にすぎないが、ここ十数年間に発表された近代都市論に与えた影響は、計り知れぬものがある。思うに、その巨大なインパクトは「フーリエあるいは路地」「ダゲールあるいはパノラマ」「グランヴィルあるいは万国博覧会」といった、各章のタイトルに典型的にあらわれているように伝統的な歴史観からは全く顧みられることのなかった近代都市文明の諸要素と人物が、詩人的な直感によって、「ミシンとこうもり傘」的な出会いをさせられたところからきている。なぜ、《フーリエ》と《路地(パサージュ)》が《あるいは》で連結されるのか必ずしも論理的な説明がなされているわけではないが、この二つの言葉は併置されたその瞬間に無限の想像力をかきたてる隠喩となって炸裂(さくれつ)する。ひとことでいえば、「パリ――十九世紀の首都」は十九世紀のパリという歴史を素材にした一種の《散文詩》であり、読者にとって、それはメタフォリックに開かれている。
ジュディス・ウェクスラーの『人間喜劇』も、「緒言」で明言されているとおり、ベンヤミンのこの論文を霊感の源泉にしている。ウェクスラーは十九世紀前半のパリを解読するためのキー・ワード的な人物としてバルザック、ドーミエ、ドゥビュロー(マルセル・カルネの名画『天井桟敷の人々』でジャン=ルイ・バローが演じた天才マイム役者)、それに、反骨のジャーナリスト、フィリポンのもとに集まったモニエ、グランヴィル、ガヴァルニ、トラヴィエスらのカリカチュリストを選び出し、これに十九世紀の強迫観念であった「可視の表層と不可視の内面の照応」という思想を解読格子として当てはめてみる。なぜなら人口の急増と産業構造の変化などによって総(すべ)ての住民が互いに異邦人と化した十九世紀の巨大都市パリにおいては、顔を見れば、その人が心の中で考えていることがわかるとするラファターやガルの観相術が、存在の不安を調停するコードとして歓迎されたという事実があったからだ。ウェクスラーはバルザック、ドーミエ、ドゥビュローらの作家や芸術家に、その典型的なあらわれを見ると同時に、彼らが天才として後世に名を残すことができたのは、実は彼らがそうした時代的コードを便宜的に用いながら、最終的にはそれに捕われることがなかったからではないかと問いかける。
この問いがうまく核心をついているかいないかは、取りあげた人物によって、多少のバラつきがある。結論から先に言ってしまえば、『天井桟敷の人々』に触発されてマイム役者となり、のちに美術史に転じた経歴をもつウェクスラー女史だけあって、ドーミエとドゥビュローの章は素晴らしい出来栄えである。かつてドーミエのカリカチュールの本質である力動感が、時代とのかかわりの中でこれほど精緻(せいち)に分析されたことはなかったし、また、わずかなイコンと同時代の証言だけを手掛かりにドゥビュローの天才的な肉体表現を見事に再現してみせた手際は並外れている。さらに、ドーミエとの対比において、ブルジョワの典型人物《ジョセフ・プリュドム》の創造者、アンリ・モニエを扱った章は、その昔、フロベールの『ブヴァールとペキュシェ』で修論を書いた筆者にとっては刮目(かつもく)すべき見解がちりばめられていて、まことに興味が尽きない。
だが、これに反して、バルザックについての分析はいかにも総花的で不満が残る。すなわち、ウェクスラーはバルザックが観相術を人物描写の重要な武器にしたことに軽く触れるだけで、具体的な人物描写の分析も行わず、またバルザックの天才が観相術の静的なコードを突き抜けてしまう過程に論を進めることもなく、ジャンルとしての《生理学もの》のほうへ行ってしまう。これはあくまで個人的な推測だが、ウェクスラーは、『人間喜劇』というタイトルをバルザックから借りながら、それほど深くバルザックの作品を読みこんではいないのではなかろうか。たとえば、ドーミエの『代書人』を論じながら『従妹ベット』のユロ男爵が引き合いにだされぬのは、いかにも不思議な気がするし、またドーミエの手になるフュルヌ版バルザック全集の《ゴリオ爺さん》や《ヴォートラン》の挿絵に一言も言及がなされていないのは、それが彼女の仮説の立証に役立つと思われるだけに一層残念である。
しかし、こうした不満を差し引いたにしてもなお、ウェクスラーの『人間喜劇』は十分に魅力的な書物であるといえる。いや、むしろ筆者などは、彼女が論理的整合性を深追いせずに、歴史上かつてないカリカチュールの黄金時代を築いた挿絵画家群像の仕事を多数の図版によって紹介した部分に、彼女がベンヤミンの衣鉢を継ぐ、十九世紀パリの本物のマニアであることの証拠を見て同好の士を得た嬉(うれ)しさを感じる。
最後に、バルザックの作品の邦題などについて二、三疑問は残るものの、こうした多岐の領域にわたる原書を明快な訳で紹介した訳者の労を多としたい。訳者の発見と出版への努力がなければ、我が国の読書界にこの刺激的な書物は存在していなかったはずなのだから。
ジュディス・ウェクスラーの『人間喜劇』も、「緒言」で明言されているとおり、ベンヤミンのこの論文を霊感の源泉にしている。ウェクスラーは十九世紀前半のパリを解読するためのキー・ワード的な人物としてバルザック、ドーミエ、ドゥビュロー(マルセル・カルネの名画『天井桟敷の人々』でジャン=ルイ・バローが演じた天才マイム役者)、それに、反骨のジャーナリスト、フィリポンのもとに集まったモニエ、グランヴィル、ガヴァルニ、トラヴィエスらのカリカチュリストを選び出し、これに十九世紀の強迫観念であった「可視の表層と不可視の内面の照応」という思想を解読格子として当てはめてみる。なぜなら人口の急増と産業構造の変化などによって総(すべ)ての住民が互いに異邦人と化した十九世紀の巨大都市パリにおいては、顔を見れば、その人が心の中で考えていることがわかるとするラファターやガルの観相術が、存在の不安を調停するコードとして歓迎されたという事実があったからだ。ウェクスラーはバルザック、ドーミエ、ドゥビュローらの作家や芸術家に、その典型的なあらわれを見ると同時に、彼らが天才として後世に名を残すことができたのは、実は彼らがそうした時代的コードを便宜的に用いながら、最終的にはそれに捕われることがなかったからではないかと問いかける。
この問いがうまく核心をついているかいないかは、取りあげた人物によって、多少のバラつきがある。結論から先に言ってしまえば、『天井桟敷の人々』に触発されてマイム役者となり、のちに美術史に転じた経歴をもつウェクスラー女史だけあって、ドーミエとドゥビュローの章は素晴らしい出来栄えである。かつてドーミエのカリカチュールの本質である力動感が、時代とのかかわりの中でこれほど精緻(せいち)に分析されたことはなかったし、また、わずかなイコンと同時代の証言だけを手掛かりにドゥビュローの天才的な肉体表現を見事に再現してみせた手際は並外れている。さらに、ドーミエとの対比において、ブルジョワの典型人物《ジョセフ・プリュドム》の創造者、アンリ・モニエを扱った章は、その昔、フロベールの『ブヴァールとペキュシェ』で修論を書いた筆者にとっては刮目(かつもく)すべき見解がちりばめられていて、まことに興味が尽きない。
だが、これに反して、バルザックについての分析はいかにも総花的で不満が残る。すなわち、ウェクスラーはバルザックが観相術を人物描写の重要な武器にしたことに軽く触れるだけで、具体的な人物描写の分析も行わず、またバルザックの天才が観相術の静的なコードを突き抜けてしまう過程に論を進めることもなく、ジャンルとしての《生理学もの》のほうへ行ってしまう。これはあくまで個人的な推測だが、ウェクスラーは、『人間喜劇』というタイトルをバルザックから借りながら、それほど深くバルザックの作品を読みこんではいないのではなかろうか。たとえば、ドーミエの『代書人』を論じながら『従妹ベット』のユロ男爵が引き合いにだされぬのは、いかにも不思議な気がするし、またドーミエの手になるフュルヌ版バルザック全集の《ゴリオ爺さん》や《ヴォートラン》の挿絵に一言も言及がなされていないのは、それが彼女の仮説の立証に役立つと思われるだけに一層残念である。
しかし、こうした不満を差し引いたにしてもなお、ウェクスラーの『人間喜劇』は十分に魅力的な書物であるといえる。いや、むしろ筆者などは、彼女が論理的整合性を深追いせずに、歴史上かつてないカリカチュールの黄金時代を築いた挿絵画家群像の仕事を多数の図版によって紹介した部分に、彼女がベンヤミンの衣鉢を継ぐ、十九世紀パリの本物のマニアであることの証拠を見て同好の士を得た嬉(うれ)しさを感じる。
最後に、バルザックの作品の邦題などについて二、三疑問は残るものの、こうした多岐の領域にわたる原書を明快な訳で紹介した訳者の労を多としたい。訳者の発見と出版への努力がなければ、我が国の読書界にこの刺激的な書物は存在していなかったはずなのだから。
図書新聞 1987年11月21日
週刊書評紙・図書新聞の創刊は1949年(昭和24年)。一貫して知のトレンドを練り続け、アヴァンギャルド・シーンを完全パック。「硬派書評紙(ゴリゴリ・レビュー)である。」をモットーに、人文社会科学系をはじめ、アート、エンターテインメントやサブカルチャーの情報も満載にお届けしております。2017年6月1日から発行元が武久出版株式会社となりました。
ALL REVIEWSをフォローする