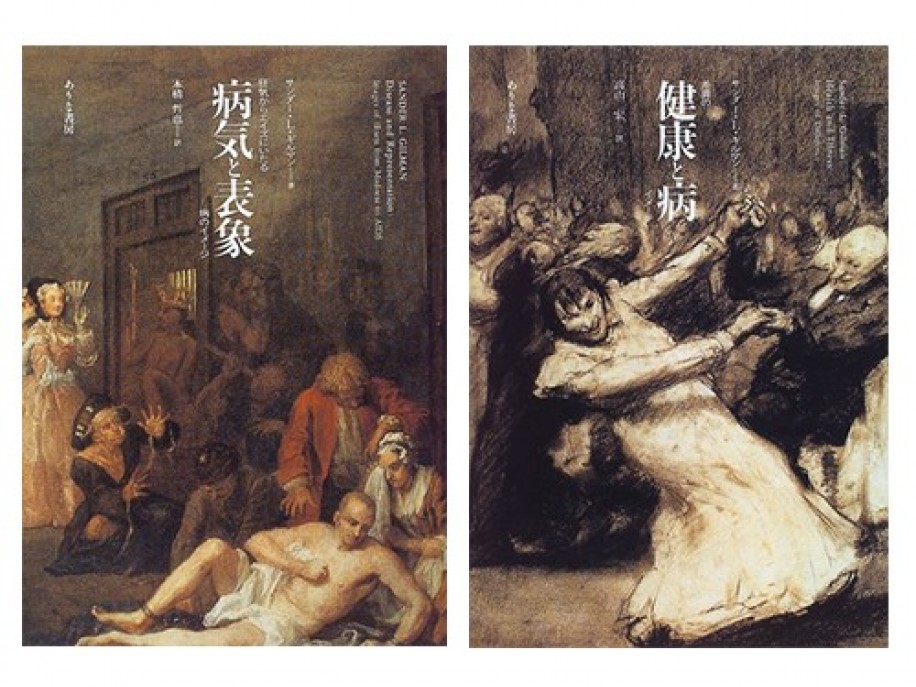書評
『官能の庭―マニエリスム・エンブレム・バロック』(ありな書房)
驚くべき書物である。もっとも古いもので一九四〇年の、もっとも新しいもので一九七四年の日付をもつ、都合三十七篇のエッセーから構成される七百ページの大著。形式的には、三十年にわたって出版された書物の書評集というべきものだが、内容的には、まことに特異なマニエリスム論とバロック論の集大成となっている。稀代の碩学マリオ・プラーツの筆は、その都度のテーマをめぐって、しかしいつしかくだんの書物を離れて縦横無尽に走る。比肩する者のないその博覧強記・博引旁証ぶりは各ページ毎に一目瞭然であり、読者は読み進むにつれ芳醇なワインによる酩酊にも似た気分を味わうことになろう。本書のタイトルと同じ「官能の庭」というエッセーの冒頭に見出せる一文は、まるで本書と著者プラーツその人を指し示しているかのようである。
「いつの日か、誰かしらが、対象をぎっしりとつめこんだこれらの作品、すなわち、イメージや語彙が豊富すぎる書物のあれこれについて、あまりにもびっしりと事物を盛り込んだ数多くの絵画について、イシサンゴの群のようにごちゃごちゃとこみいった彫像について、過剰に装飾された建築について、そして心をかき乱す調べに満ち満ちた音楽について、書くべくその身を捧げなければならないであろう」。
実際、本書はそのようにして書かれた。ヒエロニムス・ボスと『ポリフィルスの狂恋夢』の著者とに対するエッセーを扉として、マニエリスムとバロックのおびただしい芸術家と作品を横断し、そしてプラハやボヘミアやシチリアやレッチェといったバロック都市にまで及ぶ本書の記述内容は、たしかにいちおうは年代順に配列された美術史の相貌をもってはいるが、しかしこれはどのページを開いてみてもプラーツ特有の芳香を放たずにはいない、いわば「プラーツ読本」の様相を呈する。〝prazzesco〟(プラーツ様式)とは、友人たちが彼に捧げた造語だそうだが、本書は、すでに邦訳の出ている同じ著者の『記憶の女神ムネモシュネー』(美術出版社)や『肉体と死と悪魔―ロマンティック・アゴニー』(国書刊行会)に比べて、エッセー集であるがゆえにかえっていっそう「プラーツ様式」を如実に感じさせる書物たりえているというべきであろう。ルキノ・ヴィスコンティ監督の映画『家族の肖像』(一九七四年)においてバート・ランカスター演ずるところの主人公がプラーツをモデルにしているとの風説を思い浮かべながら本書を読むのも、また一興であるにはちがいない。
内容を忠実に要約することは、まず不可能だが、特徴的なのは、マニエリスムとバロックという、ともにいささか曖昧な芸術概念を差異化することに意を注ぐのではなく、むしろ両者を連続的にとらえようとしていることだといえるだろう。つまり、「蛇状曲線(リネア・セルペンティナータ)」という言葉に端的に象徴されるマニエリスムと、曲線の礼賛を主要な特徴とするバロックとのあいだに、プラーツはさほどの懸隔を見ていないようなのである。しかし、本書の魅力は、そうした概念的な詮索よりも、もう少し文体(スタイル)に即した細部にこそあるといわなければならない。たとえば、「グロテスク」と題されたエッセーにおいて、プラーツは「イタリアの文学と美術は幻想的(ファンタスティコ)なものに乏しい」と書く。ヴァティカン宮殿のロッジアにあるラファエッロによると想定されたグロテスク模様に関して、その自然主義的な描写自体が幻想的なものからの逃避であるというのだが、こうした指摘こそ貴重なのだ。それはまた「バロック序説」なる文章において、〈バロック〉と〈フィオレンティニタ〉(フィレンツェ的特性)とを峻別する際にもいえることで、フィレンツェの聖堂の白と黒の大理石の縞模様の化粧張りに典型的に見られるフィレンツェ人の数学的、幾何学的精神や、あるいは硬石象嵌細工(ピエトレ・ドクーレ)に見られる表象機能から切り離された素材(マテリア)そのものへの趣向が、バロック的なものとはおよそ無縁であるとの指摘など、いわれてみればそのとおりであるにはちがいないのだが、われわれの目にはまことに新鮮に映る。シェイクスピアとルーベンスに数多くの共通点を見るというのも、ふつうのバロック論には出てこない視点である(「ルーベンス」)。カラヴァッジョをバロック的でないとするB・Bことバーナード・ベレンソンに対する辛辣な批判(「カラヴァッジョ」)や、チェーザレ・リーパの『イコノロギア』の「引用に次ぐ引用のモザイク作品」たるフランチエスコ・ピアンタの彫刻、あるいは蠟彫刻師ガエターノ・ジュリオ・ズンボの造形したペスト風景を俎上に載せたエッセーなども見逃すことはできない。
バロックを論ずるバロキスト・プラーツの面目躍如たる書物。マニエリスムやバロックについての概念上の変化を必ずしももたらさないにしても、本書はそれらの内実を比類のない仕方で豊饒にしてくれる。
【この書評が収録されている書籍】
「いつの日か、誰かしらが、対象をぎっしりとつめこんだこれらの作品、すなわち、イメージや語彙が豊富すぎる書物のあれこれについて、あまりにもびっしりと事物を盛り込んだ数多くの絵画について、イシサンゴの群のようにごちゃごちゃとこみいった彫像について、過剰に装飾された建築について、そして心をかき乱す調べに満ち満ちた音楽について、書くべくその身を捧げなければならないであろう」。
実際、本書はそのようにして書かれた。ヒエロニムス・ボスと『ポリフィルスの狂恋夢』の著者とに対するエッセーを扉として、マニエリスムとバロックのおびただしい芸術家と作品を横断し、そしてプラハやボヘミアやシチリアやレッチェといったバロック都市にまで及ぶ本書の記述内容は、たしかにいちおうは年代順に配列された美術史の相貌をもってはいるが、しかしこれはどのページを開いてみてもプラーツ特有の芳香を放たずにはいない、いわば「プラーツ読本」の様相を呈する。〝prazzesco〟(プラーツ様式)とは、友人たちが彼に捧げた造語だそうだが、本書は、すでに邦訳の出ている同じ著者の『記憶の女神ムネモシュネー』(美術出版社)や『肉体と死と悪魔―ロマンティック・アゴニー』(国書刊行会)に比べて、エッセー集であるがゆえにかえっていっそう「プラーツ様式」を如実に感じさせる書物たりえているというべきであろう。ルキノ・ヴィスコンティ監督の映画『家族の肖像』(一九七四年)においてバート・ランカスター演ずるところの主人公がプラーツをモデルにしているとの風説を思い浮かべながら本書を読むのも、また一興であるにはちがいない。
内容を忠実に要約することは、まず不可能だが、特徴的なのは、マニエリスムとバロックという、ともにいささか曖昧な芸術概念を差異化することに意を注ぐのではなく、むしろ両者を連続的にとらえようとしていることだといえるだろう。つまり、「蛇状曲線(リネア・セルペンティナータ)」という言葉に端的に象徴されるマニエリスムと、曲線の礼賛を主要な特徴とするバロックとのあいだに、プラーツはさほどの懸隔を見ていないようなのである。しかし、本書の魅力は、そうした概念的な詮索よりも、もう少し文体(スタイル)に即した細部にこそあるといわなければならない。たとえば、「グロテスク」と題されたエッセーにおいて、プラーツは「イタリアの文学と美術は幻想的(ファンタスティコ)なものに乏しい」と書く。ヴァティカン宮殿のロッジアにあるラファエッロによると想定されたグロテスク模様に関して、その自然主義的な描写自体が幻想的なものからの逃避であるというのだが、こうした指摘こそ貴重なのだ。それはまた「バロック序説」なる文章において、〈バロック〉と〈フィオレンティニタ〉(フィレンツェ的特性)とを峻別する際にもいえることで、フィレンツェの聖堂の白と黒の大理石の縞模様の化粧張りに典型的に見られるフィレンツェ人の数学的、幾何学的精神や、あるいは硬石象嵌細工(ピエトレ・ドクーレ)に見られる表象機能から切り離された素材(マテリア)そのものへの趣向が、バロック的なものとはおよそ無縁であるとの指摘など、いわれてみればそのとおりであるにはちがいないのだが、われわれの目にはまことに新鮮に映る。シェイクスピアとルーベンスに数多くの共通点を見るというのも、ふつうのバロック論には出てこない視点である(「ルーベンス」)。カラヴァッジョをバロック的でないとするB・Bことバーナード・ベレンソンに対する辛辣な批判(「カラヴァッジョ」)や、チェーザレ・リーパの『イコノロギア』の「引用に次ぐ引用のモザイク作品」たるフランチエスコ・ピアンタの彫刻、あるいは蠟彫刻師ガエターノ・ジュリオ・ズンボの造形したペスト風景を俎上に載せたエッセーなども見逃すことはできない。
バロックを論ずるバロキスト・プラーツの面目躍如たる書物。マニエリスムやバロックについての概念上の変化を必ずしももたらさないにしても、本書はそれらの内実を比類のない仕方で豊饒にしてくれる。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
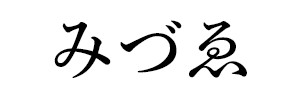
みづゑ 1992年夏
ALL REVIEWSをフォローする