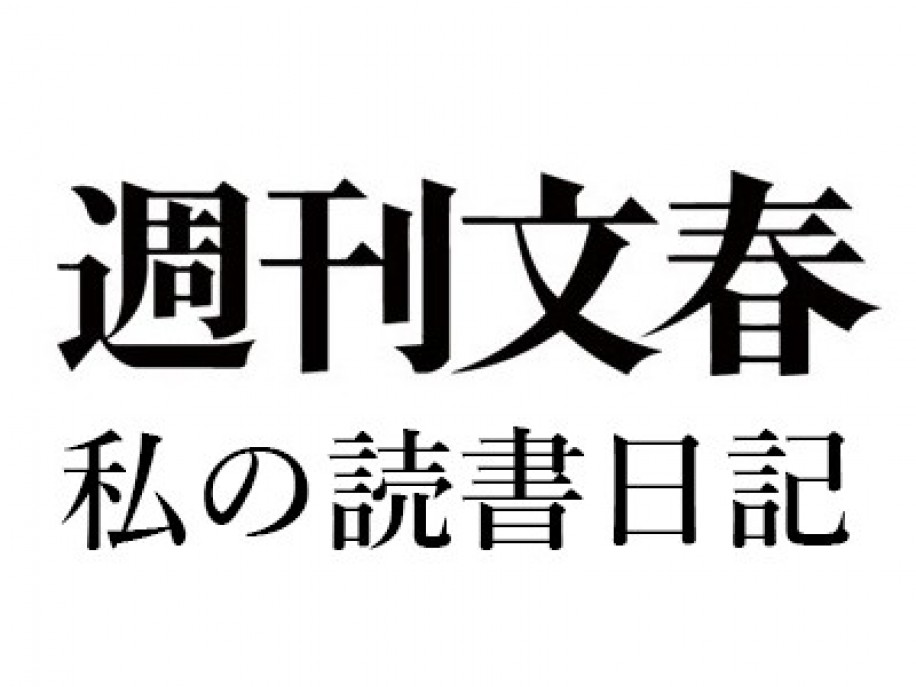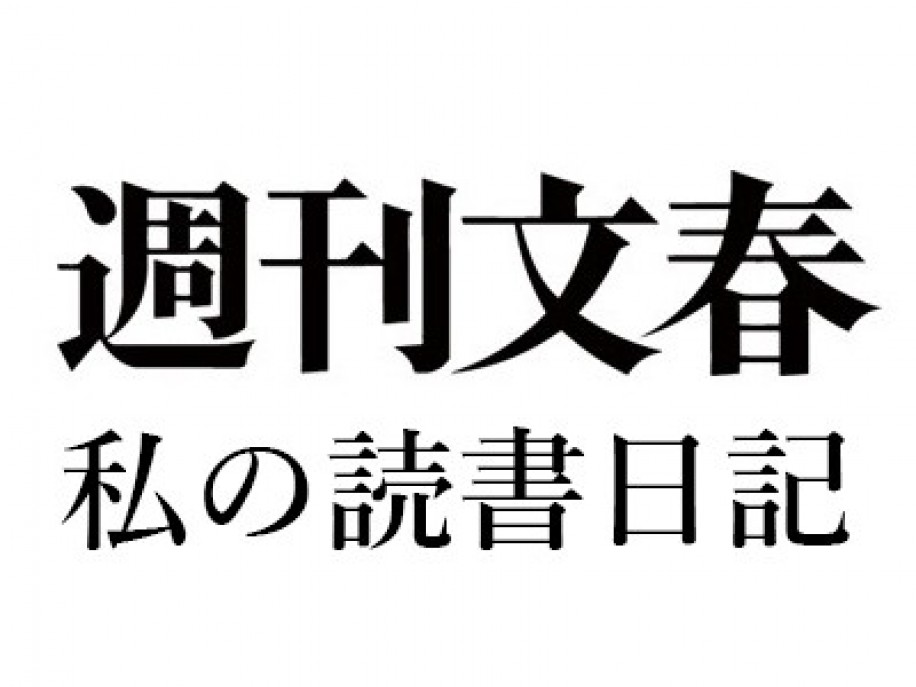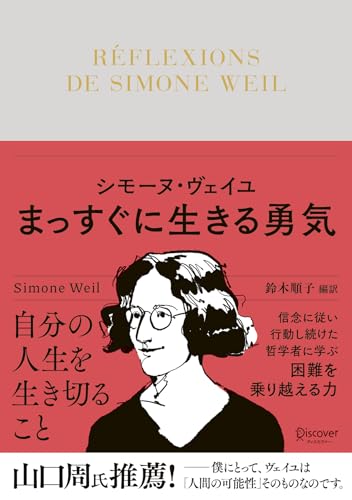書評
『フランス中世史Ⅰ カペー朝の革新』(名古屋大学出版会)
弱小国家の成長過程 王たちの変遷
中世の長期的持続の研究を中核に据えたアナール派史学の誕生は、フランス史学とりわけ中世史が「王の歴史」に特化しすぎたことへの反動と見なすことができるが、何でも直輸入の日本では「王の歴史」が未紹介のうちにその軽視だけが輸入されるという困った事態が引き起こされた。その結果、読者が「王の歴史」を知りたくても通史的な中世史が皆無という面妖な状況が生じたのである。この意味で本書は待望久しい一冊である。しかも、著者は世界水準を抜く『フランク史』全三巻を上梓(じょうし)した世界的権威。かくて最初の通史的フランス中世史でありながら決定版といえる史書の誕生とあいなった。理由の一つは、カペー朝歴代の王の性質・能力、王妃がもたらした変化、王族や大貴族との関係や内紛、領邦国家や外国との戦争、土地制度・身分制度の変遷、ローマ教皇と王のかかわりなど、通史に必要不可欠な事項がアナール派の成果も踏まえながら、公正に記述されていること。
しかし、本書を真に価値ある歴史書にしているのは「地理的・民族的・言語的に多様なフランスがなにゆえに中央集権国家となったのか?」という根源的な問いが立てられていることだ。以下興味深い論点を列挙してみよう。
(1)カロリング朝ロベール家出身のユーグ・カペーは選挙方式で新王朝の王に選ばれたが、「即位すると直(ただ)ちに世襲方式への復帰を考えた。その手段としたのが、長子を共同王として、王の生前に即位させるやり方である」。この共同王方式が意外に効果的だったのだ。フランク王国衰退の原因となった王国分割が妨げられると同時に男子長子相続制への道が開けたからである。初期のフランスは周囲を強大な領邦国家に囲まれた弱小国家だったにもかかわらず王権の確立を見たのはこの共同王方式で直系長子が何代か続けて王位を継いだため、王位=公権力という観念が支配的となり、主従関係の整備や婚姻政策の展開に有利に働いたためである。
(2)こうした過程は王子の命名からも類推できる。アンリ一世まではロベール家の名前リストによるが、フィリップ一世はロベール家リスト外から採用され、以後はルイやシャルルのようにカロリング朝の名前が復活採用される。これは歴史認識の深化による正統性への回帰と見なすことができる。
(3)領邦国家との抗争を経てルイ六世の代で王権が確立されると、領邦国家が自立的であったことが逆に大きなプラスをもたらす。領邦国家の自立性は王国の統合的側面からはマイナスだが、領邦国家内においては経済的・行政的整備というプラスがあった。
そうした豊かな果実を実らせた木を、ルイ六世の後継者たちは、戦略的で巧みな婚姻政策と主従関係の論理によって、そっくり自らの領土に併合したのであった。
図書館向けの重厚な通史でありながら、ルイ七世の王妃アリエノール・ダキテーヌのフランス史を変えた奔放な生活、フィリップ四世治下のネル塔事件やタンプル騎士修道会廃止などのゴシップ的なエピソードも、実証を踏まえてしっかり記述されている。
「王の歴史」を知ることなくフランス史を語ることはできない。
すべてのフランス好きにとって必読の一冊である。
ALL REVIEWSをフォローする