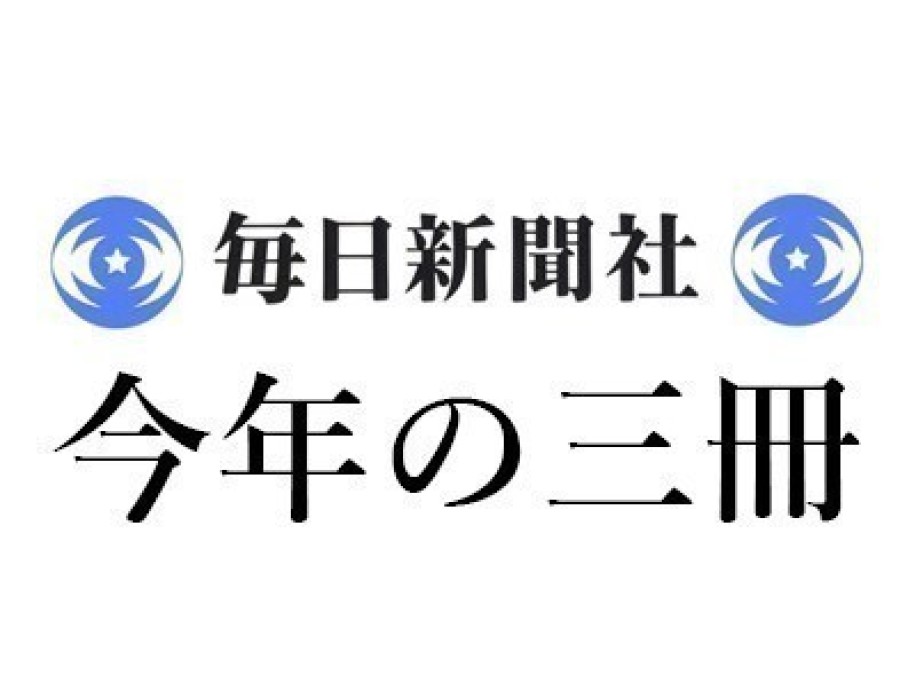書評
『凸凹で読みとくパリ: 水に翻弄されてきた街の舞台裏』(学芸出版社)
×月×日
原体験的な疑問から出発したオリジナルな労作といえば、佐川美加『凸凹で読みとくパリ水に翻弄されてきた街の舞台裏』(学芸出版社二〇〇〇円+税)も挙げなくてはならない。「なぜ、ノートル=ダム大聖堂はすぐ水に浸かってしまうシテ島に建てることができたのか?」
この疑問に答えてくれる資料は皆無のように思っていた。なぜなら、パリ史のどの研究書でもシテ島の「地面より上の事」しか論じられていなかったからである。
大きなヒントとなったのは一九一〇年一月のセーヌの大洪水の時につくられた浸水被災地域地図だった。被災図にはグランブールヴァールが走る非河岸地域も含まれているのに対し、歴史家が「サン・マルタン島」と呼ぶ右岸の島状の土地は被災を免れたからである。
謎は、一万年前に溯り、セーヌ川と、いまでは暗渠化されている支流ビエーヴル川の「河川争奪戦」を調べることで解決する。
約一万年前には隣り合って流れていた二つの川のうち、より力が強いビエーヴル川が力の弱いセーヌ川の水を奪った結果、セーヌ川の旧流域が「旧河道」と呼ばれる低地に変わったことがそもそもの始まりである。セーヌが氾濫すると「旧河道」は水に覆われるが、二本の川に挟まれていた微高地、すなわち「サン・マルタン島」だけは水に浸からずに済んだというわけだ。
この事実によって史料の読み直しが必要になる。
たとえば最古の文献である『ガリア戦記』に登場する島(ルテキア)はシテ島ではなく「サン・マルタン島」ではなかったのかという仮説が浮上してくる。シテ島はむしろ緊急時の避難場所であった。こうした二つの川中の島の立場が逆転するのは、ローマ支配時代にカルド(南北の幹線道路)とデクマヌス(東西の幹線道路)が造られてからである。土盛りされた二つの堤(ショセ)が旧河道を塞いだため、排水不良となったサン・マルタン島の東部は軟弱な地盤となったのに対し、水のせき止められたサン・マルタン島西部は土地が乾燥して建物が建てられるようになったのだ。
第二の変化はルテキアが、三世紀以後、ゲルマン人、フン族、ノルマン人などの襲撃を受け、住民がシテ島に立てこもらざるを得なくなったときに訪れる。西フランク王シャルル禿頭王は再度の襲撃に備えて島の周囲に城壁を巡らし、シャンジュ橋の少し下流側に堰のような橋を造って敵船の通行を阻止したのだが、これにより、右岸に土砂が蓄積し、その水際ラインが変わり、橋建設時と比べると川の流れの中心線に七度のずれが生じたのだ。その影響は後にルーヴル宮の構造にもあらわれた。
右岸の西側で土地の乾燥化が、東側で湿潤化が始まったのも、またシテ島でも水没しない土地が東側に付け加わり、さらに島の西側の乾燥化で王宮が建設できるようになったのもこの影響なのである。
しかし、東西の乾燥化と湿潤化がより顕著になったのは、一一四八年にビエーヴル川とセーヌ川の合流点の移動があってからのことだ。
ビエーヴル川はサン・ヴィクトール修道院の敷地に農業用の水を引き込むために開削された運河へと流れを変え、シテ島近くでセーヌに合流するようになったが、この付け替え工事の影響が甚大だったのだ。
工事以前は、シテ島の周囲には「セーヌ川+ビエーヴル川」の水量が流れていたが、工事以後は「ビエーヴル川の水はすべてシテ島と左岸の間にある小流路に流れ込み、二つの川の水がシテ島の下流側で合わさることになった」。
その結果、シテ島では土地の乾燥化が進み、軟弱な地盤が安定した。ノートル・ダム大聖堂の建設はまさにこのビエーヴル川の合流点の移動により可能になったのである。
【イベント情報】佐川美加 × 鹿島茂
『凸凹で読みとくパリ 水に翻弄されてきた街の舞台裏』(学芸出版社)を読む【日時】2025/11/30 (日) 19:00 -20:30
【会場】PASSAGE SOLIDA(神保町)
東京都千代田区神田神保町1-9-20 SHONENGAHO-2ビル 2F
※1Fよりお入りいただき、階段で2階にお上がりください
【参加費】現地参加:1,650円(税込) 、オンライン視聴:1,650円(税込)(アーカイブ視聴可)
※ALL REVIEWS 友の会 特典対談番組
※ALL REVIEWS 友の会(第5期:月額1,800円) 会員はオンライン配信、アーカイブ視聴ともに無料
 https://allreviews.jp/news/7566
https://allreviews.jp/news/7566週刊文春 2025年11月13日
昭和34年(1959年)創刊の総合週刊誌「週刊文春」の紹介サイトです。最新号やバックナンバーから、いくつか記事を掲載していきます。各号の目次や定期購読のご案内も掲載しています。
ALL REVIEWSをフォローする