谷川 渥ATSUSHI TANIGAWA
公式サイト: http://eccehomo.jugem.jp/
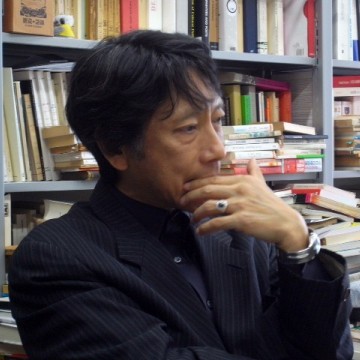
美学者。1972年、東京大学文学部美学芸術学科卒業。78年、東京大学大学院人文科学研究科美学芸術学専攻博士課程修了。マニエリスム・バロックからモダニズム・現代美術にいたる広範な領域を視野に収め、美学原理論、芸術時間論、廃墟論、だまし絵論、シュルレアリスム論、そして「芸術の皮膚論」など、独自の視点による美学的地平の開拓に努め、多方面にわたる批評活動を展開。著書に『形象と時間』『美学の逆説』『芸術をめぐる言葉』『鏡と皮膚』『図説だまし絵』『廃墟の美学』『肉体の迷宮』『書物のエロティックス』『幻想の花園』など多数。


「独身者機械」の「唖然とするほどの並行関係」をあぶり出す「解釈」の徹底ぶりかつて『独身者の機械』として邦訳(高山宏・森永徹訳、ありな書房、…


種村季弘ラビリントス広大な知の地平をあらためてまざまざと浮かび上がらせてくれる七百ページに及ぶ恐ろしく大部の本である。昨年、諏訪哲史編『…


例を見ぬ委曲を尽くした浩瀚な評伝比類のない作品を遡及的に指示するエピソードの数々二人のイギリス人によるベルメール評伝である。全十章のうち…


フェミニズムの美術史学「フェミニズムで読む美術史」というのが、訳者の与えた本書(萩原弘子訳、新水社、一九九八)の副題である。かつて「フェミ…


ゴンブリッチの美術論――『棒馬考』について『棒馬考』(一九六三、増補完訳、勁草書房、一九九四)は、論文や講演の文章など十四篇を収めたエルンス…


ロバート・バルディック『ユイスマンス伝』を読むジョリス・カルル・ユイスマンスの『さかしま』(一八八四)は、一九六六年に桃源社の「世界異端の…