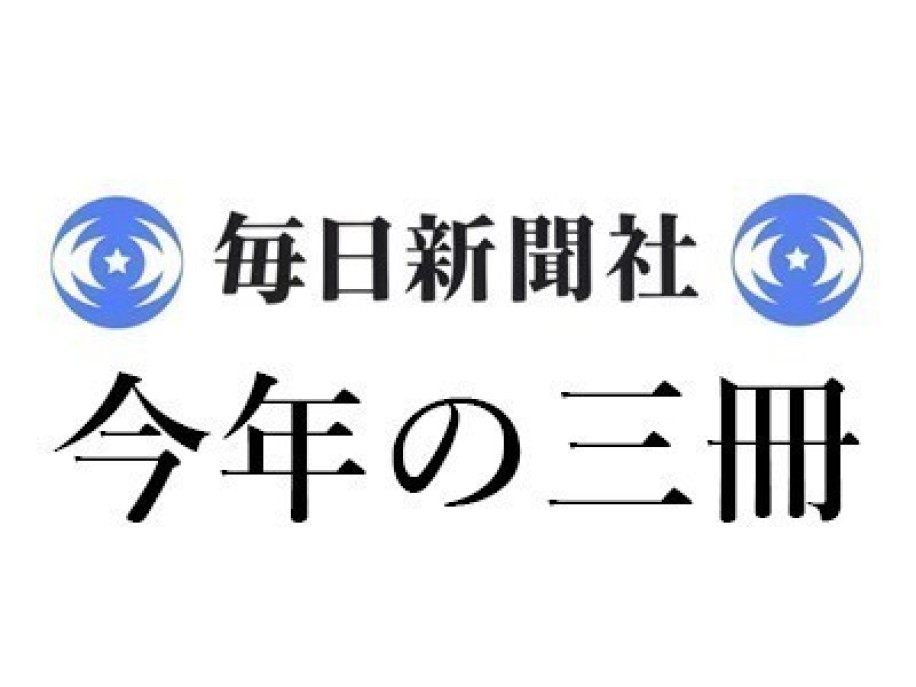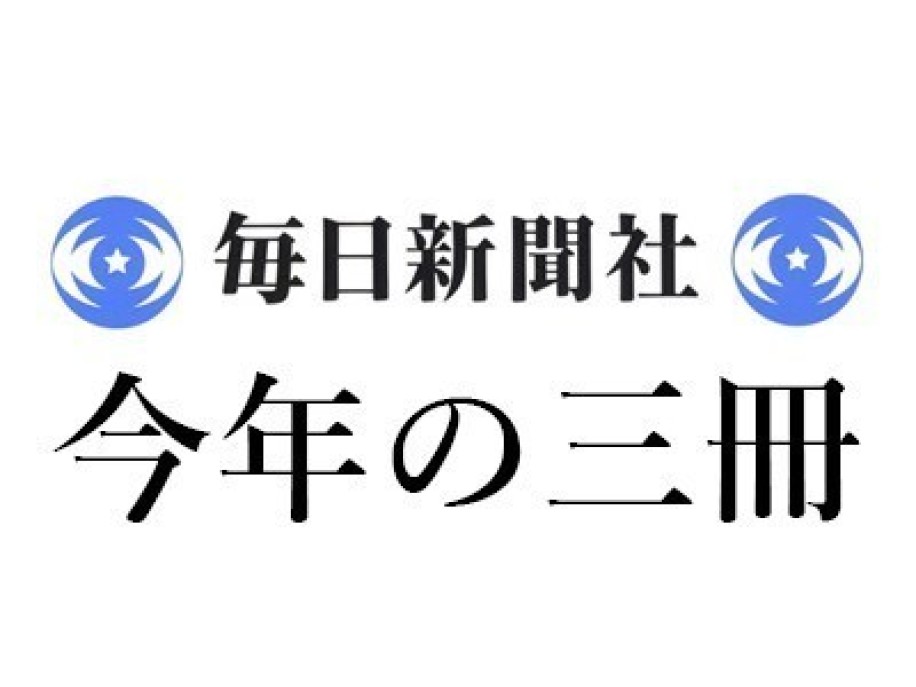書評
『新訳 大いなる遺産 上』(KADOKAWA)
表現の特殊性に迫る鮮やかな訳出
ディケンズの名は日本では明治期からよく知られているが、この代表作を未読の人は意外に多いかもしれない。貧しい孤児がある罪人を助けたことから後援を得て紳士修業のためにロンドンに赴くという波瀾万丈の物語。本作の魅力を堪能できる新訳の刊行を機に、「語り口」「喜劇」「暴力」という点からこの名作を紹介したい。ディケンズの小説は抜群におもしろい。けれど、その面白みを味わい読破するには、作家の特異な文体について知る必要がある。本書の訳者あとがきによれば、あの凝りに凝った文章を書くポーがディケンズの「書きぶりに尋常ならざる畏敬(いけい)を抱いている」と。訳者はこう述べている。
ディケンズの書いた物語の意味はすでに何度も訳出されてきたが、この語り口――その表現の特殊性――は果たして訳出されてきたのだろうか。
男児ピップを主人公にした本作の魅力の一つは、現在と過去の視点のダブルフォーカスにあるのだろうと私は漠然と考えていた。成熟した彼が昔を回顧し、過去の自己と対話をしながら、自分を再構築していく物語なのだろうと。
自伝風小説において語り手の「私」と主人公の「私」の間に醸しだされる「内的緊張関係」とF・シュタンツェルが呼んだもの、それが『大いなる遺産』では錬成と洗練を極めているのだ。
たとえば、序盤にピップが年の離れた姉ミセス・ジョーに「タール水」を飲まされるくだりがある。幼いピップにとっては不味(まず)い液体でしかないが、大人のピップは「どこかのとんでもない医者」がこの怪しげな中世の薬を「復活させ」たのだと認識している。これを飲んでいる自分が「塗りたての塀のような臭いがしているのに気づいていた」という部分も、感覚は幼児のものであるが、言語化は大人の彼によるものだろう。
ディケンズの作は1850年代頃から「あまり笑えなくなった」と評されていたという。初期のコメディに比して題材やトーンがシリアスになったからだ。とくに本作の一つ前の長編『二都物語』はそうだった。そこでディケンズは『大いなる遺産』を一つの喜劇として書き始めたとされる。一文一文がとてつもなく機知に富み、その例は河合氏が訳出に力を入れたという比喩表現にも見られる。例えば、ウェミックという事務員の口を表すのに使われている「郵便ポスト」という言葉。「郵便ポストのような」とは作者は書かない。この方針を訳者は引き継ぎ、バターを塗る時も「膏薬(こうやく)」を塗るのだ。
ロンドン帰りで澄ましているピップを仕立屋の小僧が念入りにからかう場面などは、腹筋がつる可笑しさで、コメディの質を高めているが、その一方、暴力も凄絶(せいぜつ)である。イギリスが近代化を経て封殺した前時代の粗暴さと攻撃性がいっそう弱者に向かった時代でもあった。ピップが被る身体的暴力も精神的な虐待も、ユーモラスな筆致がいっそう哀れを誘う。老嬢ミス・ハヴィシャムに仕込まれて性悪女になっていたエステラのピップへの対応などはサディスティックとも言える。
さて、エステラに片思いをするピップだが、最後にふたりはどうなるのか? これに関しても、この新訳は鮮やかな答えを提示しているのでぜひ確かめてほしい。
【下巻】
ALL REVIEWSをフォローする