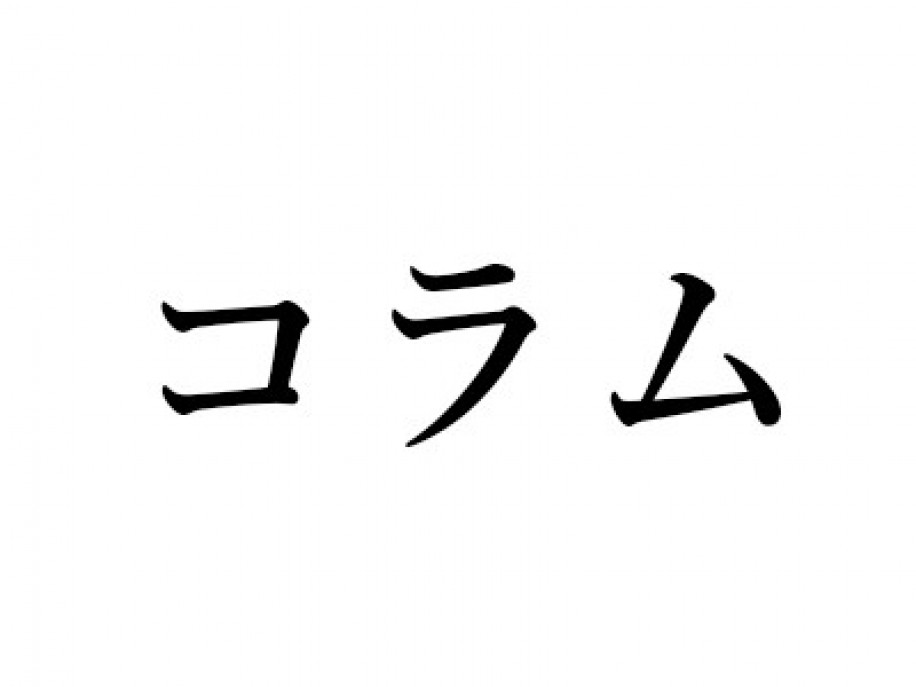書評
『家紋の話』(KADOKAWA/角川学芸出版)
職人技が生んだ洗練、家系由来と離し考察
作家泡坂妻夫氏が神田の松葉屋という紋章上絵師(もんしょううわえし)の三代目で、数十年紋を書いてきたとは意外である。もの心ついたころ、父の仕事場に転がっている紋帳を絵本がわりに見ていました。
紋は二、三千種もあり千差万別、一つとして同じ形がない。豊富に添えられた図から、私の家のは舞鶴、母の実家は五三の桐、婚家のは違い鷹(たか)の羽と見当がついた。概して月や星、植物やつつましく生きる小動物がよくとられるが、中には恋文とか因幡団子といった、形も名も珍しいかわいいものもある。
赤鳥という紋は何の形か、長いこと紋章師を悩ませていたが、これは櫛(くし)についた垢(あか)を取る化粧道具から来た紋なのだそうだ。
私が紋帳を拡げて、いつもつくづくと感心するのは、どれ一つとっても「紋になっている」ことです。
たしかにそうだ。紋は紋であり、デザインやマークではない。そして時代とともに変化し完成される。いままで紋章学というと家系や由来ばかりが尊重され、紋そのものの隙(すき)のない美しさは見過ごされがちであった。古い紋帳ばかりが尊ばれ、それを洗練、完成させようとする職人の技はむしろ蔑視(べっし)された。著者は職人らしい律義さでこれに反論する。
「二つ引き」という横二本線がいかに丸で囲むと安定し格調高くなるか、輪と中心の円の発見、その輪の太さ細さ、図形を丸に収める工夫。
鶴、鳩、海老もすぐ丸くなる動物です。
抱き、対、違い、重ねという手法、紋を派手にする工夫、地味にする「陰」という工夫。ちょっとお洒落な乱れ菊や踊り蟹。
どの家家も姓と一緒に、紋を持っている国は日本しかありません。
さらに、「曽我物語」の仇(かたき)を探す紋尽くしのくだり、下賜された桐や菊を誇示した秀吉と、辞退して葵の紋を独占した家康の話、篭形紋とダビデの星、万字とナチスのハーケンクロイツとの比較まで縦横に語って飽きない。
昔の職人はアパートでも持とうものなら「腕に自信がないから家作をつくった」といわれたそうだ。その丹精をこめた品を大切に扱わない時代への義憤のようなものが、静かな語り口から伝わってくる。
朝日新聞 1998年1月25日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする