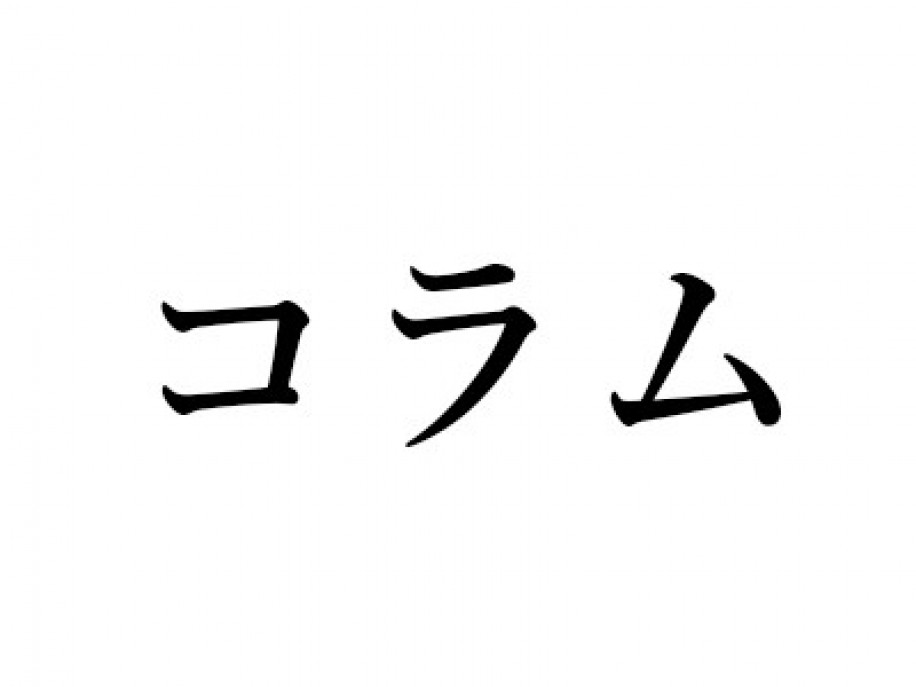書評
『アメリカの鏡・日本 完全版』(KADOKAWA/角川学芸出版)
内なる自分裁いた占領政策
ヘレン・ミアーズという一アメリカ人女性が見た日本。それも半世紀前のこと。彼女はGHQ労働関係諮問委員会のメンバーとして来日。帰国後書いた本書がアメリカではセンセーショナルな話題を呼ぶ。何とマッカーサーによって翻訳出版を禁じられたからだ。しかしさすがに当時の文芸春秋は慧眼だ。占領終了後、早速翻訳出版(「アメリカの反省」、原百代訳)がなされた。もっともその後アメリカでも日本でも、なぜか彼女のことは急速に忘れ去られた。本書の刊行は、まさにこうした戦後五十年の来し方行く末を考えさせる恰好の契機となろう(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年)。
では本書は、いったいいかなる衝撃力を持っているのか。それは端的に本書の標題に現れている。「アメリカの鏡・日本」。著者のメッセージは「私たちが改革しようとしている日本は、私たちが最初の教育と改革でつくり出した日本なのだ」ということに尽きる。そもそも黒船来航から占領に至る日本の近代化は、明らかにアメリカを始めとする西洋を鏡としていた。しかし日米関係が破局にむかう中で、アメリカは常に異質の国として日本をとり扱ってきた。そして今や改革の担い手たるアメリカは、実は自分の似姿として鏡に写る日本を、そうとは知らず裁こうとしている。
本来裁かれるのは、遠い異質の国日本ではなく、アメリカ自らの内なる日本ではないのか。楽観的な人道主義と恐ろしいまでの無神経さが裏腹となったアメリカの占領政策の二重人格性を告発する著者は、およそアメリカのアジアに対する態度の二重基準(ダブルスタンダード)を厳しく批判することになる。そこには今日再びホットなイシューと化した争点がすべて含まれている。
だが注意すべきは、戦争責任問題で日本の謝罪に断固反対する人々が、本書を百万の味方と思いこむことだ。本書はそうした人々のバイブルとなるような狭い見方に封じこめられるものではない。むしろ格別の学歴もなく日本専門家でもないにもかかわらず、ジャーナリストとしての好奇心に満ち満ちた著者のまなざしは意外なほどのびやかで、本書の構想力とスケールははるかに大きいと言わねばならない。
ALL REVIEWSをフォローする