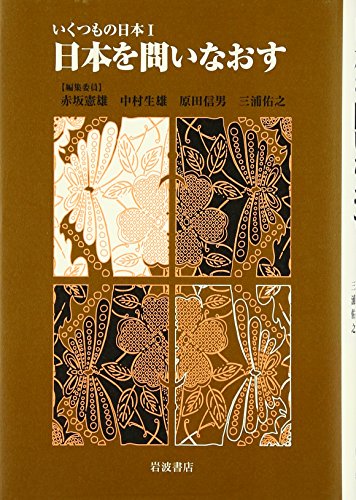書評
『宮廷政治 江戸城における細川家の生き残り戦略』(KADOKAWA)
細川家父子、書状で密な連携
三代家光に至る創生期の江戸幕府において大名たちはいかにすれば、とりつぶされることなく生き残りえたのか。本書は、「外様大名の典型的な優等生」と自他共に認めていた熊本藩の細川忠利と、父忠興との間の三千通近くに及ぶ往復書状を中心に、全部で一万通をこえる膨大な書状群を基に、この問題への一つの回答を示す。そこには、おそらく戦国乱世の時代には想像だにしなかった社会が出現しつつあった。一方で意思決定過程の制度化、すなわち将軍の権力の確立を背景に、組織や制度を通じてすべてのコトが処理されていく世界が確立する。他方でこの実務の世界と対置される形で、疑心と悪意と嫉妬心とに満ち満ちた噂話の世界も顕在化する。これを著者は宮廷社会と名づけた。
ではこの宮廷社会の中で、細川家はどの辺に位置していたのか。有力者との縁組を進め、おもねると言われんばかりに幕府に恭順の意を表明した黒田家。家臣との縁組を進め、江戸での交際を好まず幕府への自主独立の姿勢を貫いた島津家。実はおよそ対照的な両家の中間に細川家は位置づけられる。いわゆる幕閣の有力者との縁組は避けながらも、江戸人脈を増やし、たえず情報収集に目くばりして自家の安全をはかる用意周到さが、細川家の真骨頂であった。
かくて細心の注意を払いバランス感覚に富んだ優等生の忠利に対してさえ、宮廷社会の噂は容赦なかった。あまりに細々(こまごま)と幕府に報告しその指示を迎ぐ姿勢を、人は逆に不見識とみなしたからである。やはり宮廷社会は過ぎたるは及ばざるにしかずという世界なのであった。優等生たることが、そしられおとしめられる立派な理由になる。何とまあ底意地の悪い世界であろうか。
しかしこれを乗りきれたのは、何と言っても父と子の協力の賜物(たまもの)に他ならない。島原の乱の折、功をほこる忠利をきびしくたしなめた父忠興の態度に、それはよく現れている。
【旧版】
ALL REVIEWSをフォローする