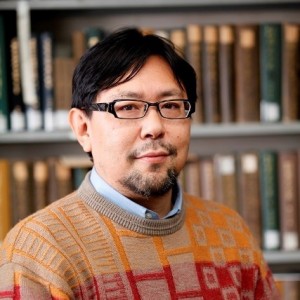書評
『大江戸御家相続 家を続けることはなぜ難しいか』(朝日新聞出版)
短命な大名が続けば家臣は路頭に迷うのだ
本書はお家が存続するために、徳川家をはじめとする江戸時代の大名たちが、いかに知恵を絞り尽力したかを教えてくれる。豊富な実例が平易な文章によって的確に紹介されていて、読了したときには大名の生活の一端が自然と理解できる、という仕掛けになっている。現在、日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超える。だが100年前は男女ともに40歳台前半だった。たしかに樋口一葉24歳、石川啄木26歳、正岡子規34歳と、若くして亡くなった有名人は少なくない。織田信長が愛した幸若舞(こうわかまい)には「人間五十年」とあるが、男女の寿命が50歳を超えたのは、実は太平洋戦争後のことなのだ。
江戸時代の大名の寿命の統計データは見当たらないが、少し実例に当たっただけでも相当に短命だったろうとは容易に想像がつく。考えてみれば、基本的に医学や衛生観念が発達していない上に、彼らは健康的な生活を送ろうという意識をもたない。行動範囲が狭く、適切な運動をしない。贅沢(ぜいたく)な食事を取り、何ごとも家臣まかせ。これでは長生きできるわけがない。
だが、大名の夭折(ようせつ)が続けば、家はつぶれてしまうのだ。それは社会的にもたいへんに困った事態であった。何となれば大名家には家臣がいて、家の廃絶は家臣とその家族が路頭に迷うことを意味するから。よく領地50石くらいに家臣1人、という式が用いられる。5万石の大名であれば家臣は1000人。家族を勘定すればおそらくは5000人以上。彼らの生活が大名一人の健康に左右される。
取り立てて名君でなくてもよい。ともかくも丈夫で、平穏な毎日を送ってくれれば。まさに「無事これ名馬」。そんな殿さま事情が透けて見えてくるような、興味の尽きぬ一冊である。
ALL REVIEWSをフォローする