書評
『江戸のパスポート: 旅の不安はどう解消されたか』(吉川弘文館)
旅人から歴史を見る
本書の出発点は江戸時代の旅行難民の実態調査である。いろいろな事情で国を離れ、旅先で辛苦する旅人たちは必ずしも放置されていたのではなく、途中で一定の「保護・救済制度」の恩恵にあずかっていた。それを保証したのが旅行者の身分に応じて藩の役所や菩提(ぼだい)寺、町村役人などが発行した「往来手形」である。この手形には持参者の身元保証、宗門の別、旅行目的の他に「諸御国宿々村々御役人衆」などに宛て、緊急時の旅宿の世話、急病の治療、死亡時の処置などを依頼する項目もあった。
著者は往来手形を現行の外国用パスポートに先行する「国内用パスポート」と規定。その結果、本書の射程は、不法入国者、失業移民、違法滞在者など世界規模で表面化している現代的な問題にまで広がることになった。中近東の大量難民、メキシコから米国へ越境する不法就労者のような現代の流民は、江戸時代に類例を求めるならば欠落人(かけおちにん)(農村逃散(ちょうさん)者)、無宿人のたぐいだろう。
著者によれば、社会の変化を反映した移動人口の推移に伴って、往来手形の内容も時代とともに無宿人を主たる対象とするものに変化してゆく。
江戸時代は後半、それも末期に至ると、その初期から抱え込んでいた遊休人口問題が表面化する。偽の往来手形を作ってでも旅に出る必要が全社会をのみ込むのだ。
従来はただ身分秩序からの脱落者にすぎなかった浪人は、幕末には確信犯な脱藩者、反体制的な浮浪の徒と化した。江戸や大坂などへ流入した農村人口はやがて江戸や大坂に膨大な「その日暮らし」層を形成した。
江戸時代は封建社会とされてきたが、その実、封建的政治支配だけを残し、全国的な市場ができかけていた社会ではないか。少なくとも、労働力市場は藩境を越えて広がっていた。本書は、歴史のイメージを大きく変える手がかりになる一冊だ。
[書き手] 野口武彦(のぐち たけひこ)文芸評論家・神戸大学名誉教授
初出メディア
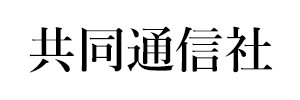
共同通信社 2016年10月
ALL REVIEWSをフォローする





































