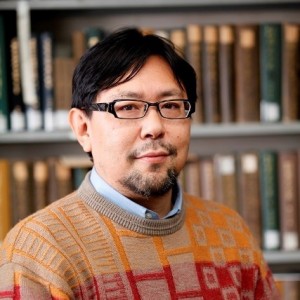書評
『江戸暮らしの内側-快適で平和に生きる知恵』(中央公論新社)
明日への希望によって庶民の社会が成立した
人間は時間軸にそって暮らしやすさを獲得していくのだと、ぼくは考えている。古代はロマンだと過大評価する人がいるがそれは誤りだ。大まかに見れば、すべてに未熟な古代より人の息吹が感じられるようになる中世、争いの中世より平和な近世、世襲ばかりで息の詰まる近世より自由で平等な近現代がすぐれている。もちろん太平洋戦争では300万人あまりの未曽有の犠牲者が出ているではないかという指摘はあるだろうが、それを含めて、人は昨日の過ちを反省しながら賢くなるのだと思う。そうした視点をもつぼくは、森田さんの考え方にふれ、まさにその通り、と思わず膝を叩(たた)いた。江戸時代の特徴は一に平和である、と森田さんは言う。それまでの動乱が終息して平和になったからこそ、人々は「明日」を考えられるようになる。親は子どもに教育を受けさせ、親方は弟子に技術を伝える。そうした明日のための投資の結果、一般庶民が主役の社会が形成される。思想家・石田梅岩(ばいがん)が言うように、各々が職分を全うして平和な生活を守り育てる。それが江戸の社会の基調なのだ……。実に明快な理論である。
そうは言っても、現代に比べれば、江戸時代はさまざまな点で貧しい。平均寿命はおそらく30代。制約も厳しい。でも人々は限られた資源を有効に活用して、暮らしに工夫を与えていた。その様子を「住・食・衣」の順に見ていきながら、やがて「生・老・病・死」という観念的な考察に進んでいく。
歴史は教科書に出てくる英雄が作るものではない。英雄たちは、多くの名もない人々の意志によって動かされているのだ。この意味で歴史の主役は、一般の民衆に他ならない。そのことを楽しく、しかし着実に教えてくれる本である。
ALL REVIEWSをフォローする