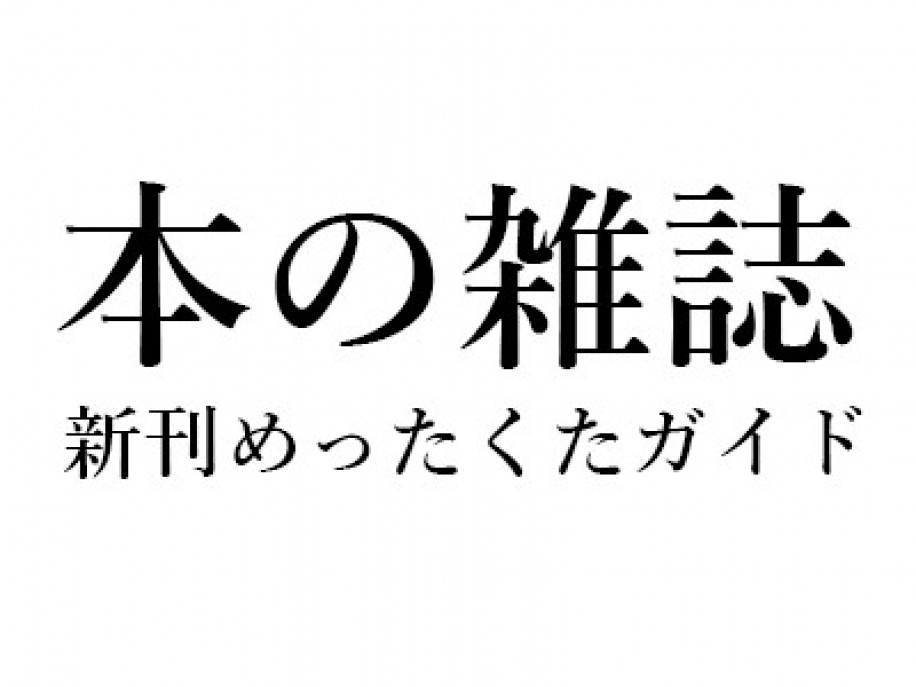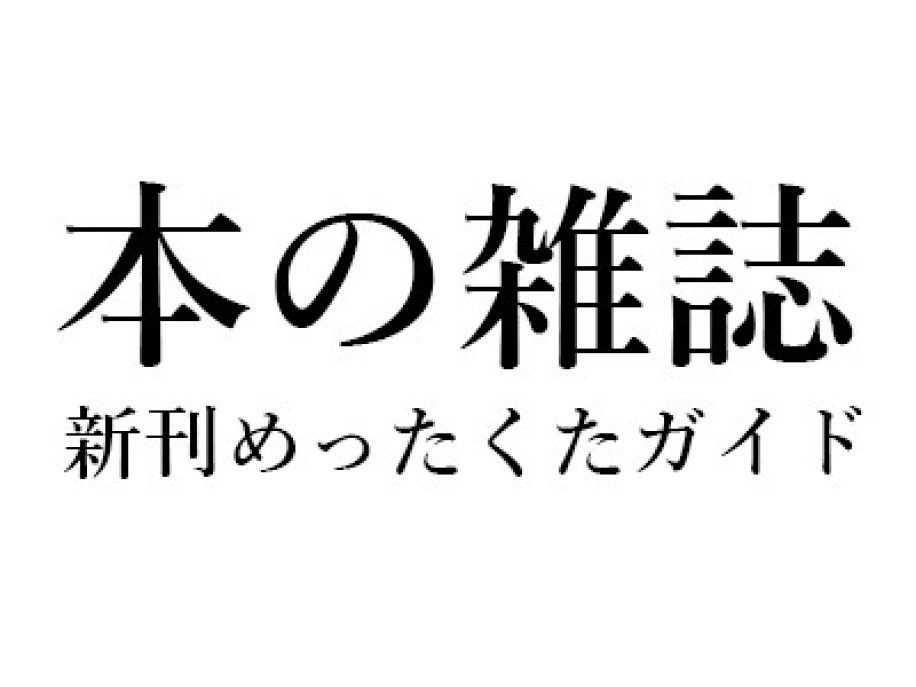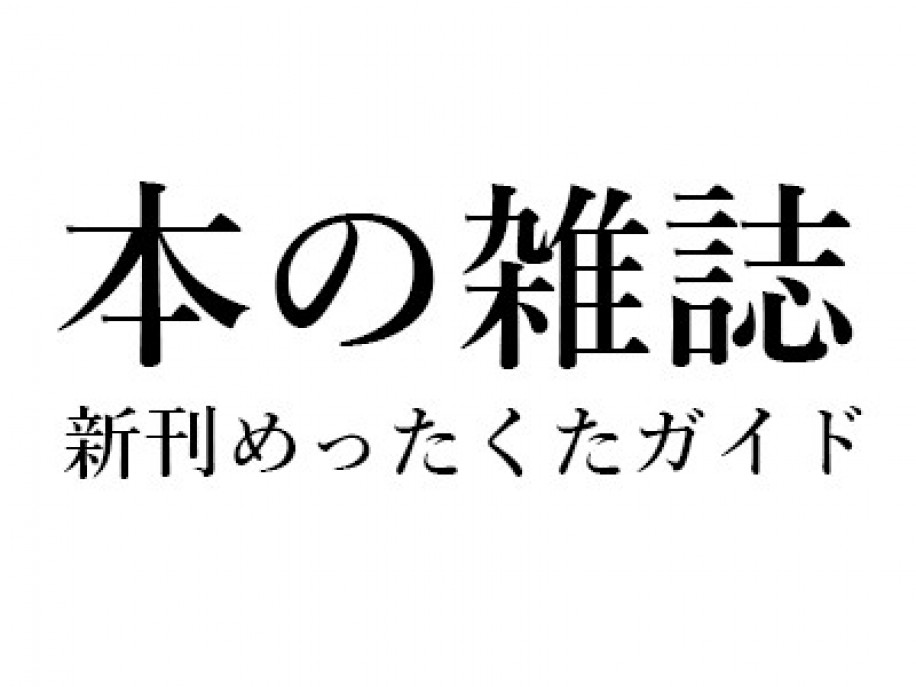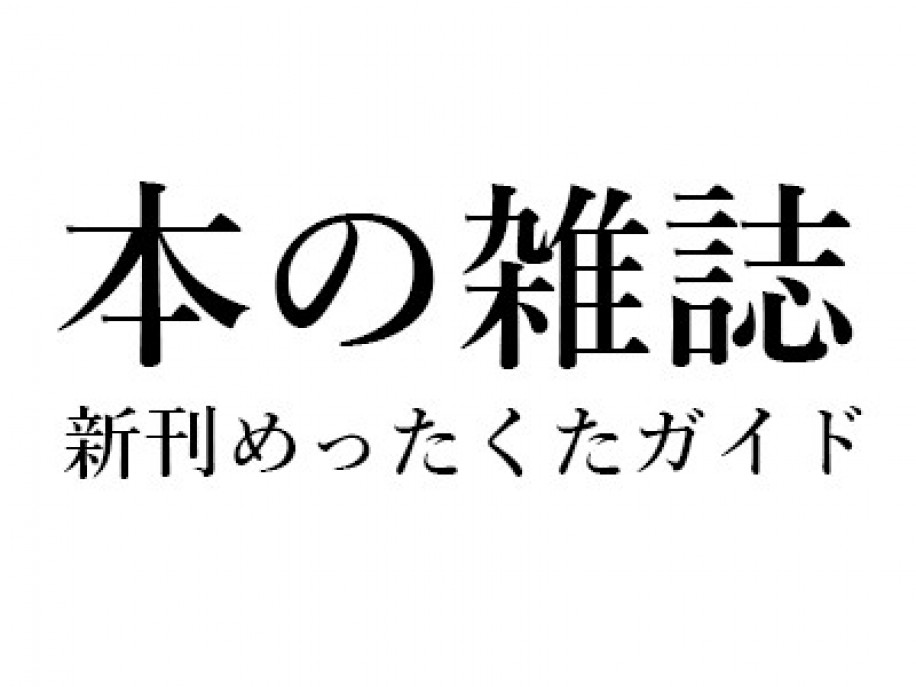読書日記
イアン・M・バンクス『ゲーム・プレイヤー』(角川書店)、デイヴィッド・ブリン『知性化の嵐1 変革への序章』(早川書房)ほか
イアン・M・バンクスの豪華絢爛宇宙冒険絵巻、『ゲーム・プレイヤー』に驚け!
今月(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2001年12月)は英米を代表する宇宙SFシリーズ三連発から。一番手は、スコットランド作家イアン・M・バンクスの『ゲーム・プレイヤー』(浅倉久志訳/角川文庫)★★★★。 英国発の豪華絢爛ワイドスクリーン・バロック型宇宙冒険絵巻《カルチャー》シリーズ、堂々の日本初上陸である。バンクスの邦訳は『蜂工場』『共鳴』『秘密』『フィアサム・エンジン』と過去四作あるが、判型もジャンルも訳者もバラバラで(全部読んでる人はたぶんすごく少数)、本国での人気と実力のわりに日本では地味な存在だった。そのイメージを一変させる(かもしれない)のがこれ。はるかな遠未来、銀河系全体に広がるゆるやかな文明集合体〈カルチャー〉を舞台とするこのシリーズは、〝SF作家〟バンクスの代表作。七冊出ている原書のうち、刊行順で第二作にあたる本書は、ゲームによる支配を実現した辺境の帝国に、銀河系一の〝ゲームの達人〟が殴り込みをかける──という恐ろしくストレートなゲームSFだが、そこはバンクスらしく、脇役に個性的なAI(趣味はバードウォッチング)を配し、エキゾチックなディテールと魅惑的なアイデアをちりばめてたっぷり楽しませてくれる。主人公の旅立ちまではちょっとかったるいが、そこを抜ければあとは一気の娯楽作。続巻の邦訳にも期待したい[と、ゲラを読んで書いたあと、届いた刊本を見て腰を抜かした。カバーが松本零士かよ! このキャプテン・ハーロックみたいな人は誰ですか? いくらなんでも中身と違いすぎるんじゃ……。予想通り売れなかったらしく、続巻は出てません。とほほ]。デイヴィッド・ブリン『知性化の嵐1 変革への序章』上下(酒井昭伸訳/ハヤカワ文庫SF)★★は、《知性化》シリーズ久々の新刊。といっても、全部で五千枚に達する大長篇の第一部だから、話はほとんど進まない。舞台は銀河協会によって知性種属の立入りが禁止された辺境の休閑惑星。ヒトを含む六種属がさまざまな事情でこの星に流れ着き、土着の生態系を乱すまいとひっそり隠れ住んでいる。そこに巨大宇宙船が飛来したからさあたいへん。隠れ里の平和な暮らしもこれまでか──と思いきや、どうも様子がおかしい。どうやら今度の訪問者も、銀河協会の目を盗んでよからぬことを企むならず者らしい……。この本筋以外に六種属の生態と〈属際連盟〉政治の舞台裏が複数視点から大量に描写され、あまりの長さにうんざりする。枝葉末節にこだわりすぎて、ストーリーテラーの本領を見失った感あり。
ロイス・マクマスター・ビジョルド『天空の遺産』(小木曽絢子訳/創元SF文庫)★★☆は、二十二歳のマイルズくんが主役。セタガンダ帝国の皇太后が急逝、外交使節として仇敵の惑星を弔問に訪れたマイルズだが、到着早々トラブルに──というパターンは『戦士志願』と同様。フーダニットっぽく始まった事件が例によってドタバタのうちに解決してしまうのが惜しい。今回、デンダリィ艦隊は登場せず、セタガンダ社会の(平安朝的な)異文化描写が読みどころだが、出来はいまいち。
一方、国産宇宙SFのイチ押しは、『侵略者の平和』に続く《那國文明圏》シリーズ第二弾、林譲治『暗黒太陽の目覚め』上下(ハルキ文庫)★★★★。那國・勘定奉行所から辺境の宇宙都市オデッサに派遣された代官、華表蓮蛇(とりいはすた)は、経済的自立を目指して芸者園の誘致に成功。が、那國を代表する大女優・桜叶(さかな)みさとを乗せた宇宙船が宇宙犯罪組織・龍党(ドラゴンパーテイー)に襲われたのを皮切りに、次々に災難が降りかかる。那國防衛軍・龍党・マヤ設計局の三つ巴の対立に巻き込まれたオデッサの運命やいかに……。人物のキャラ立ち、ディテール描写とネーミングのセンス、SF的アイデアの密度は申し分なく、予想を裏切るプロット展開(大ネタのはずし具合)も絶妙。前作同様、まとめにかかったときに話がぎくしゃくするのが唯一の欠陥か。佐藤道明のイラストもすばらしい。
それに続くのが、草上仁の『スター・ハンドラー』上下(ソノラマ文庫)★★★☆。細部のツメに甘さはあるが、万人向けのリーダビリティ、あっと驚くアイデア(まさかあんなものを暗号破りに使うとは!)ではこちらが上かも。異生物訓練士をヒロインに起用し、ティプトリー「われらなりに、テラよ、奉じるはきみだけ」の楽しさをユーモア冒険SF長篇に展開したような雰囲気で、中年読者にも強く推薦したい。同じソノラマ文庫の岩本隆雄『ミドリノツキ』上中下(→朝日ノベルズ)★★☆は、『星虫』アゲイン的な新世紀型ジュブナイル。いまどきの学園もの風の背景に大仕掛けなネタ(世界を救うエクスカリバー?)を異種配合した前半はすこぶる快調。ただし話がだんだん時代を逆行して、古色蒼然たる方向に進むのはどうか。
吉川良太郎『ボーイソプラノ』(徳間書店)★★☆は、『ペロー・ザ・キャット全仕事』で第二回日本SF新人賞を受賞した新鋭の第二作。《パレ・フラノ》三部作の第二部にあたる本書は、私立探偵の語り手(わたし)を主人公にしたチャンドラーばりのSFハードボイルド。ワイズクラックを連発する語り手の設定は笑っちゃうほど古典的だが、このタイプの〝高潔の騎士〟がかろうじて生き残れる場所は今やSFの領分にしかないのかも。
藤崎慎吾『螢女(ほたるめ)』(朝日ソノラマ→ハヤカワ文庫JA)★★☆も、『クリスタルサイレンス』で華麗なデビューを飾った著者の、待望の第二長篇。前作から一転して、伝奇ホラー的なモチーフを生態系SFとして語り直す。ストーリーテリングの実力とチャレンジ精神は評価したいが、SFとしては疑似科学的な説明の入れ方が中途半端。話の構造はSFなのに、どうも理屈が納得しきれないので、伝奇小説に見える。一方、梅原克文の連作集『サイファイ・ムーン』(集英社)★★★は、ニューエイジ風味(バイオタイド理論を採用)の伝奇ホラー。
「SFじゃなくてサイファイだ!」と言われれば、はあそうですかすみませんてな感じだが、あいかわらず冗長性が高くて演説が多いのが難。ただし、オマケのアルジャーノン・パロディには爆笑しました。牧野修『呪禁官(じゅきんかん)』(祥伝社NONノベル)★★★☆は、オカルトと科学の関係が逆転した世界で展開するハリポタ風学園SF。この逆転に無理やりロジカルな説明をつけるのが牧野流。『知の欺瞞』のソーカル事件までネタにしちゃうお茶目ぶりが楽しい。川端裕人『The S.O.U.P.』(角川書店)★★★☆は、今や電脳SFが現代サスペンスとして成立することを実証した一冊。日本の小説には珍しく、ハッカー倫理を正面から扱い、かなり踏み込んで描写している。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする