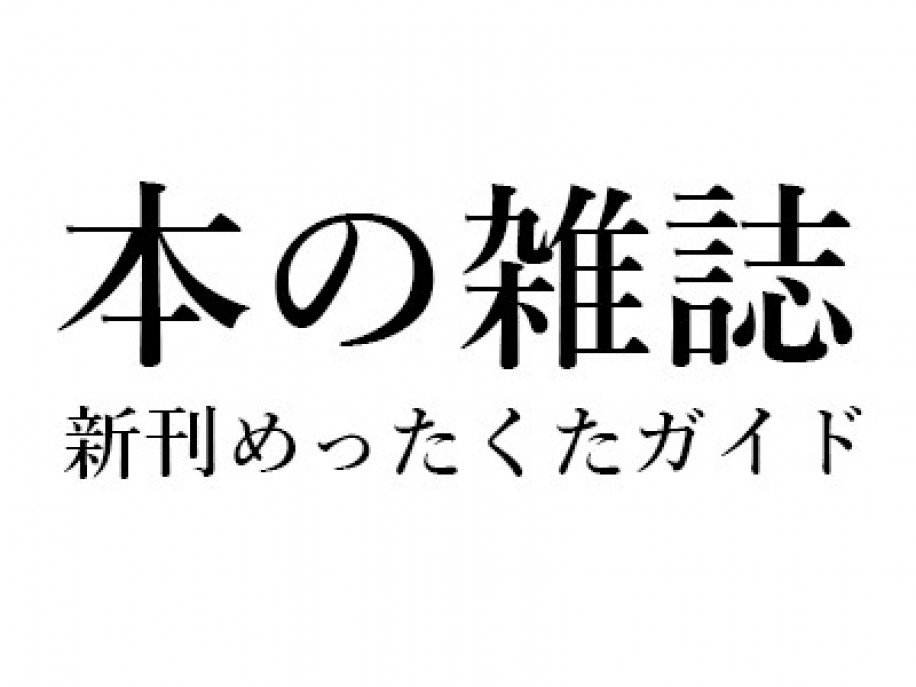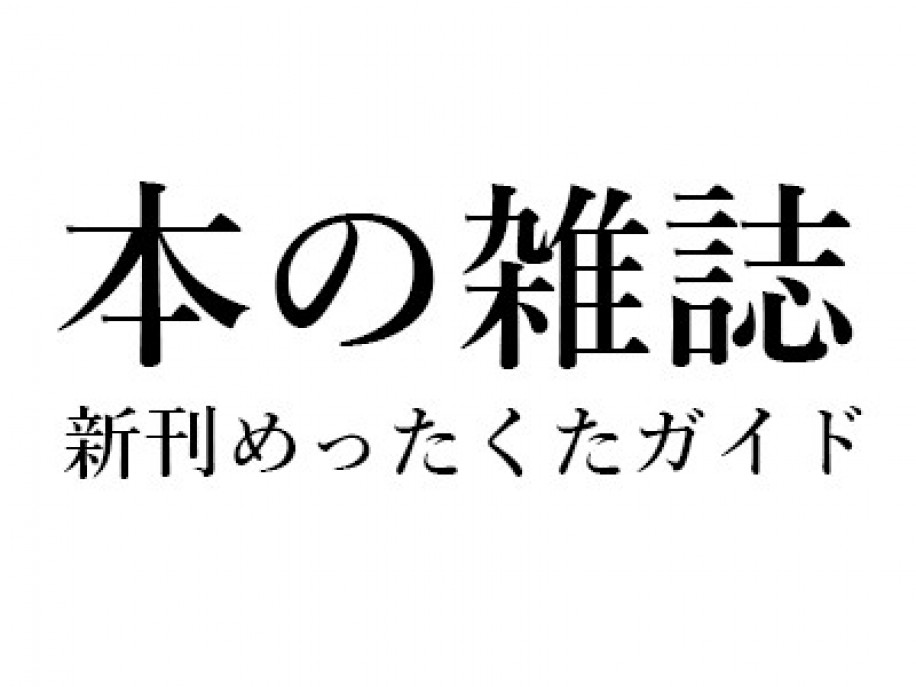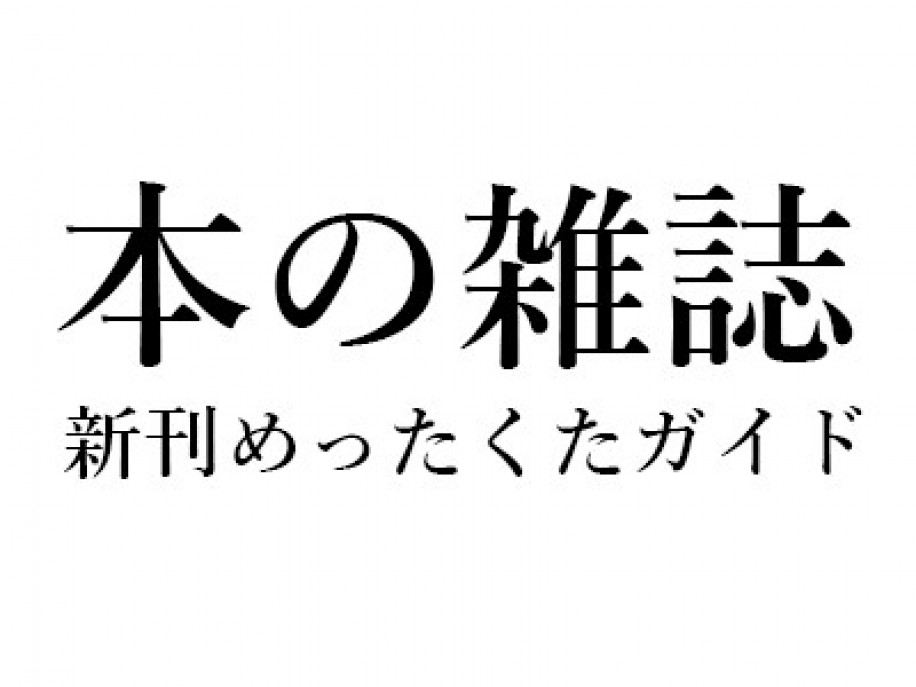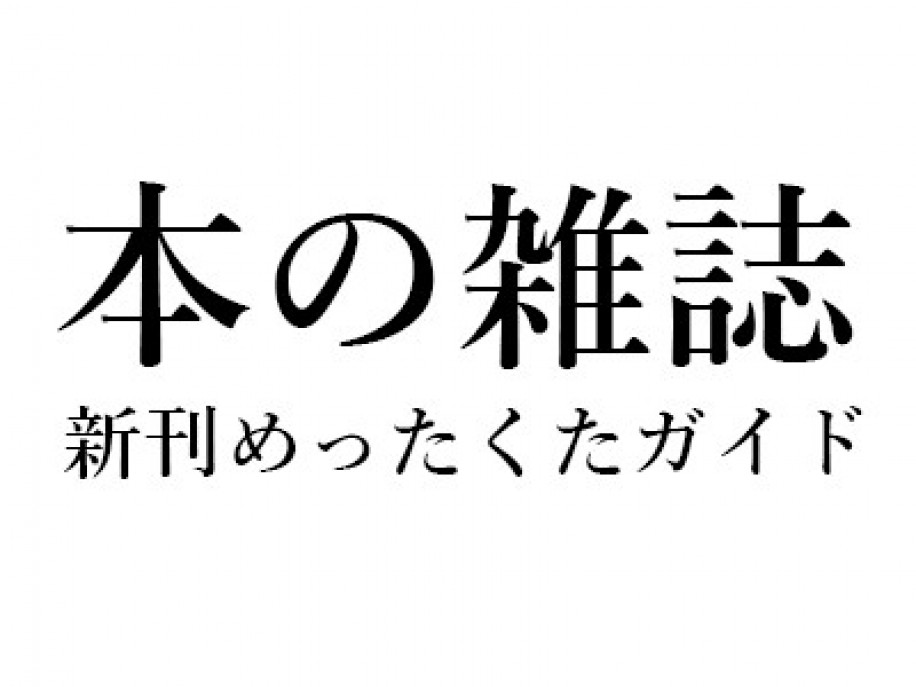読書日記
イアン・ワトスン『オルガスマシン』(コアマガジン)、ブライアン・ステイブルフォード『地を継ぐ者』(早川書房)ほか
イアン・ワトスン幻の処女長篇『オルガスマシン』世界初公開!
今月のオープニングシュートは、イアン・ワトスン幻の処女長篇『オルガスマシン』(大島豊訳/コアマガジン)★★★★(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2001年8月)。いくらスピルバーグ効果(映画「A.I.」の脚本に参加していたことがある)とはいえ、ワトスンはキューブリックに呼ばれてこんな本が出てしまったこと自体が今世紀最大の驚きで、なにしろこれは英語版がどこにも存在しない、事実上の日本オリジナル出版なのである。そのへんの事情はワトスン自身が日本向けの序文で詳しく書いてますが、だからといって〝英米で出版を拒否された過激SFポルノ〟みたいなキワモノではまったくない。主役は、顧客の好みに合わせて注文生産された異形のカスタムメイド・ガールたち。乳房がシガレット・ケースになってるパーティ・コンパニオン仕様をはじめ、『家畜人ヤプー』もかくやの極端な改造ぶりが凄まじい。製造工場から注文主の元に配達された彼女たちがたどる数奇な運命が物語の主軸。処女作だけあって描写の密度は圧倒的で、サイバーパンクを先取りしたようなディテールとアイデアはSFマニア感涙。八○年代に全面改訂された結果、後半は娯楽SF長篇としても一本びしっと筋が通り、活劇のスリルも楽しめる。ふつうの書店にはなかなか並ばない少部数・高定価本なので、くれぐれもお見逃しなく。翻訳SF長篇もう一冊は、同じく英国の中堅作家、ブライアン・ステイブルフォードの『地を継ぐ者』(嶋田洋一訳/ハヤカワ文庫SF)★★★。舞台は二二世紀で、ナノテクSFとしては、ベア『女王天使』とリンダ・ナガタ『極微機械(ナノマシン)ボーア・メイカー』の中間ぐらいの時代設定か。世の中それなりに変わってるんだけど(不妊化伝染病の流行で定着した人工出産とナノテク長寿が人口の均衡を保っている)、理解しにくいほど異質ではない。同じ不老ネタでもスターリングの『ホーリー・ファイアー』なんかと違って、背景よりプロット重視。老人が保守的なのは人生の残り時間が短いせいだから、不死が保証されたとたん事情が一変する──みたいな魅力的なアイデアもあるが、さほど突っ込んで議論されることはない。ソツがなさすぎて物足りないが、野心的じゃなくて読みやすいふつうの娯楽SFとしては悪くない。
……というコメントは、第二回日本SF新人賞を同時受賞し、徳間書店から四六判で同時刊行された二作にもあてはまる。作品は、谷口裕貴『ドッグファイト』★★★と、吉川良太郎『ペロー・ザ・キャット全仕事』★★★☆。どちらも八○年代アメリカSFをお手本にティーンズノベル風味少々を加えてきっちり消化。学習能力の高さは小説が証明しているが、答案がちょっと優等生すぎる。『ドッグファイト』は、デイヴィッド・ブリン『知性化戦争』系列のレジスタンスもの。ネオチンパンジーのかわりに、多少の遺伝子改造を施された犬たちが活躍する。敵は圧倒的な火力を有する統治軍。わがほうの主力は〝犬飼い〟と呼ばれるテレパスで、精神でつながった犬たちを使って敵と戦う中盤の山場がすばらしい。ただし、賞の枚数制限ゆえか、後半は書き込み不足が目立ち、シナリオっぽくなるのが惜しい。
対する『ペロー…』は猫が主役。ウィリアム・ギブスンのキャラ(記憶屋ジョニイとか)をブーダイーンに放り込んだ感じの、しごく繊細(テクニカル)で様式的(スタイリツシュ)な和製サイバーノワール。二十四歳の新人のデビュー作としては文句なしの完成度だが、メインプロットはやや借り物っぽい(のはご本尊のギブスンも一緒か)。……とまあ、ともに文句はあるものの、SFガジェットばりばりのこうした国産娯楽SFが四六判ハードカバーで出ることは大いに歓迎したい。
『ペロー…』の主人公はloup chat(人猫)と呼ばれるが、京極夏彦『ルー゠ガルー 忌避すべき狼』(徳間書店→講談社文庫ほか)★★★☆は、近未来のloup garoux(人狼)譚。ただし、ウルフガイじゃないので変身はしません。謳い文句は〝近未来少女武侠小説〟だから、セーラームーン系の戦闘美少女ものとも読める。サイコサスペンス風の導入から前半はミステリ的に展開し、やがて少女版榎木津みたいなぶっ飛びキャラも登場、息つくヒマなく後半の活劇に雪崩れ込む。近未来の社会背景には《アニメージュ》誌で読者から募集したネタが投入されてますが、知らないと見分けるのは困難でしょう。いまどきの近未来SFとしては、まだちょっと説明しすぎかなあ。
徳間ついでにもう一冊、筒井康隆『大魔神』★★★は、幻に終わった映画のシナリオ。筒井的なギャグもちらほらあるが、映画化前提で書かれたものだけに、基本はふつうの大魔神。ていうか、今読むとむしろ「∀ガンダム」みたいですよ。驚きはないけど楽しく読めるし、寺田克也・菅原芳人・唐沢なをき・沙村広明を起用したビジュアルは超贅沢で、愛蔵度の高い一冊。
妹尾ゆふ子『チェンジリング 赤の誓ゲアス 約』(ハルキ文庫)★★★は、現代日本を舞台にした取り替え子譚。小野不由美『魔性の子』系列だが、こちらはケルト神話が下敷きなので、世界観はむしろ山岸凉子『妖精王』に近い。OLのヒロイン像はリアルだし、関係者のインタビューが挿入される仕掛けも面白いが、全体的なまとまりはいまいち。続刊に期待。
佐藤哲也の『ぬかるんでから』(文藝春秋)★★★☆は、ファンタジーノベル大賞作家の第一短篇集。基本は家族をめぐる不条理SF──じゃなくて、今なら椎名誠流に超常小説と呼ぶべきか。オレは「祖父帰る」に爆笑したけど、あまりにも独特なユーモア感覚は万人向けじゃないかも。SF的にわかりやすいのは、とんでもない春が来てしまう「春の訪れ」。八○年代筒井康隆やエリック・マコーマックの短篇が好きな人はぜひ。
今月最後の一冊は、第8回日本ホラー小説大賞を受賞した伊島りすと『ジュリエット』(角川書店)★★★★。開発計画が頓挫し、半ば廃墟と化した南の島の無人リゾート施設に管理人として赴任した親子三人に、やがて怪現象が忍び寄る──と要約すれば、あからさまに『シャイニング』な設定ですが、SF読者にはむしろ日本版『ソラリス』として強く推したい。これこそ現代国産本格ホラーの王道かも。長編賞・短編賞受賞作はまた来月。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする