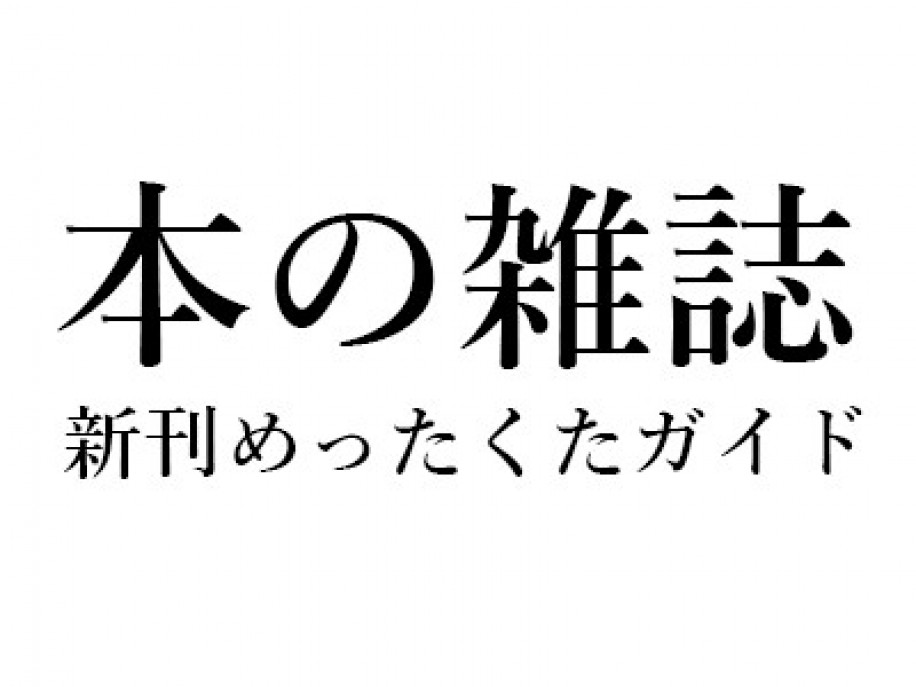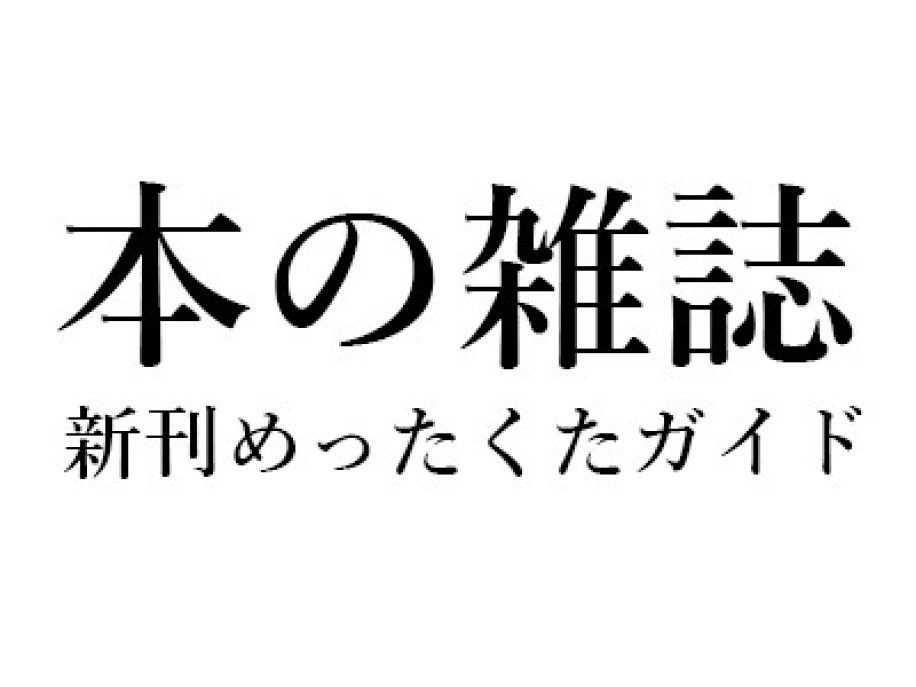書評
『驚異の発明家の形見函〈上〉』(東京創元社)
「競売番号六十七番、骨董品の函。四十五センチ×六十三センチ。起源不詳。十九世紀」
一九八三年、パリのオークションで「わたし」は奇妙な骨董品と出会う。それは十八世紀末から十九世紀にかけて盛んだったメメント・ホミーネム。函を組み立てた当人の個人史上でのある決定的な瞬間や、運命を変えた出来事にまつわる品々を収めた形見函だった。オークション会場で知り合ったイタリア人好事家によって、製作者の名を知らされた「わたし」は、フランス革命前夜のパリで自動人形の開発に心血を注いだ天才発明家クロード・パージュの生涯の謎を調べ、再現し、分解することにとり憑かれる。「広口壜・鸚鵡貝・編笠茸・木偶(でく)人形・金言・胸赤鶸(むねあかひわ)・時計・鈴・釦(ボタン)・空白」、十の仕切の中に収められた品々にまつわる思い出にそって綴られたクロードの生涯。それが、この読み応えたっぷりのビルドゥングスロマンなのである。
重なる近親結婚の末、肉体の一部が欠損または過剰な者が生まれるようになったフランス片田舎のトゥールネー。一七八〇年、その谷間の村を襲った大嵐の晩、クロードの家に高名な外科医が訪れる。彼の右手中指と薬指の間にある、ルイ十六世の顔そっくりな黒子(ほくろ)を取り除くために。ところが、外科医は中指ごと切除。自分のコレクションに加えようと“広口壜”に入れて持ち帰ってしまう。怒り狂ったのは「尊師」と呼ばれる村の領主。この老人はかねてから、鋭敏な耳と観察眼、そして緻密なデッサン力を持つクロードの素質を見抜いており、将来を嘱望していたのだ。中指を失った哀しみに心沈ませる少年を、自邸に引き取り英才教育を施す尊師。が、ある事件が引き金となり、クロードは尊師のもとを離れ、一人パリへと去ってしまい――。
食いしん坊で気のいい御者ポールや、三文文士プルモーと育む友情、尊師の館で見た「縮写肖像画」のモデルであるユゴン夫人との青い恋、思うような仕事につけないパリでの下積み時代、トゥールネーを襲う大火事、尊師との再会、尊師がなし得なかった言葉を発する自動人形発明の夢、それを支えてくれる運命の女性との結婚。不思議、波瀾、失意、裏切り、愛、友情、夢、希望、挫折、成功に彩られたクロードの生涯は、まさにシュトゥルム・ウント・ドラング(疾風怒濤)一色だ。物語るカーズワイルのディケンズばりの声量の豊かさもあいまって、読者は読んでいて飽きるということがない。しかもその中には、知的好奇心の世紀たる十八世紀の魅力が、物語にしっくり馴染む形でさりげなく、しかし、存分に仕込まれてもいるのだ。
ニュートンの『光学(オプティックス)』や、ディドロ&ダランベールの『百科全書』が刊行され、ヴァガボンド(放浪者)取締法がなくなり、交通インフラが整備されたおかげで人びとの往来が激しくなり、物見遊山の旅グランド・ツアーが貴族の間で流行し、それによってピクチャレスク趣味が進み、一個人のキャビネット、ヴンダーカンマー(驚異の部屋)が寄贈されたのをきっかけに大英博物館条例が発令され、ここからパブリック・ミュージアムの歴史が始まり、世界初のジェットコースターが生まれ等々、科学と博物学と視覚文化と交通とコレクションと発明に彩られた十八世紀。しかも、この時代はオートマタ(自動人形)の全盛期でもあるのだから、本書の主人公である天才器械師クロードが生まれるのに、これほどふさわしい世紀もないのである。たとえば、本書中にもチェスを指す人形を作ったとして顔を出すヴォルフガング・フォン・ケンペレン。彼はまた話をする人形を生み出してもおり、オートマタ愛好家なら、初めはこの人物をクロードの面影に重ねるはずなのだ。また人形の発声装置に関して、クロードがヒントを得たとして言及されている「ヴォーカンソンの唇」。ヴォーカンソンは、唇と指と舌を動かしながらフルートで十二の旋律を奏でる笛吹き男という人形を発明した人物として知られている器械師なのだ。ドイツ文学愛好家なら、しかし、このヴォーカンソンの笛吹き男のことを、ホフマンが『自動人形』という短編小説の中で「厭(いと)わしいもの」として批判していることを思い出しもするだろう。
クロードの友人プルモーが書いた『クロード・パージュ――ある発明家の年代記』。それをイタリア人好事家から読ませてもらい、今度は自らクロードの生涯を物語にした「わたし」。そして、その物語はクロードが遺した形見函の構成をなぞっていて、というメタ・フィクショナルな構造を持つこの希有な小説は、「わたしが函を手に入れたのではなかった。函がわたしを手に入れたのである」という言葉で始まり、「事実がわたしを捉えるに任せよう」という言葉で締められている。これは“物語”そのものの隠喩に他ならない。作家も読者も物語を見つけたり、手に入れるのではない。わたしたちを捉え、手に入れるのが優れた物語というべきなんである。十八世紀という知的好奇心を満たしてくれる時代を背景にしながら、趣向はポストモダニスティックという、あらゆる点において驚異的な傑作。これが新人のデビュー作とは! それが一番の驚異かも。
【下巻】
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

Invitation(終刊) 2003年4月号
ALL REVIEWSをフォローする