書評
『あのころ、私たちはおとなだった』(文藝春秋)
アン・タイラーくらい女性が読んで共感できる作家も珍しい。彼女が繰り返し描くのは、大家族の中で日々夫や子供の世話に追いまくられる女性の疲労感であり、淋しさであり、ささやかな夢と幸福だ。ドラマ性に欠けた人生を生き、時に「こんな生活、もういやっ」と小さな悲鳴を上げたりもする。でも、決してそうした日常を放棄したりしない。そんな世界にごまんといるに違いない、頑張って踏ん張ってる女性たちに向けるアン・タイラーの視線は、温かく柔らかく大らかなのだ。
最新作『あのころ、私たちはおとなだった』の主人公は貸し宴会場「オープン・アームズ」を経営し、大家族のまとめ役として、日々奮闘している五十三歳のレベッカ。年上の男ジョーと恋に落ち、大学を中退して結婚、いきなり三人の娘の継母に。その後、実の娘もさずかったものの、結婚七年目にして夫は交通事故で他界。以来、四人の娘と夫の叔父さんの世話、宴会場の仕事に専心してきたレベッカだったのだけれど、ある日、こう叫んでしまう。「私はどこへ行ったんだろう? なぜ私はこんなふうにふるまっているんだろう? 私は自分の人生の詐欺師だ!」。かくしてレベッカは、「そうなっていたかもしれない人生」を夢想しはじめる。そして、十九歳の時にふった元恋人のウィルに連絡を取ってみるのだが――。
年をとるにつれ、大抵の人は「これでよかったのか」という不安に襲われ、人生の分岐点を思い返しては「あの時違った選択をしていたら」と後悔の念に駆られるものだ。このまま面倒見のいいおばあちゃんのまま終わってしまいそうな人生。そこに、劇的な句読点を打ちたいと願うレベッカに、だからわたしたちは共感を覚えずにはいられない。しかし、人生は今・此処(ここ)で続いていく。かつて・どこかから出発して形作られた現在の自分を消し去ることなどできはしない。ささやかな反抗と冒険の末に、レベッカが選択するこれからの人生とは?
同じ場所で繰り返される代わり映えのしない日々を引き受ける。そんな平凡な覚悟が生み出す、ささやかだけれどとても豊かな何か。アン・タイラーはその何かをユーモアたっぷりの筆致で浮かび上がらせる。そう、彼女の小説には、辛辣だったり、ハート・ウォーミングだったり、ほろ苦かったりと、様々なタイプの笑いが仕込まれているのだ。
たとえば、昔の恋人ウィルと三十年ぶりに再会するシーン。レストランでウエートレスから、待ち合わせをしているのは「あちらの方ですか?」と訊かれ、「レベッカは娘の視線を追った。(中略)一組は若いカップル。もう一つのテーブルには痩せた老人が一人で坐っていた。『いいえ』とレベッカは言った。それから、『ああ』と言った」
「あるある!」ってシチュエーションでしょ。自分だって太ったおばさんと化しているのに、レベッカがウィルをとらえる視線の容赦のなさといったら! その後のウィルとのつきあい方の身勝手さときたらっ! その他、百歳の誕生日を迎えるジョーの叔父さん、ボビーのまだらボケな言動や、四人の娘たちが巻き起こす騒動など、笑いには事欠かない上に、胸にジンと滲みるフレーズもてんこ盛りなのだ。その中で、わたしが一等好きなのは、ジョーに初めて声をかけられた瞬間を思い出したレベッカのこんな感慨。
「ある瞬間に――人生のターニングポイントとなるある瞬間に――そのあとに続くすべてのことの芽が含まれ、体を縮めて待っているなんて、なんと不思議なことだろう」
この“オープン・アームズ”(包容力)な物語は、あなたの今・此処のかけがえのなさを思い出させてくれ、今・此処からの不思議を垣間見せてくれるに違いない。
【この書評が収録されている書籍】
最新作『あのころ、私たちはおとなだった』の主人公は貸し宴会場「オープン・アームズ」を経営し、大家族のまとめ役として、日々奮闘している五十三歳のレベッカ。年上の男ジョーと恋に落ち、大学を中退して結婚、いきなり三人の娘の継母に。その後、実の娘もさずかったものの、結婚七年目にして夫は交通事故で他界。以来、四人の娘と夫の叔父さんの世話、宴会場の仕事に専心してきたレベッカだったのだけれど、ある日、こう叫んでしまう。「私はどこへ行ったんだろう? なぜ私はこんなふうにふるまっているんだろう? 私は自分の人生の詐欺師だ!」。かくしてレベッカは、「そうなっていたかもしれない人生」を夢想しはじめる。そして、十九歳の時にふった元恋人のウィルに連絡を取ってみるのだが――。
年をとるにつれ、大抵の人は「これでよかったのか」という不安に襲われ、人生の分岐点を思い返しては「あの時違った選択をしていたら」と後悔の念に駆られるものだ。このまま面倒見のいいおばあちゃんのまま終わってしまいそうな人生。そこに、劇的な句読点を打ちたいと願うレベッカに、だからわたしたちは共感を覚えずにはいられない。しかし、人生は今・此処(ここ)で続いていく。かつて・どこかから出発して形作られた現在の自分を消し去ることなどできはしない。ささやかな反抗と冒険の末に、レベッカが選択するこれからの人生とは?
同じ場所で繰り返される代わり映えのしない日々を引き受ける。そんな平凡な覚悟が生み出す、ささやかだけれどとても豊かな何か。アン・タイラーはその何かをユーモアたっぷりの筆致で浮かび上がらせる。そう、彼女の小説には、辛辣だったり、ハート・ウォーミングだったり、ほろ苦かったりと、様々なタイプの笑いが仕込まれているのだ。
たとえば、昔の恋人ウィルと三十年ぶりに再会するシーン。レストランでウエートレスから、待ち合わせをしているのは「あちらの方ですか?」と訊かれ、「レベッカは娘の視線を追った。(中略)一組は若いカップル。もう一つのテーブルには痩せた老人が一人で坐っていた。『いいえ』とレベッカは言った。それから、『ああ』と言った」
「あるある!」ってシチュエーションでしょ。自分だって太ったおばさんと化しているのに、レベッカがウィルをとらえる視線の容赦のなさといったら! その後のウィルとのつきあい方の身勝手さときたらっ! その他、百歳の誕生日を迎えるジョーの叔父さん、ボビーのまだらボケな言動や、四人の娘たちが巻き起こす騒動など、笑いには事欠かない上に、胸にジンと滲みるフレーズもてんこ盛りなのだ。その中で、わたしが一等好きなのは、ジョーに初めて声をかけられた瞬間を思い出したレベッカのこんな感慨。
「ある瞬間に――人生のターニングポイントとなるある瞬間に――そのあとに続くすべてのことの芽が含まれ、体を縮めて待っているなんて、なんと不思議なことだろう」
この“オープン・アームズ”(包容力)な物語は、あなたの今・此処のかけがえのなさを思い出させてくれ、今・此処からの不思議を垣間見せてくれるに違いない。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
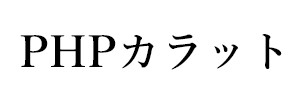
PHPカラット(終刊) 2003年12月号
ALL REVIEWSをフォローする


































